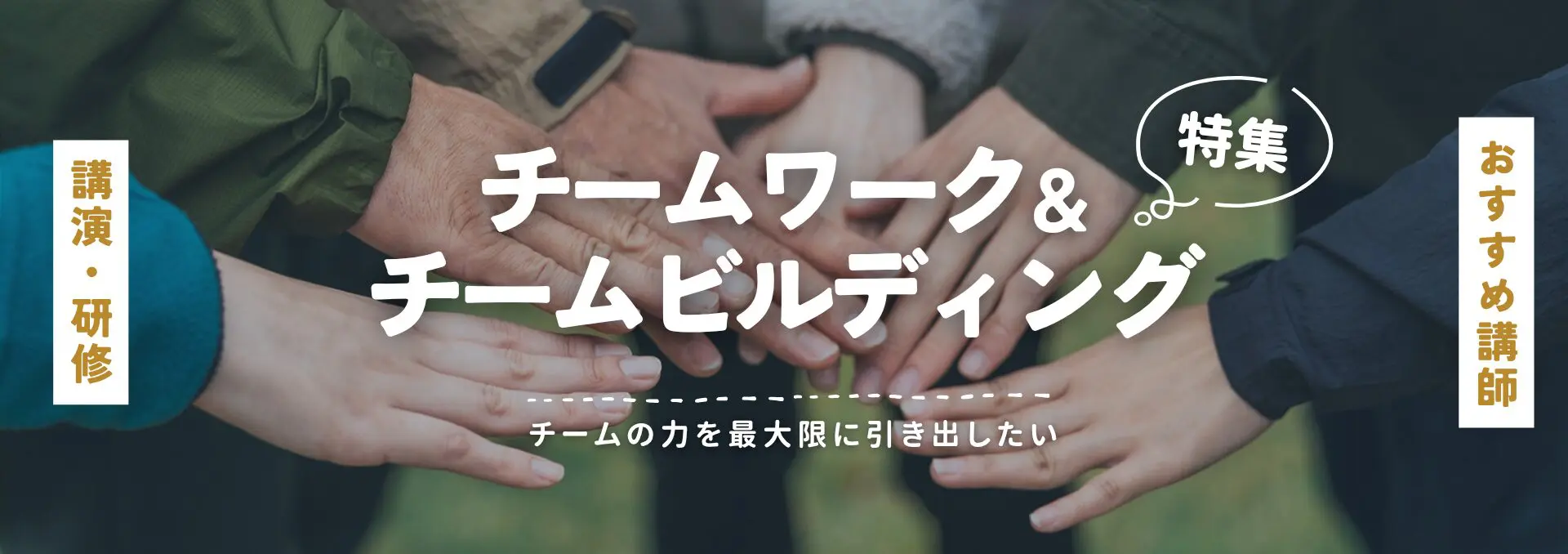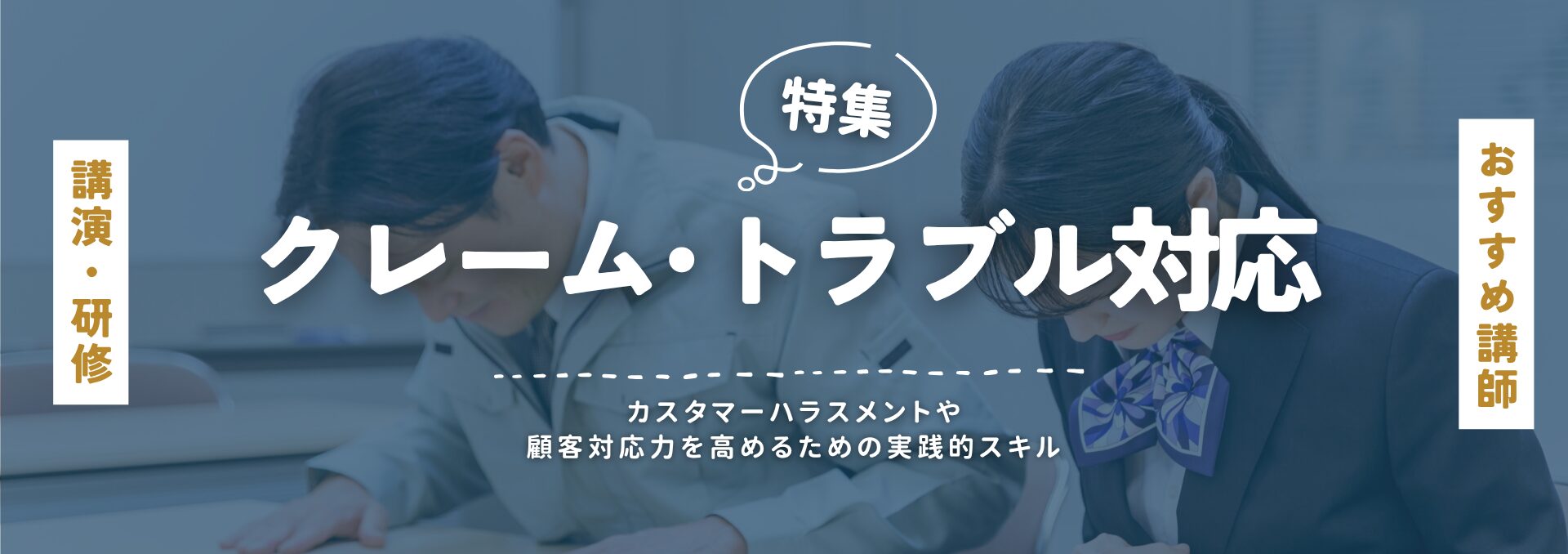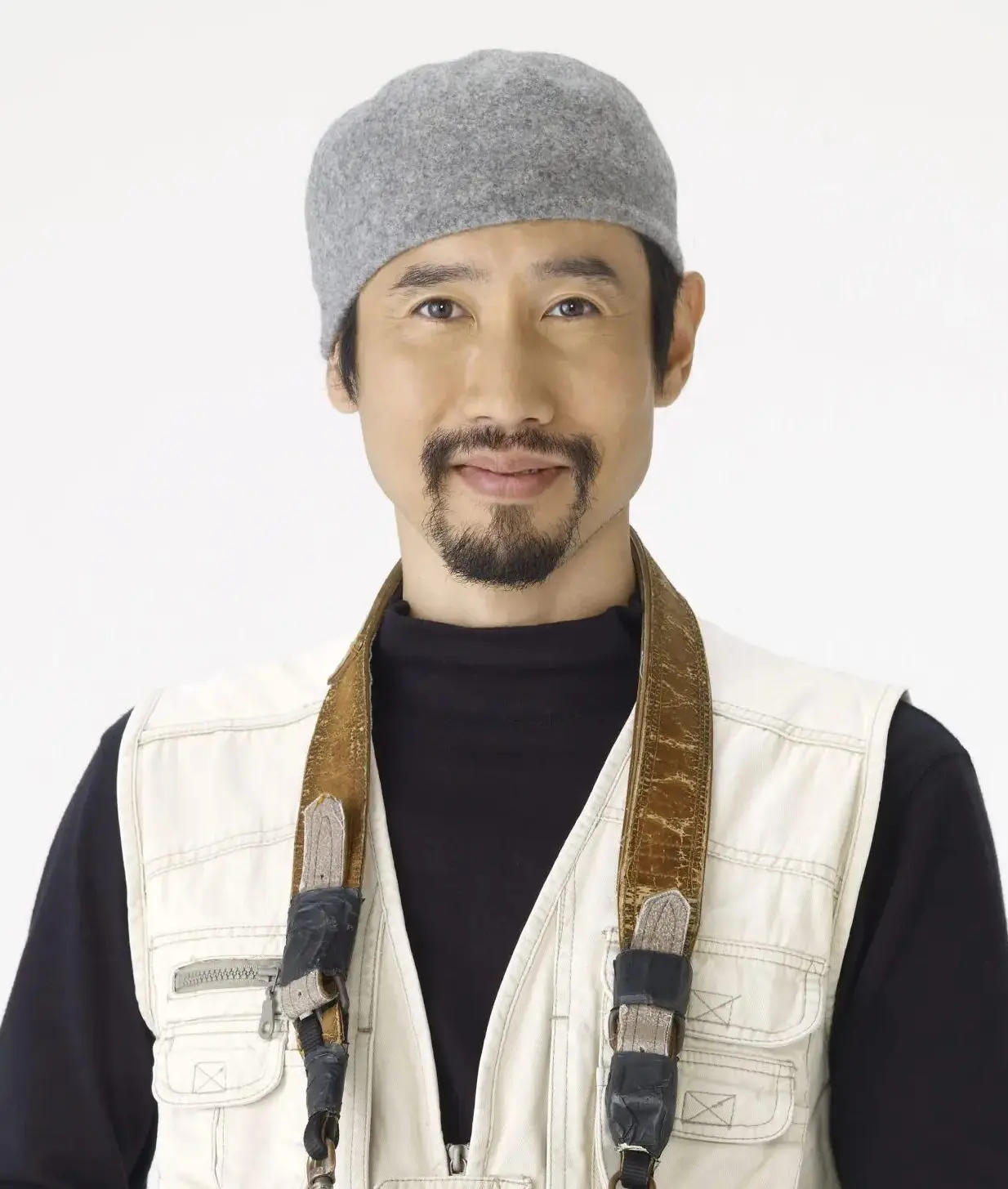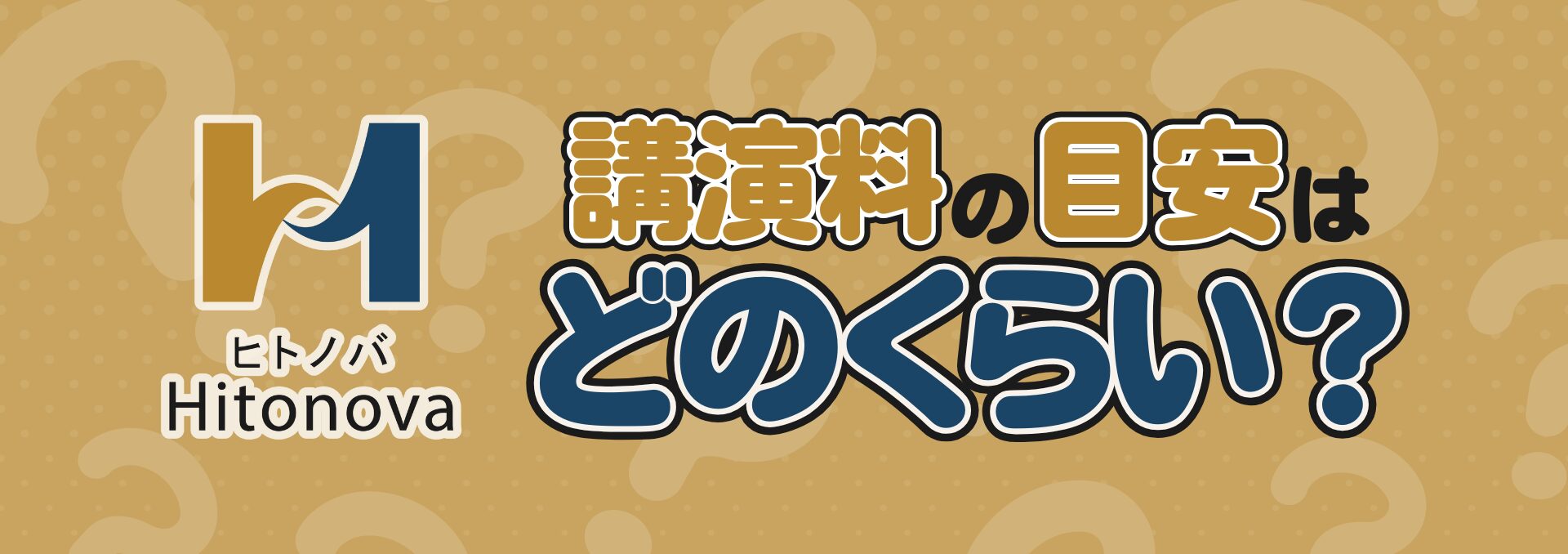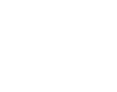野村彩 のむらあや
弁護士/公認不正検査士
プロフィール
企業における不祥事や内部通報制度の運用、ガバナンス体制の構築、役員の法的責任、ハラスメントへの対応などを中心に実務を行う弁護士。公認不正検査士(CFE)の資格を有し、複数の上場企業において社外役員としても活動している。セミナーでは、コンプライアンスやハラスメント対策、企業の危機対応力強化、民法・会社法関連のテーマを取り上げ、実務に即した情報を発信。専門的な知見をもとに、新聞・雑誌・ウェブメディアなどでの寄稿や連載も行っている。
テーマ
出身・ゆかりの地
経歴
1977年生まれ、神奈川県出身。神奈川県立湘南高等学校を卒業後、慶應義塾大学法学部政治学科を経て、立教大学大学院法務研究科(法科大学院)を修了。2006年に司法試験合格、2007年12月より弁護士登録(第二東京弁護士会)。
企業法務・訴訟を主軸とする鳥飼総合法律事務所にて弁護士としてのキャリアをスタートし、2016年より和田倉門法律事務所に参画。上場企業の社外役員や各種審査委員なども歴任しており、2022年以降は株式会社GENDA社外取締役(任期満了で退任)、株式会社ACES社外監査役、日本郵政グループ内部通報制度不服審査委員会委員、株式会社アンドパッドおよび株式会社ニーリーの社外監査役を務める(いずれも現任)。
企業法務全般に加え、コーポレートガバナンス、内部通報制度、不正対応などの分野に精通。公認不正検査士(CFE)としての知見も活かし、企業のコンプライアンス体制強化やリスクマネジメントに貢献している。
また、第二東京弁護士会 金融商品取引法研究会、上場会社役員ガバナンスフォーラム、日本コーポレートガバナンス研究所アドバイザリーボード、日本コーポレートガバナンス・ネットワーク(CGネット)ダイバーシティ・ガバナンス研究会、ACFE内部通報研究会など、ガバナンス・不正対策分野に関わる多様な研究会に所属し、実務と理論の両面から活動を展開している。
主な講演テーマ
新任役員が知っておくべきコンプライアンス
新任役員が最初に直面する課題の一つが「コンプライアンスの理解と実践」です。この講演では、企業経営に不可欠な法令遵守の基本をはじめ、役員が果たすべき責任や留意点、実際の違反事例から学ぶリスク対応について解説します。役員就任直後の不安を払拭し、自信を持って職務を遂行するための土台を築きます。 ×
役員責任とは
~取締役受忍の時代~
経営判断の責任は年々重くなっており、「取締役受忍」の姿勢が求められる時代です。この講演では、取締役としての法的責任の範囲や、実際の訴訟リスク、監査役・社外取締役との役割の違いを具体的事例とともに紹介。リスクに備えた意思決定と対応策を明らかにします。 ×
コーポレートガバナンス・コードが求めるものとは
ガバナンス強化が求められる今、企業にとって「コーポレートガバナンス・コード」の理解は不可欠です。本講演では、その背景と意図、実務への影響をわかりやすく解説。取締役会の構成、多様性、情報開示、対話のあり方など、現場で何をすべきかを明確にします。 ×
役員報酬設計の現在
報酬制度は経営戦略と直結しており、社会からの説明責任も増しています。この講演では、近年の役員報酬設計のトレンドや規制、透明性の確保に向けた開示基準、報酬委員会の機能などを解説。企業価値と連動する報酬制度の構築を支援します。 ×
役員が知っておくべき株主総会の注意事項
株主総会は、企業とステークホルダーの信頼関係を左右する重要な場です。本講演では、総会準備から想定問答、当日の運営まで、役員として知っておくべきポイントを網羅。トラブルを未然に防ぐためのリスク管理の視点も学べます。 ×
内部統制とは何か
〜具体的なケースを用いて検討する〜
「内部統制」の理解なくして、健全な企業運営は成り立ちません。この講演では、実際に起こりうるケーススタディを通じて、内部統制の仕組みや実践方法を解説。部門間連携や責任体制の整備など、現場目線での導入・運用を提案します。 ×
不祥事の防止と内部通報制度
企業不祥事は信頼と経営を揺るがします。この講演では、通報制度の設計と運用の要点、通報者保護、企業としての対応プロセスについて解説。不正の芽を早期に摘むための実効性ある制度づくりをサポートします。 ×
役員のためのコンプライアンス研修
現代の企業経営において、役員に求められる法的・倫理的責任は年々重くなっています。コンプライアンス違反は、たとえ現場での問題であっても、経営陣の監督責任や内部統制構築義務の不履行として追及される時代です。
この研修では、役員特有のリスクに焦点を当て、「役員とは何か」「責任の範囲と回避策は何か」「ガバナンスは誰のためのものか」を、事例とワークを交えながら実践的に学びます。 ×
管理職のためのコンプライアンス研修
コンプライアンスは単なる「法令遵守」にとどまりません。企業が社会的信頼を維持し、持続的な成長を遂げていくためには、「法」「ルール」「倫理」の3軸でバランスの取れた実践が不可欠です。
本研修では、近年注目が高まるコンダクト・リスクの概念や、実際に社会問題化した事例(湯沸かし器死亡事故、解約違約金の炎上など)を取り上げ、法的にグレーでも企業に重大なダメージを与えるリスクの正体を可視化します。
また、社内・取引先双方で起こりがちなコンプライアンス違反(労務トラブル、パワハラ、下請法違反、カスタマーハラスメントなど)についても具体例を交えながら解説。実務で直面する場面に即したリスクの見極め方を学べます。
さらに、「不正が起きる企業の構造」「内部統制違反が問われた事案」「第三者委員会の役割」など、企業としての組織的対応の重要性を明らかにし、公益通報者保護法や内部通報制度の最新動向にも触れます。
有事対応では、「何よりも迅速性が重要」である理由、調査や再発防止策の設計まで、具体的なフローを共有。役職や部門を問わず、すべてのビジネスパーソンが知っておくべき知識と実践力を身につける内容です。 ×
管理職のための労務管理研修
~働き方改革をふまえて~
働き方改革を背景に、労務管理は一層複雑化しています。
この研修では、企業における労務管理の基本から、実務で直面しやすい課題までを体系的に学びます。特に、労働法令や社内規程の基礎、労働時間や休暇の取り扱い、問題社員対応、健康管理までを幅広く網羅。コンプライアンスの重要性やリスク管理の視点を取り入れながら、管理職として必要な知識と対応力を実践的に身につけていただきます。
「就業規則と給与規程の違いは?」「有給取得理由を聞いていいの?」「メンタル不調の社員への対応は?」といった、現場で迷いやすいトピックも豊富な事例をもとに解説。法的リスクを回避し、安心・安全な職場環境づくりをリードする管理職を目指す方に最適なプログラムです。 ×
役員のためのハラスメント研修
本研修は、ハラスメント問題を「企業不祥事」「ガバナンスリスク」として捉え、役員として果たすべき対応と責任を具体的に学ぶ内容です。パワーハラスメント防止法の施行や世代間ギャップに伴う認識の違い、そして近年の報道事例などを踏まえ、「なぜ今、ハラスメントが経営課題なのか」を再確認します。
ハラスメントの定義は一様ではなく、犯罪・懲戒処分・慰謝料請求・社内対処のいずれに該当するのかにより対応が異なります。本研修では、曖昧になりがちな境界線を、具体的なケーススタディとともに明確に整理。さらに、役員に求められる「内部統制構築義務」や「防止措置義務」についても、法的な裏付けとともに解説し、有事と平時それぞれの対応指針を提示します。
企業としての信頼と持続性を守るために、役員自身が知っておくべきポイントを総合的に押さえることができます。 ×
管理職のためのハラスメント研修
本研修では、管理職が日々のマネジメントにおいて直面する可能性の高いハラスメントの理解と、的確な対応力を習得することを目的としています。2020年のパワーハラスメント法制化以降、企業に求められる水準が高まる中、「何がパワハラになるのか」「どこまでが指導でどこからがアウトなのか」といった現場の疑問を明確に解消します。
「“給料泥棒”と言ったら?」「皆の前で叱責したら?」「有給休暇の理由を聞いたら?」といった事例をもとに、6類型に分けて具体的なハラスメント行為を整理。また、相談を受けた際の聞き取りの進め方、NGワード、適切な初期対応のポイントについても重点的に解説します。
加害者にも被害者にもなりうる立場だからこそ、正しい知識と実務対応力が不可欠です。職場の信頼関係を守り、安心して働ける組織づくりを支える管理職になるための実践的な研修です。 ×
管理職がハラスメントの相談を受けたとき
現場での初期対応が、その後のリスクを大きく左右します。本講演では、管理職がハラスメントの相談を受けた際の適切な対応方法や、記録の取り方、組織内での報告・共有フローを解説。相談者・被相談者双方への配慮を忘れずに対応するための実務に役立つ内容です。 ×
新入社員が知っておくべき法律・契約書の基礎
社会人としてキャリアをスタートさせるにあたり、ビジネスの現場で必ず関わるのが「契約」です。法務部だけでなく、営業・開発・調達などあらゆる部門で契約書を“理解し、扱える”スキルが求められます。
この研修では、契約書の基本構造から重要な条項の意味まで、実際の契約書を使いながら実践的に学びます。 ×
書籍・メディア出演
メディア
- 日本経済新聞
- 毎日新聞
- TIME誌
近著・論文
- 日本公認会計士協会「会計・監査ジャーナル」連載「公認不正検査士の不正調査手法」第一法規 2025-現在
- ガバナンスQ連載「経営者のためのハラスメント・アップデート講座」2024-現在
- 『会社法 質疑応答集』第一法規(2024年改訂時)
- 税理士.ch 「AI利用の法的リスク」ビズアップ総研(2024)
- WEB労務行政 連載「人事労務に関わるコンプライアンス講座(全6回)」(2024)
- 「定年再雇用でトラブらないために知っておきたい法律知識Q&A」月刊経理WOMAN(2023)研修出版
- 「総務が押さえておくべき2023年に施行の法令改正情報」(2023)月刊総務
- 「『会社法』のことが理解できる30分セミナー」月刊経理WOMAN(2022)研修出版
- 「中小企業が押さえておきたい『個人情報保護法』の改正ポイント」月刊経理WOMAN(2022)研修出版
- 「知っておきたい『フリーランスガイドライン』の内容と会社の注意点」(2022)研修出版
- 『会社法 質疑応答集』第一法規(2022年改訂時)
- 「『株主総会』の法律知識」月刊経理WOMAN(2020)研修出版
- 「総務部門が押さえておくべき2020年に施行の法令改正情報」(2020)月刊総務
- 「取締役が『法的責任』を問われる4つのケース」月刊経理WOMAN(2020)研修出版
- 『税理士業務のための民法改正ハンドブック 相続法編』第一法規(2019)
- 『事業承継の法律相談』青林書院(2018)
- 『税理士業務のための民法改正ハンドブック 債権法編』第一法規(2018)
- 『税理士・会計士のための顧問先アドバイスノート・企業法務編(新版)』清文社(2010)
- 『実践企業組織改革③増資・減資・自己株式・新株予約権(改訂版)』税務経理教会(2012)
- 『実践企業組織改革②株式交換株式移転・事業譲渡(三訂版)』税務経理教会(2011)
講演実績
社内研修
- 財閥系企業を含む上場企業、非上場企業、地方自治体
- 業界は金融機関、メーカー、IT、運送、建設、アパレル、化粧品、小売等多数
- 頻度は年に30回程度
オンライン
- みずほリサーチ&テクノロジーズ「コンプライアンス入門」
- ビズアップ総研「下請法の基本と実務上の留意点」
- Udemy「パワーハラスメントの基礎」
この講師のおすすめポイント
野村彩さんは、企業法務の最前線で活躍する弁護士であり、公認不正検査士(CFE)の資格も持つコンプライアンスとガバナンス分野のスペシャリストです。企業の不祥事対応や内部通報制度の設計・運用、役員の法的責任、ハラスメント対策など、企業活動における重大リスクへの対応に数多く携わってきました。
上場企業の社外役員や監査役としての実績も豊富で、理論と実務の両面から信頼性の高い知見を提供しています。講演では、役員や管理職が現場で直面するリスクを具体的事例でわかりやすく解説し、即実践に役立つアドバイスを届けています。
◆ 実務に即したコンプライアンスの専門家
野村さんは、実際の企業で起きた不祥事や通報対応事例に精通しており、講演では「現場で何をすべきか」が明確になる具体的な知識を提供します。法的な枠組みだけでなく、組織としての実践的な対応力の強化を重視しており、聞き手にとって「明日から使えるノウハウ」が満載です。
◆ 企業役員・管理職向けテーマに特化
「新任役員が知っておくべきコンプライアンス」「役員責任とは」「株主総会の注意点」など、企業の経営層・管理職が押さえるべきテーマにフォーカスした講演が多く、役員研修や管理職向けセミナーに最適です。専門性が高く、かつ平易な言葉で説明してくれる点も高く評価されています。
◆ コーポレートガバナンスの第一人者
コーポレートガバナンス・コードや役員報酬設計、社外取締役の役割など、ガバナンスに関するトピックでも信頼されており、上場企業の取締役や監査役の登壇者としても多数の実績があります。社外役員経験を活かした実践的な解説が特徴です。
◆ ハラスメントや働き方改革など社会的テーマにも対応
ハラスメント研修や労務管理研修では、最新の法改正や社会の動向を反映しながら、現場で起きがちな事例に即した対応を提案。「何がパワハラになるのか」「どう対応すればよいのか」といった現場の悩みを丁寧に解きほぐします。
◆ 安心感のある語り口と圧倒的な説得力
弁護士としての知見に加え、社外役員・第三者委員・ガバナンス研究会など多方面での活動実績に裏打ちされた話は、説得力と信頼感にあふれています。法務部門はもちろん、経営陣・総務・人事まで幅広い層に支持されています。
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。