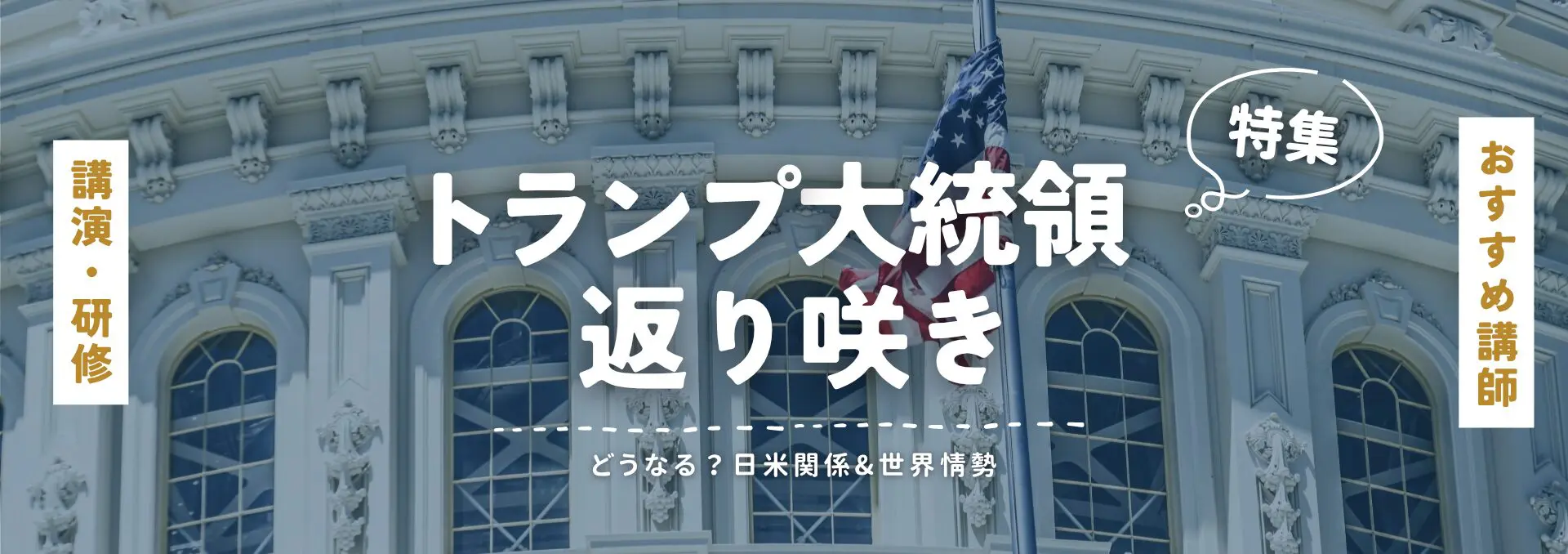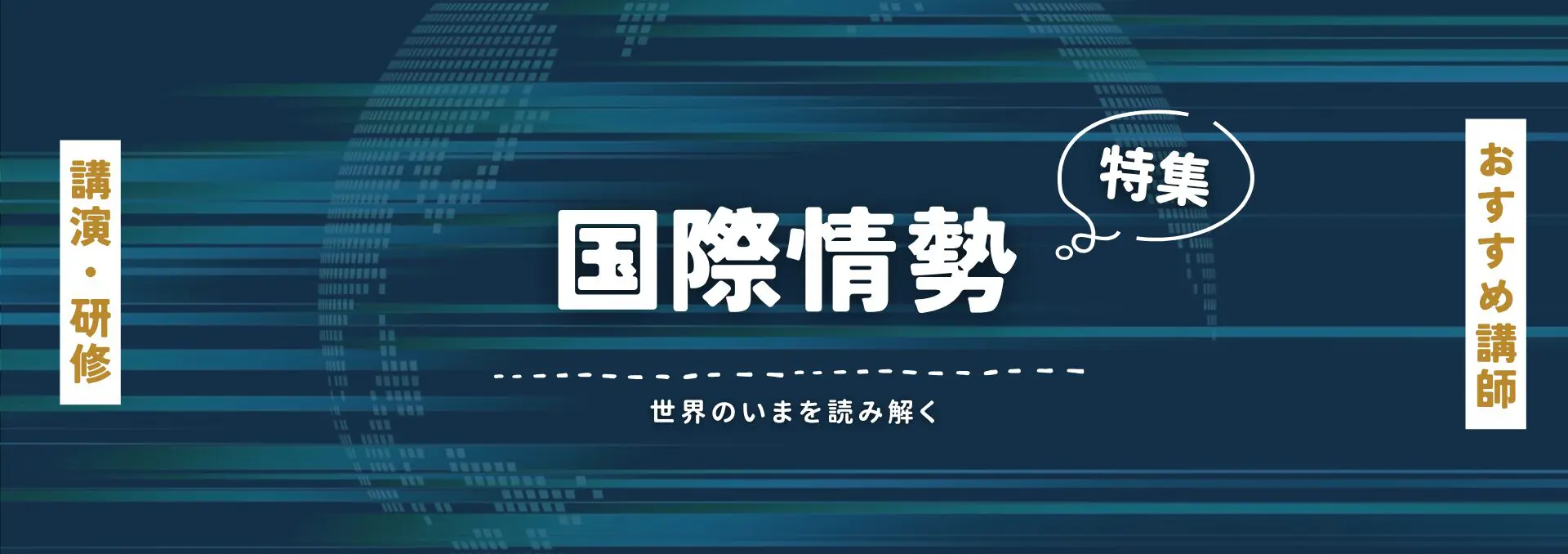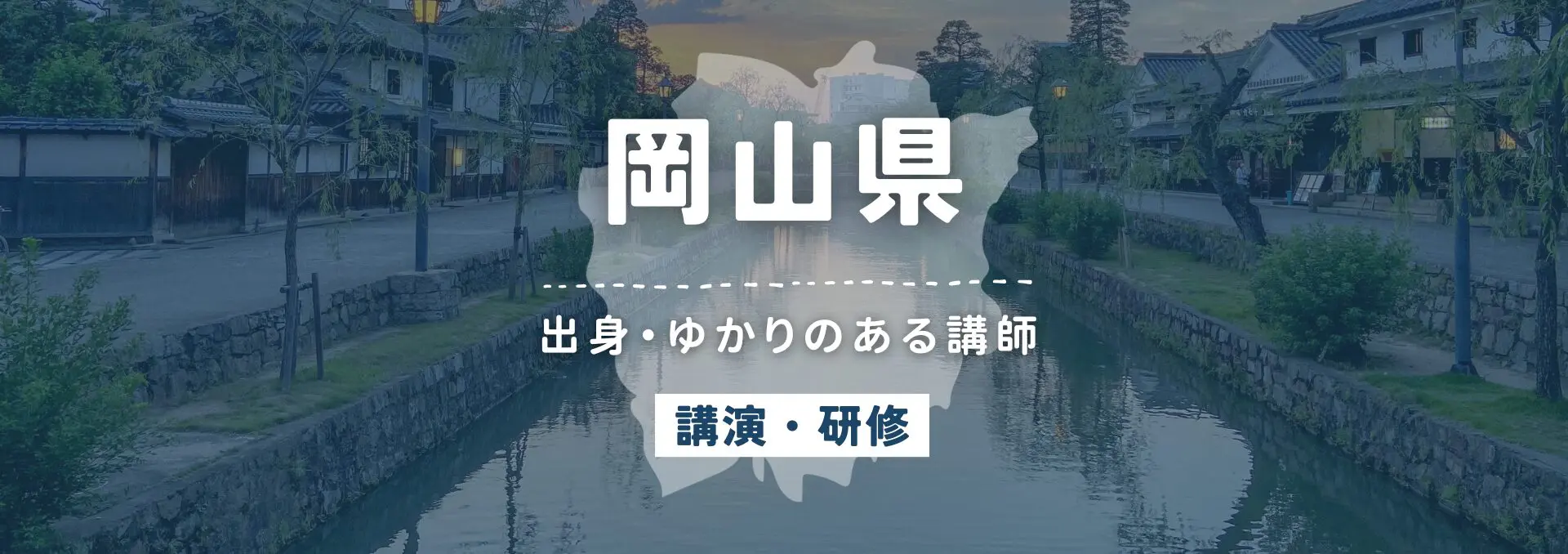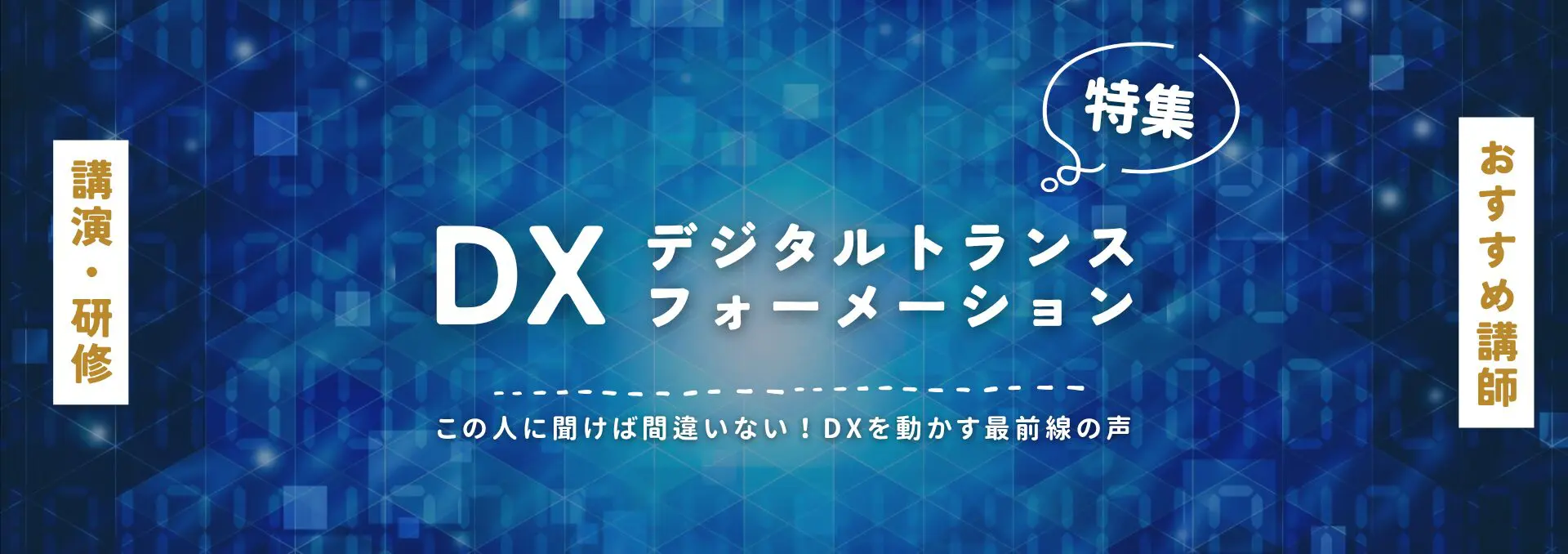室山哲也 むろやまてつや

日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ)会長/元NHK解説主幹
プロフィール
1976年にNHKに入局し、「ウルトラアイ」などの科学番組ディレクターとして活躍。その後、「クローズアップ現代」「NHKスペシャル」のチーフプロデューサーや解説主幹を務め、2018年に定年退職。科学技術、生命・脳科学、環境、宇宙工学などの分野で論説活動を行い、教育テレビの子供向け科学番組「科学大好き土よう塾」の塾長としても科学教育に貢献。国際的な映像祭での受賞歴多数あり、日本科学技術ジャーナリスト会議の会長を務め、政府の委員も多数務める。
テーマ
出身・ゆかりの地
経歴
1976年、早稲田大学法学部を卒業後、NHKに入局。最初のポジションは宮崎放送局のディレクターだった。その後、1981年にはNHK教養科学部のディレクターとして、『ウルトラアイ』などの番組を担当。1987年にはNHK広島放送局のディレクターとして、『NHKスペシャル』などの制作に携わった。
1990年にはNHK科学番組部のプロデューサーに就任し、『NHKスペシャル 人体「脳と心」』、『クローズアップ現代』、『NHKスペシャル』など多くの番組を手がけた。その後、1997年にはNHKエンタープライズのエグゼクティブプロデューサーとして、ロボコンや博物館プロデュースなどに携わった。
2000年にはNHKBSの統括プロデューサーとして、40帯番組の制作を担当し、2002年にはNHK解説委員(科学担当)、2005年にはNHK解説主幹(科学担当)として、科学番組の解説と制作に深く関わった。
2013年には日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ)の副会長に就任し、同時に大正大学と東京都市大学で特別教授として教鞭を執った。2018年にNHKを定年退職後、2020年にはJASTJの会長に就任し、科学技術のジャーナリズムに対するリーダーシップを発揮している。
主な講演テーマ
22世紀型人類になろう!
~テクノロジーで創る地球の未来~
新興感染症、気候変動、エネルギー問題、食糧問題、戦争──。
地球はいま、「持続可能な成長」(SDGs)を実現するための過渡期にあります。
人類はすでに地球1.7個分の資源を消費して暮らしており、もし全員がアメリカ並みの生活水準を目指せば、地球が5個必要だともいわれています。
これから私たちは、「地球1個分の文明」を築くことが求められます。
AIをはじめとする優れたテクノロジーを活用して、それをどう実現していくか。
また、日本の「もったいない精神」という文化を、どう融合させるか。
「虫の目」(現場)、「鳥の目」(全体)、「魚の目」(流れ)という3つの視点を駆使し、未来をつくる若者たちとともに、その方法を探っていきたいと考えています。 ×
元NHKプロデューサーが語る:コミュニケーションの極意
放送局はコミュニケーションのスキルを磨くことができる場です。番組制作の過程で必要な「企画」「対話」「まとめ」「編集」「伝達」など、コミュニケーションの本質が凝縮されています。私はNHKでのプロデューサーと解説委員の経験を通じて得た40年の知識を活かし、最新の脳科学や著名人の言葉を交えて、分かりやすくお伝えします。 ×
活発化する宇宙開発競争
宇宙開発競争が活発化しています。通信衛星、気象衛星、測位衛星は、私たちの社会
に欠かせないものとなっており、ますます精度をあげています。また、アメリカを中
心にしたアルテミス計画(月面開拓)や、中国の宇宙ステーション建設など、宇宙開
発は月や火星をめぐる戦いになりつつあります。今や宇宙開発は、湖上の経済や安全
保障に大きく影響を与える、未来社会の縮図ともいえます。「宇宙開発」はどこまで
来ているのか?今後どうなっていくのか?日本はどのようにふるまうべきなのか?最
新情報も織り交ぜ、宇宙開発の現状と課題をお話しします。 ×
どうつくる?持続可能な社会
~新型コロナとSDGs~
SDGs(持続可能な開発目標)が世界的に注目されています。新型コロナウイルス、気候変動、エネルギー、食料問題、戦争など、これらの課題に対処しながら、「持続可能な成長」への重要な局面に入っています。急激な人口増加と無計画な開発により、地球資源の消費が増え、地球1.7個分の生活が既に行われています。持続可能な未来を築くために、地球1個分で豊かで質の高い生活を実現する方法について、科学的データを交えてわかりやすく解説します。 ×
どうつくる?持続可能な社会
~SDGs実現への処方箋~
SDGs(持続可能な開発目標)が世界的に注目されています。新興感染症、気候変動、エネルギー問題、食糧問題、そして戦争の悲劇など、これらの課題に直面しつつ、人類社会は「持続可能な成長」を実現するための重要な段階に入っています。急激な人口増加と無計画な開発により、人類はすでに地球資源を1.7個分消費しています。地球1個分で豊かで質の高い、持続可能な生活を実現するために、私たちがどう行動すべきか、最新の科学的データも交えてわかりやすくお話しします。 ×
分断の時代を乗り越えるSDGsの処方箋
米中対立やウクライナ戦争が世界を「分断の時代」に後退させました。
国際的な協力が後退する中、今後は気候変動問題と安全保障の観点からもSDGs(持続可能な開発目標)を達成する必要があります。
人類はすでに地球資源を1.7個分消費しており、持続可能な生活を実現するためには、地球1個分の生活を目指す必要があります。再生可能エネルギーの潜在力について最新の科学データを交えながら、「分断の時代」のSDGs達成の方法について、わかりやすくお話しします。 ×
カーボンニュートラルへの処方箋
気候変動に対応するため、カーボンニュートラルへの道は避けられません。ウクライナ戦争により状況が複雑化する中、脱炭素化の重要性が一層高まっています。今後のエネルギー政策は、環境保護と経済発展を両立させる必要があり、その核心には再生可能エネルギーがあります。最先端の科学技術と再生可能エネルギーを組み合わせ、効率的なエネルギーシステムを構築し、成長戦略にも繋げ、健全な循環型社会を実現していくことが求められます。私たちはどうすればエネルギー課題に取り組み、カーボンニュートラル社会を実現できるのか。最新の情報を交えながら、わかりやすくお伝えします。 ×
生成AIの衝撃!人工知能時代をどう生きるか
AIの急速な進化は、Chat GPT(チャットGPT)を含め、社会に大きな影響を与えています。AIによって生活は便利になる一方で、既存の雇用を脅かす側面もあります。AIの進化の行方や、私たちがどう向き合っていけばいいのか、AI研究の最前線や人間の脳との違いを考慮しながら、人工知能時代の生き方について、わかりやすく解説します。 ×
生成AIの衝撃!人工知能時代の税理士像とは?
税理士業務もAIの影響を受け、広範な業務に変化が訪れています。将来、AIなどのテクノロジー進化により、業務の5割が自動化されると予測されています。AIの進化の行方や、税理士が今後どう対応すべきか、最新のAI研究の動向を踏まえつつ、人間とAIの違いを考察し、人工知能時代の生き方についても探ります。 ×
人生100年!シニアが輝く人工知能社会とは?
保守的で頭が固く、時代の流れについていけないとされる高齢者像が、デジタル技術の進化によって根本的に変わり始めています。例えば、最近注目されているChat GPT(チャットGPT)などの生成AIは、むしろ人生経験と語彙力が豊富な高齢者に適していることが分かってきました。また、脳や体の機能を支えるデジタルサイボーグ技術により、社会的に活躍する高齢者の可能性も広がっています。今や、最先端のデジタル技術は、高齢者の生活を豊かにする革新的な技術とも言えるのです。デジタル時代におけるシニアの生き方と、社会の在り方について、具体例を交えて考察してみましょう。 ×
クルマの未来と社会の行方
テスラ(米国)やBYD(中国)のEVが世界を席巻する中、日本の自動車産業には大きな衝撃が走っています。この背景には、「カーボンニュートラル」や「AIによる自動運転」という大きな動向があり、これに対応することが産業の存亡に直結すると言われています。さらに、CASE(ネット化、自動化、シェア、電動化)の概念が示す通り、クルマは社会変革の重要な鍵を握っています。
今後、クルマはどのように進化していくのか?そして、私たちの社会はどのような姿に変わっていくのでしょうか?最新の情報を交えながら、わかりやすく解説します。 ×
脳を知って、よい子を育てよう
――五感と成長の不思議な関係から見た子育ての未来
AI時代を迎え、人間に固有の能力をどう発展させるかが、教育の重要なテーマです。人間の脳は五感を通じて世界を感じ取り、情報を整理し、独自の精神世界を形成しています。直観力や情操力、問題提起力など、AIにはない優れた能力がありますが、これらをどう伸ばしていくかが鍵となります。私が制作したNHKスペシャル「人体 脳と心」の情報を基に、最先端の科学的知見を交えながら、人間の脳の特性と「脳力全開」の育成方法についてお伝えします。 ×
DXで創るポストコロナ社会
現在、世界は気候変動、環境汚染、新興感染症、エネルギー問題などの人類規模の危機に直面しています。国際社会はこれらの課題に対処するためにSDGs(持続可能な開発目標)を掲げ、持続可能な社会を目指しています。しかしながら、これらの課題は非常に複雑であり、今後はDX(デジタルトランスフォーメーション)の力を借りて、変革していくことが不可欠です。ポストコロナ(ウイズコロナ)社会のあり方と、どのようにして変革を推進していくべきか、そして最新のテクノロジーの状況を踏まえ、DXの可能性と今後の課題についてご説明します。 ×
DX時代到来!人工知能にどう向き合うか
人工知能はDX推進の中核技術として位置付けられています。産業、医療、交通など、社会全体に革新をもたらす可能性がありますが、同時に雇用の削減など負の側面も議論されています。人工知能が社会をどのように変革するのか、また私たちはこれにどう向き合うべきなのか、さらに教育がどのように進化すべきかなどについて、最新の科学情報をもとにお話しします。 ×
進む交通のDX!自動運転の光と影
自動運転技術は急速に進化しており、そのレベルは現在、1から5まで分類されています。最近ではレベル3の自動運転車も市場に登場し、条件付きではありますが無人運転が可能なものも出てきました。自動運転はCASE(情報の融合、自動化、シェア経済、電動化)と共に、社会に革新をもたらす重要な技術です。しかし、同時に「事故責任の所在」など法的課題に対する取り組みの遅れなど、さまざまな課題も山積しています。自動車の進化が社会にもたらす影響や最新情報、現在の課題、そして未来社会の可能性について、政府の自動運転審議会委員である室山氏の視点からお話しします。 ×
新しい隣人?ロボットは社会を変えるか?
人類は、道具の創造を通じてテクノロジー文明を築き上げてきました。その最先端を行く存在がロボットです。現在では、ヒューマノイドやアンドロイドなど、「人間に酷似した」ロボットが登場し、AIと統合されることで、ますます人間に近い能力を持つようになりました。これらは「少子高齢化社会の救世主」と期待される一方で、誤作動やテロによる危機管理の問題や、雇用奪取の懸念が議論されています。今後、私たちはロボットとどのように向き合っていけばよいのでしょうか?最新情報を交えながら、わかりやすく解説します。 ×
気候危機と脱炭素社会の行方
地球温暖化による気候変動はますます深刻化し、世界全体を大きく影響させています。環境災害が世界の経済活動や国際政治にも暗い影を投げかけています。私たちはこの課題にどう向き合い、脱炭素社会を実現していけばよいのでしょうか?最新の科学的知見も交え、わかりやすく解説します。 ×
みんな違ってみんなイイ!
現代において「ダイバーシティ(多様性)」がこれほど重要な時代はありません。新しい文明が異なる文化が交わる場で生まれるとトインビーは述べていますが、異文化と対話し、新たな価値を生み出せる子どもや青少年の育成が不可欠です。SDGsでもその重要性が強調されています。私自身が自閉症の娘を育てる中で得た経験も踏まえながら、多様性を尊重した社会の構築とその重要性、最新の脳科学や進化生物学の研究成果に基づいてお話しします。 ×
DX時代の教育論!ロボコンに見る教育の極意
ロボコン(ロボットコンテスト)は、日本だけでなく世界中の関係者から「創造性教育の模範」と高く評価されています。これは、生成AIが社会に浸透する中で、人間特有の「直感」「創造性」「感動」「主体性」といった脳の力を育むからです。私はNHKロボコンのプロデューサーとしての経験をもとに、最新の脳科学の知見を交えつつ、ロボコンが示す未来の教育の在り方についてお話しします。 ×
脳が幸せになる教育──ロボコンという魔法
~正解がない自由な精神のチカラ~
この講演では、ロボットコンテスト「ロボコン」を通じて、創造性、主体性、感動といった“人間らしさ”が育まれる教育の本質について語られます。特に、AI時代において求められる「正解がない世界で生きる力」の重要性が強調され、ロボコンがどのようにして子どもたちに「自分で考え、作り、試行錯誤する力」を育む場であるかを紹介します。また、ロボコンが単なる技術的な競技ではなく、教育と人間性を深く考えさせる場であることに焦点を当て、AIやロボットに代替されにくい「創造性」と「人間性」の価値を再確認します。 ×
脳から見た「安全安心社会」とは?
~ヒトと技術の向き合い方~
人間は、脳を使って科学技術を生み出し、豊かな文明を築いてきました。しかし一方で、気候変動、災害、環境汚染など、深刻な危機も生み出してしまいました。私たちは「脳」を使って、今後、どう対処していけばいいのでしょうか?
キーワードは「AI」です。
脳には創造力という長所とともに「錯覚や思い込み」という弱点があり、AIには情報処理能力という長所とともに「決断力や責任感」がありません。しかし、両者が弱点を補完しながら進めていけば、最強チームになることが出来ます。
講演では、脳と生成AIとの連動の仕方についてお話しし、自動運転の例なども織り交ぜながら、安全・安心社会を創るヒントを探っていきたいと思います。 ×
脳と心の不思議な世界
~私たちは脳で世界をどう創っているのか~
AI時代に突入した現在、重要な問いの一つが「人間とは何か」ということです。人間は「生物」であり、一方でAIは「非生物」です。人間としての私たちが脳の仕組みを理解し、その力を活かすことで、AIと共存し、協力関係を築いていくことが可能です。人間の脳は、五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)や創造力、直感力、無意識のメカニズムなどで構成されています。これらの「脳と心の不思議な世界」について、最新の科学的成果や実例を交えてお話ししていきます。 ×
ロボットと人間の不思議な関係
人間は、道具を作ることでテクノロジー文明を築き上げてきました。ロボットはその最先端の創造物であり、現在ではヒューマノイドやアンドロイドなど「人間に酷似した」ロボットが私たちの生活の中に現れつつあります。しかし、誤作動やテロによる危機管理の問題、そして雇用の喪失など、多くの課題も指摘されています。このような状況の中で、私たちは今後、どのようにロボットと向き合っていけば良いのでしょうか?さらに、人体とロボットが融合する「サイボーグ技術」などの最新情報を交えながら、現状と課題についてわかりやすくお話しします。 ×
生命誕生の8つの偶然
地球に生命が誕生するまでには、数々の偶然が重なり、奇跡のようなプロセスが進んできました。太陽系の形成、月の形成、そして地球上で起きた海の誕生や巨大隕石の衝突など、これらの出来事が生命を脅かす一方で、私たち人類の祖先はどのようにしてこれらを乗り越え、進化してきたのでしょうか?宇宙の視点から生命の誕生と進化を考察します。 ×
こうしてヒトが生まれた
人類は、宇宙の進化、太陽系の進化、地球の進化、そして生命の進化の過程を経て誕生しました。この意味で、現在存在する数百万種の生物は、遺伝子の起源が同じ兄弟であり、人類もその一種に過ぎません。文明の課題は、すべてこの進化の構図の中で生じています。私たちの祖先は、地球がドラマチックな変動を経験する中で、どのようにして危機を乗り越え、人間として成長してきたのでしょうか? ×
進化が生んだ病
この講演は、「病気とは何か」「生きるとは何か」「死とは何か」という本質的な問いに迫り、私たちの身体と社会について深く考察する内容です。医学的観点からだけでなく、進化論的な視点を取り入れ、病気と人間の関係を新たに解き明かします。
第1章では、病気が単なる「異常」ではなく、生きることの裏側にある「必然」であるという視点から、健康と病気の本質に迫ります。シェークスピアや哲学者の言葉を引用し、病気と死がどれほど人間の一部であるかを考察します。
第2章では、感染症が歴史をどのように変えてきたか、ペストやスペイン風邪、そして新型コロナウイルスなどの例を通して、病気が文明や社会、経済、価値観をどう変動させてきたのかを説明。感染症が単なる医学的な出来事ではなく、社会全体に影響を与えるものであることを示します。
第3章では、感染症がなぜ繰り返されるのかについて、地球規模での問題としての視点から議論し、気候変動や人口増加がどのように新興感染症を引き起こす原因となるかを説明します。
第4章および第5章では、進化医学(ダーウィン医学)の観点から、病気がどのように進化の過程で生まれたかを解説。肥満やうつ病、心臓病、がんなど、進化がもたらした病気が現代社会においてどのようにリスクとして現れているかを考察します。
第6章では、病気とどう向き合うかという視点を提示し、「完全な健康」の幻想を打破し、「病気を抱えながら生きる」社会設計の必要性を訴えます。また、治療だけでなく、心のケアや生活の質(QOL)を重視した医療が求められる時代であることを指摘します。
最後に第7章では、病気や死が生きることに内在するリスクであり、そのリスクを受け入れる勇気が重要であると説きます。病気や死を恐れるのではなく、どんなリスクにも挑戦し、成長することが人間の本質であることを再確認します。
この講演を通じて、私たちは「健康とは何か」「病気とどう生きるか」という問いに対する深い洞察を得ることができ、病気と共に生きる叡智を身につけることができます。現代社会における病気の捉え方や医療の未来、そして人間の在り方を考えるための貴重な機会となるでしょう。 ×
宇宙開発競争
人類が築いた文明は今や宇宙にまで及んでいます。人工衛星は、放送や通信、天気予報など、私たちの日常生活に不可欠な役割を果たしています。しかし、その裏にはロケットの打ち上げ競争や宇宙ビジネスなど、激しい競争があり、また軍事的な課題も浮上しています。「宇宙開発」はどのような進展を見せているのでしょうか?宇宙開発の光と影について考察します。 ×
サイボーグ人間の誕生
進化するコンピューターに対抗して、人間の神経系(脳や末端神経)とコンピューターを接続するブレーンマシンインターフェイス(BMI)という新技術が注目されています。この技術は福祉や医療を推進する一方で、人間の超人化やロボット化の可能性を生み出し、ある種の人権問題につながる懸念もあります。人類は今後、どのように進化していくのか?その現状と課題について掘り下げていきます。 ×
巨大地震と日本
日本は世界でも有数の地震国です。その歴史は、巨大地震や津波との闘いの歴史とも言えます。特に都市化が進む中、災害の複雑化と深刻化が課題となっています。私たちは巨大災害にどう立ち向かうべきなのでしょうか?東日本大震災などの事例を挙げながら、地球環境が引き起こすリスクと、科学技術の役割を考えてみましょう。 ×
生物多様性の危機
人間の活動は、急速な生物の絶滅を引き起こしています。その規模と速度は地球史上、特に深刻なものです。これは人類の存続にも直接関わる問題です。生態系や生物多様性の重要性、そしてそのメカニズムについて深く考えてみましょう。 ×
テレビディレクター40年:私が出会った偉人達
NHKのディレクターやプロデューサー、解説委員として40年間のテレビ業界で多くの著名人に出会い、彼らの世界観や人生の教訓を取材し、その現場を目撃してきました。ノーベル賞受賞者、探検家、政治家、ビジネスリーダー、宗教家、教育者など、日本や世界で影響を与えてきた偉人たちの名言や人生哲学を紹介しながら、私たちが今後どう生きていくべきかについての指針をお伝えします。 ×
脱炭素社会をどうつくるか
――地球温暖化とエネルギー戦略の最前線
この講演では、気候変動とその影響に関する深刻な現状を問い直し、私たちが直面する地球規模の課題にどう立ち向かうべきかを論じます。地球温暖化が引き起こす異常気象、山火事、豪雨、干ばつなどの現象は、いまや人類の未来に対する「時限爆弾」となっています。講演では、気候変動が人類の文明を崩壊に導く可能性を示すオックスフォード大学の研究結果に触れ、温暖化を止めるための挑戦と、その背後にある「地球益」と「国益」のジレンマを探ります。
さらに、人口増加と「地球1個分」では足りない生活水準の問題が環境への圧力を増大させる中、再生可能エネルギーと自然エネルギーの可能性に焦点を当てます。太陽光、洋上風力、次世代のペロブスカイト太陽電池などが持つ大きな潜在能力を紹介し、エネルギーを効率的に運び、貯めるための技術的な課題にも言及します。また、脱炭素社会の実現には、都市と里山の協働による分散型社会の実現が鍵となることを説明し、自然と共生する価値観の重要性を再評価します。
講演の中では、2023年のCOP28や日本のエネルギー戦略に基づく国際的な取り組みを紹介し、再生可能エネルギーの導入拡大やCO₂排出削減目標についても詳述します。また、グリーン成長戦略に基づく経済成長の可能性について触れ、環境と経済の両立を目指す未来のビジョンを提案します。
最後に、地球型市民として新しい文明を築く必要性を強調し、気候危機を転換点として捉え、私たち一人ひとりが地球を守るためにできる行動を今すぐに始めるべきだというメッセージを伝えます。この講演は、気候危機に立ち向かうための知識と行動のヒントを提供し、持続可能な未来を築くための道筋を示します。 ×
生命誕生の奇跡と私たちの未来
――「8つの偶然」から考える人間とは何か
本講演では、私たちがどこから来て、何者で、どこへ向かうのかという根本的な問いに答えようとする壮大な旅に誘います。科学を通じて生命の起源と進化を解き明かし、私たちが存在する奇跡的な背景を詳述し、地球と宇宙の調和について探求します。
まず、生命の誕生を探るためには宇宙の始まりから紐解く必要があり、ビッグバンから始まり、太陽系の形成、地球の誕生、そして生命の起源に至るまでの過程を詳細に説明します。私たちが「星のかけら」であること、つまり、私たちの体を構成する原子が星の爆発によって生まれたことを考えると、私たちの存在がどれほど特別であるかを実感できるでしょう。
さらに、生命の誕生に至るまでの「8つの偶然」の奇跡的な連鎖を紹介します。例えば、地球に液体の水があったこと、月が地球の気候を安定させたこと、そして木星が小惑星衝突を防いだことなど、これらの偶然が重なった結果、私たちのような生命が誕生したことに驚かされます。
科学的視点だけでなく、文化的・宗教的な多様性を考慮しながら、生命の定義や進化の過程についても触れます。自己意識を持ち、未来を想像し、宇宙を探索する能力を持つ私たちは、進化の中でも極めて稀な存在です。この特別な星でどのように生きるべきかを考えさせられる内容となっています。
現代の課題—気候変動やパンデミック、人工知能の進化など—に直面しながらも、私たちには未来を創り出す力があることが強調されます。科学と文化を活かし、次の世代へ命のバトンを渡すために何をすべきかを問いかけ、地球型市民としての新しい生き方が提案されます。
本講演は、私たちの存在と進化、そして未来に対する深い理解を促し、「地球型市民」として新しい文明を築くための指針を示す内容です。 ×
人生100年時代に輝くために
〜シニアとAIが共創する未来〜
この講演は、人生100年時代を迎えた現代社会におけるシニア世代の新たな可能性と、AI技術の進化がもたらす未来をテーマにしています。現代のシニアは、過去の「高齢者」のイメージを覆し、人生の後半を充実したものにするためにAIをどのように活用できるのかを探ります。
特に注目すべきは、「老い」は必ずしも弱さではなく、むしろ「老人力」という武器に変わる可能性があるという視点です。高齢者が持つ経験や知恵を、AIを駆使することでさらに活かし、社会に貢献できる方法が提案されます。生成AI(Generative AI)の普及により、シニアは知識や創造性を活用して、自分の経験をアウトプットし、日常生活の課題を解決するパートナーとしてAIを取り入れることができます。
また、この講演では、AI時代におけるシニア世代の強みについても深く掘り下げます。人間ならではの創造性や感情、対人力はAIには代替できない特質であり、シニアがこれらを活かして新しい社会を切り開く重要性が語られます。AIの登場により、仕事の自動化や職業の変化が進んでいる中、シニア世代こそが新たな未来を作り出す鍵を握っていると力強く訴えます。
日本は少子高齢化という課題を抱えていますが、それを解決するために先進的なテクノロジーを活用し、「誰もが幸せに老いることができる社会」を実現する可能性があります。この講演は、シニアがAIと共に生き、自己の可能性を最大限に活かす方法を提示し、未来に向けて希望と勇気を持ち続けることの重要性を訴えます。
シニア世代にとって、AIは単なる道具ではなく、社会参加や学び直し、趣味の深掘り、健康維持に至るまで、さまざまな面で力強いサポートを提供します。この講演を通じて、「AI時代のシニア」として自信を持ち、未来に向けての第一歩を踏み出す勇気を得ることができるでしょう。 ×
科学ジャーナリズムの未来
この講演は、現代社会における科学とジャーナリズムの役割を深く掘り下げ、人類の未来を形作るための視点と行動を考察します。オックスフォード大学を中心に発表された「人類滅亡12のシナリオ」を基に、気候変動、核戦争、パンデミック、AIの暴走などの脅威に対して、私たちがどのように立ち向かうべきかを問い直します。
講演の初めでは、現代における「文明の選択肢」としての視点を提示し、地球規模での課題に取り組むためには個々人の認識変化と「地球型市民」への変革が必要であることを強調します。科学ジャーナリズムが果たすべき責任に触れ、正確でわかりやすい情報伝達を通じて、科学と市民社会、マスメディアの橋渡しをする重要性を説明します。
また、過去30年間の科学と社会の交差点を振り返り、地球サミットや阪神淡路大震災、東日本大震災、新型コロナウイルスなどの出来事を通して、科学ジャーナリズムがどのように社会に影響を与えてきたかを分析します。そして、良質な科学ジャーナリズムの条件として、エビデンスの確認や複眼的思考、情報伝達力などが挙げられ、記者が社会的意義を読み解き、地球規模の視野で解説することが求められることを明確にします。
さらに、「報道の三つの目」として、事実を伝える目(虫の目)、背景を俯瞰する目(鳥の目)、未来を見通す目(魚の目)の重要性を指摘し、報道がどのように文明の意味を解釈し、社会を導いていくかを考察します。
現在の情報環境では、ネットメディアとAIを活用した新たな科学ジャーナリズムの展開が求められますが、同時にフェイクニュースや誤情報のリスクにも直面しています。講演では、これらのリスクにどう対応するか、また正確性と倫理を維持するための新たな表現技術の必要性を訴えます。
最終的に、科学ジャーナリズムの使命として、知的好奇心を尊重し、社会の活力を維持するためにどのように寄与できるかを探ります。AI時代における人間の進化についても触れ、「情報伝達」から「文明の設計図を共に描く対話」へと進化する重要性を説きます。未来を切り拓くのは「行動する者」であり、地球型市民としての変革が求められる時代において、科学ジャーナリズムは新たな役割を果たさなければならないことを強調します。
この講演は、科学の発展とその社会的影響を理解し、私たち一人ひとりがどのように未来を選び取るべきかを考えさせる、深い洞察に満ちた内容です。 ×
宇宙開発戦争――光と影を見据えて
この講演「宇宙開発戦争――その光と影」では、宇宙開発の現状とその影響について考察します。宇宙開発は科学技術の挑戦であり、人類の未来に大きな可能性を秘めていますが、その背後には軍事的な競争や環境問題といった課題も存在します。
宇宙開発の起源は軍事にあり、ナチス・ドイツのV2ロケットがきっかけとなり、米国とソ連の「宇宙開発競争」へと繋がりました。日本も2008年に宇宙基本法を制定し、宇宙開発は安全保障の一環として進められています。特に、イプシロンロケットは軍事利用と民間利用を兼ね備えた「デュアルユース技術」として注目されています。
一方、宇宙開発は「知のフロンティア」としても重要です。月面基地や火星探査が進み、民間企業も活発に参入しています。アポロ計画から得られた技術が私たちの生活に影響を与えているように、宇宙開発の成果は日常生活にも深く関連しています。
また、宇宙開発の課題として「スペースデブリ」や環境問題もあります。5万9000基以上の人工衛星が宇宙に浮かび、その多くが機能を失い、衝突のリスクを高めています。これにより、持続可能な宇宙開発が問われています。
最後に、宇宙開発には人間の本性—冒険心と好奇心—が根底にあります。しかし、この冒険を支えるためには地球が安定している必要があり、私たちの生き方と宇宙開発の未来は密接に関わっています。「人類は宇宙文明を創れるのか?」という問いを通じて、宇宙開発がもたらす可能性と課題について考える機会となります。 ×
ロボット技術がもたらすもの
~人間らしさを問う未来のパートナー~
この講演「ロボット技術が私たちの社会や人生にもたらす影響」では、AIとロボット技術が進化する現代社会における重要性とその影響について深掘りします。ロボットはもはやSFの世界だけの存在ではなく、私たちの生活に密接に関わる時代に突入しています。講演では、ロボットの定義や進化の歴史から始まり、手塚治虫の「鉄腕アトム」の夢と現実を通して、ロボットの技術的進歩がどのように実現されてきたかを紹介します。
また、ロボット技術は人間の能力の外部化として捉えられ、ロボットは「人間の拡張装置」としての役割を果たしてきました。しかし、その一方で「不気味の谷」や軍事利用による倫理的問題も浮き彫りになります。講演では、ロボットとどのように共存すべきか、どの仕事をロボットに任せ、どの仕事を人間が担うべきかという重要な問いについても触れます。
さらに、ロボット技術の発展が私たちに教えてくれる「人間らしさ」、つまり感動や想像、他者を思いやる心の大切さについても考察します。この講演を通じて、AIやロボット技術が人間社会にどのような影響を与え、私たちがどのように共に生きていくべきかを真剣に考える機会となります。 ×
みんな違って、みんなイイ!
~特別な支援を必要とする子供の理解から考える多様性社会~
この講演「みんな違って、みんなイイ!」では、特別な支援を必要とする子どもたちとその家族が直面する課題と、社会全体での理解と支援の重要性を探ります。講演の中心テーマは「多様性(ダイバーシティ)」であり、それがいかに強い社会を築くための鍵となるかに焦点を当てています。現代社会が抱える多様な価値観、文化、背景を尊重し、どんな人でもその人らしく輝ける社会の実現が求められています。
具体的には、発達障害を「障害」としてではなく「脳の特性」として理解し、異なる脳のあり方や文化が交わることで新しい社会が生まれるという視点が紹介されます。技術やテクノロジーがこの多様性社会を支える手段となり、身体的な障害を持つ人々も社会参加できるようになる未来が描かれています。
また、講演者自身の娘との経験を通じて、発達障害を持つ子どもたちがどのように「違い」を受け入れ、社会と共に成長していけるかを伝えます。発達障害が創造性や集中力といった特性に結びつくこと、そしてそれがAI時代における人間の価値にどのように貢献するのかという視点も紹介され、未来を見据えた多様性社会の形成が重要であることが強調されます。
この講演を通じて、障害を持つ子どもたちを含むすべての人が自分らしく、平等に、社会で幸せに生きられる社会のあり方について深く考えることができます。 ×
書籍・メディア出演
- 『驚異の小宇宙人体~脳と心(5)』
- 『科学ジャーナリストは警告する』
- 『ウルトラアイ』1~4巻
メディア
- NHK総合「時論公論」「くらし解説」「ここに注目」「クローズアップ現代」
- NHKEテレ「科学大好き土曜塾」5年間キャスター
- 解説委員時代はNHKに100回以上出演、退職後は民放に数回出演
講演実績
講演
- 自治体(大阪市、川崎市、三鷹市、静岡市など)
- NTT東日本
- 住友グループ総会
- 早稲田大学
- JAXAなど
シンポジウム
- どう実現?自動運転社会(国土交通省、内閣府など)
- 宇宙開発と未来(JAXA/NASAなど)
- 温暖化にどう向き合うか?(環境省、東京都、英国大使館)
- 基礎科学が切り開くイノベーション日本(JST)
- 北極圏で何が起きているか(国立極地研)
- どう向き合う?新興感染症(環境省)
この講師のおすすめポイント
室山哲也さんは、科学技術を中心とした多岐にわたるテーマで活躍するジャーナリストです。NHKで40年以上にわたり科学番組の制作に携わり、「ウルトラアイ」や「NHKスペシャル」といった数々の人気番組を手掛けました。現在は、日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ)会長として、科学技術ジャーナリズムの発展に尽力する一方、政府委員や大学教授としても活動。人工知能(AI)、SDGs、環境問題など、現代社会が直面する課題をわかりやすく解説する講演で高い評価を得ています。
◆ NHKで培ったわかりやすい解説力
室山さんの講演は、40年以上にわたるテレビディレクター・プロデューサーとしての経験が生きています。難しい科学技術のテーマを誰もが理解できるように噛み砕いて解説するスタイルは、多くの聴衆に親しまれています。
◆ 未来社会を見据えた幅広いテーマ設定
生成AI、カーボンニュートラル、SDGs、宇宙開発といった多岐にわたるトピックで講演を展開。最新技術や環境問題など、未来社会の方向性を考える上で欠かせない情報を提供します。
◆ 実績に裏打ちされた信頼感
NHKの解説主幹として科学解説を担当し、多くの国際的な映像賞を受賞した実績は、室山さんの講演内容の質を保証します。さらに、日本科学技術ジャーナリスト会議の会長としての活動は、彼の見識と信頼性を高めています。
◆ 多様な視点を持つ科学ジャーナリスト
室山さんは、科学技術だけでなく、教育、ダイバーシティ、ライフスタイルなど多分野で講演を行っています。その多様な視点は、聴衆に新たな視野を広げる刺激を与えます。
◆ SDGsと環境問題への深い洞察
持続可能な社会をテーマにした講演では、新型コロナの影響から脱炭素社会の実現まで、具体的な処方箋を示します。特に企業や自治体にとって、SDGs達成のための行動指針を得られる貴重な機会となるでしょう。
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。