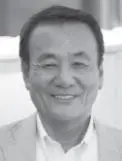池田眞徳 いけだまさのり
経歴
【経歴】
1951年、大阪府生まれ。法政大学法学部法律学科卒業後、1973年に日本電気株式会社(NEC)へ入社。同社ではNEAC汎用コンピュータを用いた資材システム開発に携わり、ソフトウェア開発の基礎を築く。
1983年にテクトコンピュータ株式会社を設立し、野村證券をはじめとする企業の業務システム開発を手がける。特に「FAXによる自動約定報告システム」は、証券業界の業務効率化に大きく貢献。1989年にはプッシュ式電話を活用したゴルフ場自動予約システムを開発し、総武カントリークラブなど多数のゴルフ場に導入。関連特許も2件取得している。
2005年に急病を機に一線を退き、2009年に特定非営利活動法人「原爆先生」を設立。原爆講演活動を本格化するきっかけとなったのは、父・義三氏の残した被爆手記『ありのままに』。この手記をもとに書籍『ヒロシマの九日間』(文芸社)を出版。2008年、宇都宮市役所から講演依頼を受けたことを契機に、都内小学校での「原爆授業」を開始。
以後、「人を集めるのではなく、人の集まりに届ける」という方針で、DMによる学校向けの広報を行い、全国の小・中・高校で「原爆先生の特別授業(90〜100分)」を展開。2024年までに延べ2,100校で講師を務め、リピート率は75%を超える。従来の“語り部”型とは異なり、視聴者の「没入体験」を重視したアクティブラーニングの授業スタイルが高評価を得ている。
2021年、西武園ゆうえんちのアトラクション「ゴジラ・ザ・ライド」に感銘を受け、SFXやCGなど映像表現を講演に取り入れることを決意。映像・イラスト・音響・資料を融合させた新たなコンテンツ制作に着手。コロナ禍による学校のIT化を受け、NHK・BBC・Getty Images・広島平和記念資料館などから提供を受けた映像素材を活用し、リモート配信対応の授業コンテンツを開発。対面講演の補完や再視聴にも対応するハイブリッド型教育支援を展開している。
【略歴】
1951年 大阪府生まれ
1973年 法政大学法学部卒業、日本電気株式会社入社
1983年 テクトコンピュータ株式会社設立、その後複数社の経営に携わる
2008年 都内小学校にて原爆授業を開始
2009年 特定非営利活動法人「原爆先生」設立、理事長に就任
現在 全国の小中高で講演活動を展開、映像・リモート配信も導入中
主な講演テーマ
戦争と原爆の体感学習
アーカイブ映像やVFX映像、独自に制作した映像や画像と講師の語りを組み合わせ、視聴者が戦争や原爆の実相に没入し、非日常の世界を体感できる内容です。
視聴者自身が戦争や原爆について考え、是非を判断する「能動型学習(アクティブラーニング)」の素材を、講演を通じて提供します。
これまでに全国2,000校以上で実施され、75%を超えるリピート率を誇る実績があります。 ×
広島・長崎への修学旅行事前学習
多彩な映像や独自に制作した映像・画像、そして講師の語りを組み合わせることで、視聴者は戦争や原爆という非日常の世界に没入し、体感することができます。
広島・長崎への修学旅行の事前学習として講演を受けることで、旅行への意欲が高まり、実際に訪れる街並みや人々、自然の風景がまったく異なる意味を持って映るようになります。
特に原爆資料館の見学においては、講演が極めて高い予習効果を発揮し、何倍もの深い体験へとつながります。
ある引率教員からは、「以前は資料館見学の時間よりも早く全員が退館していたが、講演を受けた後の旅行では、退館時間を過ぎても多くの生徒が退館しようとしなかった」との感想も寄せられています。 ×
原爆先生の平和学習
アーカイブ映像やVFX映像、独自に制作した映像・画像と講師の語りを組み合わせることで、視聴者は戦争や原爆の世界に没入し、非日常の体験を味わいます。
「戦争はダメ」「平和が大切」といった受け身の学びではなく、参加者自身が戦争や原爆について考え、自ら是非を判断する——そんな能動的な学び(アクティブラーニング)の素材を提供します。
これまでに全国2,000校以上で実施され、75%を超えるリピート率を誇る特別授業(講演)です。 ×
書籍・メディア出演
書籍紹介
クリックすると、詳細が表示されます。
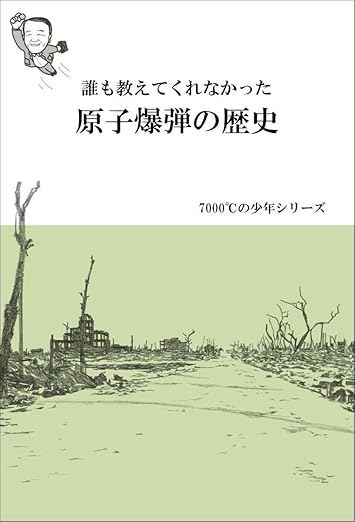
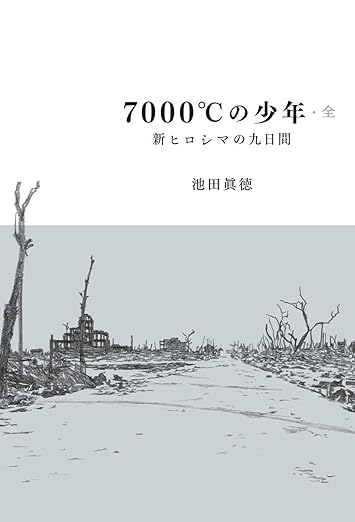
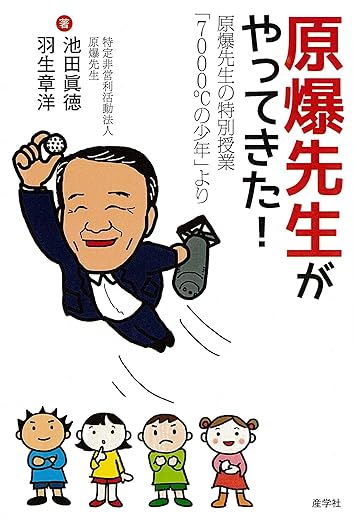
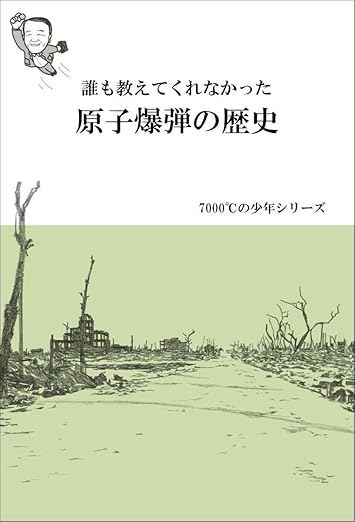
誰も教えてくれなかった 原子爆弾の歴史
著者はこれまで1,000校を超える学校で「原爆先生の特別授業」を行ってきました。その中で必ず語るのが、「広島に投下された原子爆弾は、わずか1kg、ゴルフボールほどのウランによって街が破壊され、14万人が命を落とした」という衝撃の事実です。広島の人口の約40%が、このたった一発の爆弾で命を奪われました。
この話を聞いた子どもたちは、はじめて原爆の恐ろしさを実感します。しかし、原爆の仕組みや開発の背景、当時の時代状況までを90分の授業で伝え切るのは不可能です。
興味を持った生徒がさらに調べようとして専門書を手に取っても、そこにあるのは難解な専門用語の連続。読み進められずにあきらめてしまうのが現実です。実際、著者自身もかつて同じように感じていました。
この本は、そんな「普通の人」にこそ読んでほしい、原子爆弾をやさしく解説する入門書です。
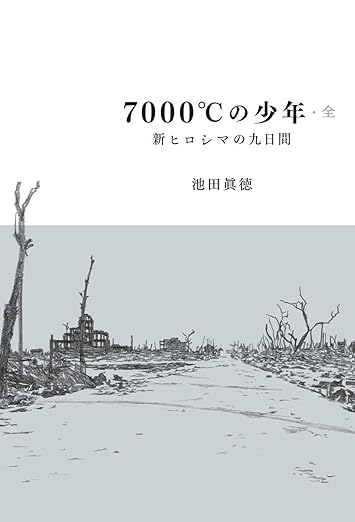
7000℃の少年 新ヒロシマの九日間
本書は、1945年8月6日の原爆投下直後、焦土と化した広島の爆心地に突入した若き特幹兵たちの奮闘を描く、実話に基づく戦争フィクションです。
主人公・義三(よしぞう)は、昭和19年に17歳で陸軍の特別幹部候補生隊に志願入隊。軍人一家に育った義三は、訓練でも学業でも常に優秀な成績を収め、1年後には兵長に昇進。特攻艇「マルレ」の操縦訓練に明け暮れていました。
運命の日、昭和20年8月6日。義三は物資調達の任務で広島市内へと足を踏み入れます。そして午前8時15分、爆心地からわずか3kmの地点で原子爆弾に遭遇します。奇跡的に無傷だった彼は、任務を果たそうとするものの、広がる惨状に直面し、圧倒され、自信を失います。
その日の夕方、義三は江田島の基地に戻るも、すぐに「広島救援」の命令が下されます。彼は第二班の班長として、同じく10代の少年兵8人を率いて再び被災地へ向かいます。
未曾有の被害と向き合いながら、彼らは徒歩で爆心地へ進み、瓦礫の街を歩き、焼けただれた川辺や橋の上で数え切れない被爆者と出会います。精神的に追い詰められる部下たちを前に、義三は不思議な冷静さを保ち、やがて内に秘めていたリーダーとしての資質を自覚していきます。
彼らの任務は、遺体の収容・焼却という過酷なものでした。その現場で、義三たちは人間の限界と希望の光の狭間でもがきながらも、確実に成長していきます。
支援に現れた上官・武田大佐や宮本少尉の導きも受けながら、仲間との絆を深め、命を懸けて行動する中で、少年兵たちは本物の「兵士」へと変貌していきます。
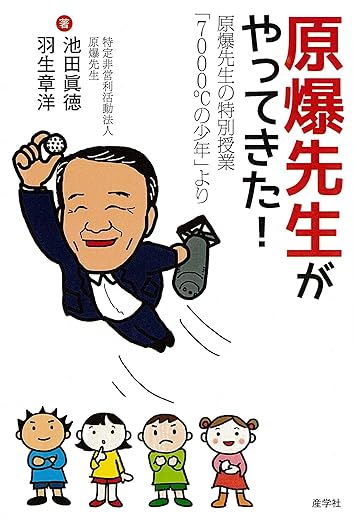
原爆先生がやってきた
東京都内の小学校を中心に、これまで600校以上・5万人超の児童生徒が受講してきた話題の授業「原爆先生の特別授業」。
この授業は、被爆体験を持つ実父の記録を出発点に、「戦争」や「原爆」という重いテーマを、子どもたち自身の“考える力”を引き出す形で伝えるユニークな取り組みです。
特筆すべきは、政治的な色合いを排し、あえて「平和」という言葉さえ使わずに構成されたその内容。受け身ではなく、自分の頭で感じ、考え、判断する――そんな能動的な学びが、多くの教育関係者や保護者、そして何より子どもたちから圧倒的な支持を集めています。
本書では、「原爆先生」の授業がどのようにして生まれ、なぜこれほど広がりを見せているのか、初めてその全容を明かします。授業の具体的な構成や演出の工夫、実際の教育現場での反応、そしてそこに込められた思いまでを丁寧に記録。
風化しつつある原爆の記憶を、次の世代にどう届けるのか――。
従来の“語り継ぎ”とは異なる、まったく新しい戦争教育のかたちがここにあります。
メディア
- フジテレビ 25分の全国放送「原爆先生、子供たちに伝えたいこと」(2015年)
- 毎日新聞 社会面「知識」伝える特別授業(2018年)
- 中日新聞「原爆先生 切迫の語り」(2019年)
書籍
- よくわかる勤務割表の書き方(日総研刊)
- ヒロシマの九日間(文芸社刊)
- 原爆先生がやってきた(産学社刊)
- 7000℃の少年 新ヒロシマの九日間(Kindle電子出版)
- 誰も教えてくれなかった 原子爆弾の歴史(Kindle電子出版)
講演実績
- 東京都内小学校(2,000校以上)
- 全国の中高校(200校以上)
この講師のおすすめポイント
池田眞徳(いけだ まさのり)さんは、特定非営利活動法人「原爆先生」の理事長として、全国2,100校以上で「原爆先生の特別授業」を行ってきた平和教育の実践者です。法政大学法学部を卒業後、日本電気(NEC)でシステム開発に従事。その後、テクトコンピュータ株式会社を設立し、証券・ゴルフ業界などに革新的なITソリューションを提供しました。
2009年、父の被爆体験を綴った手記をきっかけに、原爆の実相を次世代に伝える活動をスタート。「人を集めるのではなく、人の集まりに届ける」という姿勢で、全国の小中高校を訪問。アーカイブ映像・VFX・独自制作の映像を駆使した臨場感あふれる授業は、従来の“語り部”とは一線を画す、没入型のアクティブラーニングとして高く評価されています。
また、コロナ禍を機に映像配信にも対応。NHK・BBC・Getty Imagesなどの協力を得て、対面+オンラインのハイブリッド授業を可能にし、教育の可能性をさらに広げています。
◆ 原爆・戦争の実相を“体感”で学ぶ圧倒的臨場感
池田さんの講演は、従来の講義形式を超えた「体感型学習」。CG・音響・映像・ナレーションを融合させ、視聴者が戦争や原爆の非日常に“入り込む”ような没入体験を提供します。平和学習にありがちな「受け身の感想文」で終わらず、自ら考え、判断する主体的な学びへと導きます。
◆ 全国2,100校以上で実績、圧倒的なリピート率
これまでに全国で2,100校以上の小・中・高校で講演を行い、リピート率は75%超。一度受けた学校からの再依頼が非常に多く、その内容の質とインパクトの高さが証明されています。教員や教育委員会からの信頼も厚く、修学旅行の事前学習としても効果が高いと評判です。
◆ IT技術と教育を融合した“次世代型平和授業”
IT分野でキャリアを築いた池田さんならではの強みが、教育コンテンツにも活かされています。CGやアニメーション、リモート配信など、最新技術を駆使した講演は、デジタルネイティブ世代の生徒たちにも響きやすく、時代にマッチした新しい学びを提供します。
◆ 「人を動かす」ストーリーテリングの力
父の被爆手記『ありのままに』をもとに書かれた著書『ヒロシマの九日間』を軸に展開される語りは、事実に基づきながらもストーリーテリングの力にあふれ、聴く人の心を揺さぶります。事実を伝えるだけでなく、「自分だったらどうするか」を問いかける池田さんの語りは、強く記憶に残ります。
◆ 対面・オンライン両対応で学びを止めない
映像・音響・資料を組み合わせた授業は、対面はもちろん、オンラインやハイブリッド形式にも完全対応。学校現場の多様なニーズに柔軟に応える体制が整っており、コロナ禍以降も全国の教育現場から高い評価を受けています。再視聴できるコンテンツの提供も可能で、学びの定着にもつながります。
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。
お客様の声
戦争と原爆の体感学習
東京都の小学校(教員)
毎年六年生は原爆先生を申し込みます。そしてその多くの児童が授業とは全く違った衝撃を受けます。卒業直前、「これまで心に残っていることは何ですか?」との問いに、「原爆先生!」を挙げた児童がたくさんいました。毎度のことながら考えさせらる思いでいっぱいです。
私たち教員の年代は、戦争や原爆について知らない、理解できない世代となっています。しかし、知らないではすまされない、と思います。前半は映像を見たり、音を聴いたりするような場面、後半は原爆の知識を確認できる場面など、児童にとっても、教員にとっても魅力的な時間でとなりました。
広島・長崎への修学旅行事前学習
新潟県の中学校(教員)
池田様のお話は生徒の心に深く染み入るものでした。会場にいた生徒・教職員・保護者の全員が原爆投下時の広島の様子や悲惨な状況などを息をのんで聞き入っておりました。講師の語りは勿論、普段見ることができないアーカイブ映像や、原爆のCG映像など引き付けられる映像や画像が満載である中、一番印象に残ったのは義三様の映像でした。焦土の中、広島の焼け跡を懸命に進み、被爆者の救出や死体の焼却などに尽力された兵隊たちの様子が生々しく、痛ましく、その場の空気や臭いまでもが会場でも感じられました。さらには、原爆の仕組みや投下の状況なども詳しく教えていただきました。
原爆先生の平和学習
岐阜県の中学校(教員)
社会の授業で戦争や原爆は学習してきたものの、生徒たちは改めて平和の大切さ、戦争や原爆の恐ろしさを心から感じることができたようです。本校では、想像力と創造力という資質・能力の育成に取り組んでいますが、講師の平和学習によって、生徒や教員のすべてが戦時中の様子を想像しながら耳と心を傾けていました。今後は、創造力をもって身近なところから平和の実現に貢献してほしいと心から願っています。