佐々木信夫 ささきのぶお
経歴
1948年生まれ。早稲田大学卒業後、早稲田大学大学院政治学研究科博士前期課程を修了。東京都庁に入庁し、企画審議室などで16年間勤務。1989年3月、論文「都市行政学研究」で慶應義塾大学大学院より法学博士号を取得。同年4月に聖学院大学教授に転任。1994年から2018年まで中央大学教授、および同大学院経済学研究科教授を務める。2000年から1年間、米国カリフォルニア大学(UCLA)にて客員研究員として活動。2018年4月からは中央大学名誉教授として現職を務めている。
都庁職員から行政学者へ転身して以来、新たな自治体のあり方や道州制、大都市制度、そして新しい国のかたちや行政の仕組みについて論じ、日本の国家・地方の「あるべき姿」を提唱している。市町村合併に関するテレビ解説で、第4回NHK地域放送文化賞を受賞。2012年には橋下徹大阪市長から大阪市特別顧問に委嘱され、2015年までその職を務めた。また、政府の地方制度調査会委員(第31次)、日本学術会議会員(政治学、第22・23期)を歴任。2015年からは大阪府・市特別顧問として活動している。
主な講演テーマ
この国のたたみ方~日本州構想と活性化
日本が抱える課題の一つは人口減少社会と地域活性化です。この問題を解決するためには、現行の47府県制度を見直し、「道州制」への移行が効果的と考えます。道州制は、10州+2都市州に分け、各州が独自の権限で地域経済や社会問題に対応する仕組みです。これにより、地域に特化した施策が実現し、全国的な調整が効率的に行われます。
道州制導入により自治体間の競争が生まれ、経済や文化が活性化する可能性があります。特に人口減少が進む地方では、効率的な資源配分が行われ、過疎化対策や都市の過密化問題が解決されます。道州制を実現するためには強力なリーダーシップと改革が求められ、政治の力が必要です。
道州制の導入により、全国規模で競争が活性化し、地域経済が自立して国全体の経済力が強化されます。この改革は日本の未来に向けた大きな変革であり、実現には社会全体の理解と協力が必要です。講演では道州制のメリットと実現に向けたステップを説明し、地域主権国家への転換について掘り下げます。 ×
地方創生~東京一極集中の是正と地方再生
日本の最大の課題の一つは東京一極集中であり、経済、政治、文化が東京に集まり、地方は過疎化が進んでいます。このままでは地方の活力が衰退し、地域ごとの特性を活かした発展が難しくなります。石破政権が掲げた地方創生は注目されましたが、安倍政権下では実効性が問われ、東京に人や資金が集まり続けています。
これを是正し地方を再生するためには、「日本フリーパス構想」と「州制度移行」が必要です。日本フリーパス構想では、都市と地方をつなげる交通インフラ整備により、地方でも都市の仕事や文化にアクセスできるようにします。また、道州制を導入し、地方が自主的に政策を進めることで、地域経済の活性化を図ります。道州制によって地域間競争が生まれ、全体の発展に繋がります。
これらの改革が進めば、東京一極集中の是正と地方創生が実現し、日本全体の活性化が期待されます。しかし、改革には時間と政治的な合意形成が必要です。 ×
地方議会の活性化
日本の地方議会は重要な役割を担っていますが、現実的にはその影響力が十分に発揮されていません。現在、約35,000人の地方議員がいますが、地域課題解決や活性化にどれだけ貢献しているのかは不明瞭です。議員は地域に密着しており、地域の特性を理解し、影響力を持っていますが、多くの議会は官僚的で、トップダウンの意思決定が多く、議会の機能が発揮されていません。
地方議会の活性化には、議会改革が必要です。予算案承認や行政へのチェックだけでなく、地域発展に向けた戦略を議論し、実行する場であるべきです。議員一人一人が積極的に地域のために提案し、協力し合うことが求められます。また、議会の透明性を高め、市民とのコミュニケーションを強化することが重要です。デジタル化や情報公開を進めることで、市民が議会の活動に関心を持ち、議員との距離が縮まります。
地方議会が力を発揮すれば、地域の産業振興や観光戦略、教育や福祉の充実など、地域独自の課題に対処する施策が進むとともに、地域経済や社会福祉が向上します。地方自治が強化されれば、地域の自立が進み、地域特性に応じた政策を展開することができます。市民と議員が協力し、地方議会の重要性を理解することが、地域社会の変革に繋がります。この講演では、地方議会活性化のための具体的なステップや成功事例を紹介し、参加者が地域活性化に向けてどのように行動できるかを考える機会を提供します。 ×
書籍・メディア出演
書籍紹介
クリックすると、詳細が表示されます。
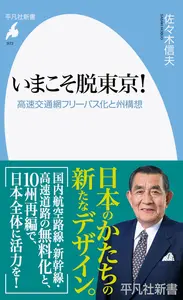
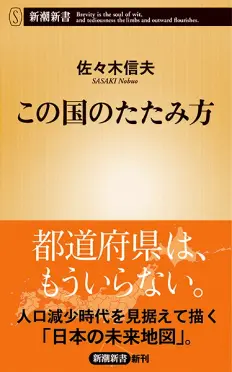
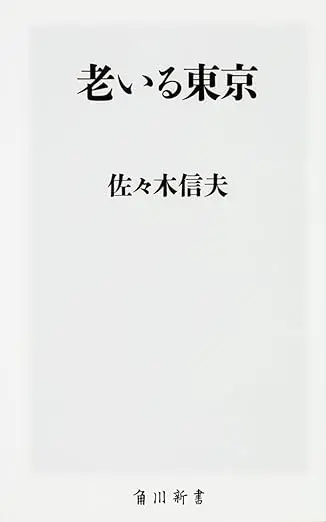
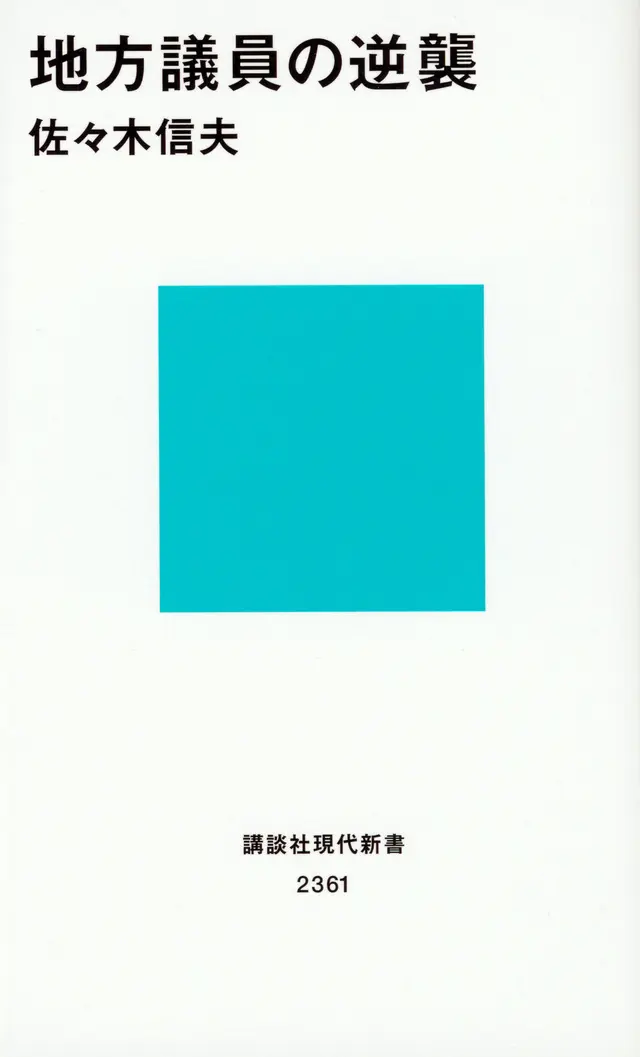
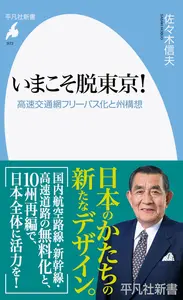
いまこそ脱東京! 高速交通網フリーパス化と州構想
日本の社会は多方面で限界に達していると言えます。行政の細分化が招いた無駄や非効率、また、スムーズな流通を妨げる高速交通システムの問題も深刻です。さらに、東京への人口集中がもたらす感染症リスクの増加も無視できません。今こそ、これらの課題を一度に解決する必要があります。日本の未来像を再構築し、再出発を遂げるために必要な方策とは何か。三大高速交通網のフリーパス導入と地方自治体の10州制への再編がその鍵となります。新たな時代に向けた希望を見据えた著者の力強い提案です。
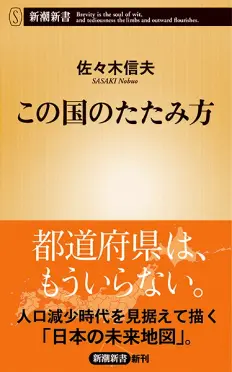
この国のたたみ方
徒歩や馬による移動が主流だった時代に設計された「都道府県」という制度は、現在ではその効率性を欠いていると言わざるを得ない。現在、日本の人口の半分以上が都市部に集中しており、今後の人口減少は避けられない現実です。この状況を踏まえ、地域の潜在的な力を最大限に引き出すために、「市町村+州」という新しい単位で統治機構を再構築する必要があります。長年、道州制の導入を提案してきた地方自治の専門家が描く、これからの日本のビジョンです。
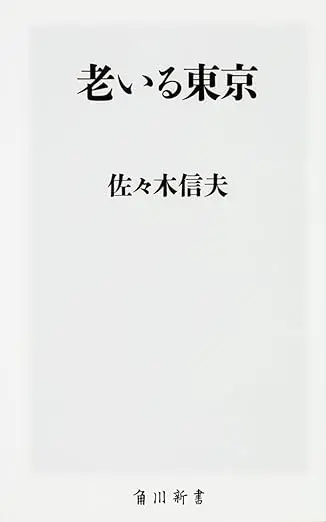
老いる東京
東京の現状において、急速に取り組まなければならない課題がいくつかあります。空き家の増加、人口の高齢化が進み、今や3人に1人が高齢者という状況です。築地市場の移転や五輪施設の問題が取り上げられる中で、東京の生活都市としての存続が切迫しています。待機児童問題や高齢者対策に加え、50年以上経過した道路や橋などのインフラの老朽化が進んでおり、これらの問題への対応は急務です。東京への人口集中は限界に達しており、かつて「大都市は豊かだ」とされた時代は終わりを迎えています。周辺のニュータウンが限界集落化しつつある中、都政の現実を長年見つめてきた著者が、深刻化する問題に鋭く切り込んでいます。
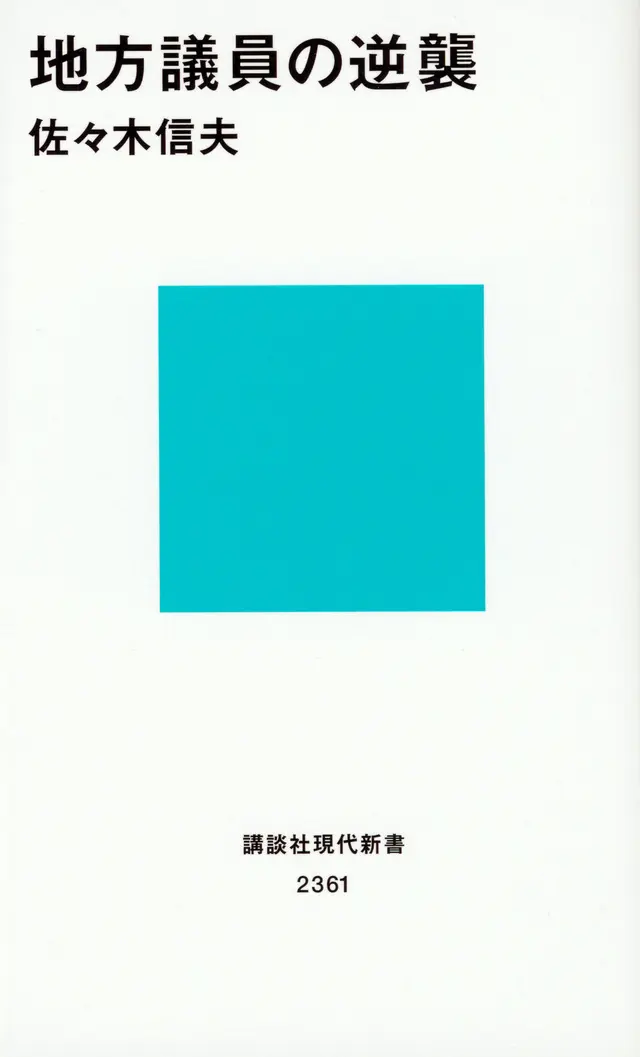
地方議員の逆襲
舛添都知事のような公私混同を繰り返す地方のリーダーが、なぜ登場し、許されてきたのでしょうか?また、地方議員の政務活動費に対する監視がなぜ甘いのでしょうか?さらに、「号泣会見」を開いたような不適切な地方議員がなぜ後を絶たないのでしょうか?地方議員選挙のあり方はどう変えるべきなのでしょうか?土日や夜間に地方議会を開催することで、どのような変化が期待できるのでしょうか?大阪都構想には依然として可能性があると言えます。今こそ、地方議員、地方議会、そして地方自治体を変えるラストチャンスです。地方から日本の未来を刷新するための指針となる一冊です。
地方政治家の金銭問題、特に舛添都知事の事例は、なぜ解決されずに続いているのでしょうか?その背後にあるチェック体制はどうなっているのでしょうか?地方議員も同様の問題を抱えていないのでしょうか?地方議会をどう変革すべきなのか?もし地方が日本を牽引する力となれば、この国は大きく生まれ変わることができるはずです。では、地方議員や地方議会をどのように変えていくべきなのでしょうか?
著者は東京都庁での勤務経験を持ち、近年では「大阪都構想」の議論において、橋下徹元大阪市長のブレーンとしても活躍。地方活性化や改革の理論的支柱として、新たな国家像を提案し続けています。舛添都知事や「号泣会見議員」が示すように、地方議会や議員が住民からかけ離れた存在となっている現状を、住民の手に取り戻さなければなりません。選挙制度や議会運営をどのように改革するのか?地方議員にとっての最も重要な役割、政策立案の方法論は何か?「大阪都構想」の真の利点とは何か?もう、舛添都知事や号泣議員のような失敗を繰り返してはいけません。地方創生に関わるすべての人々が必読すべき一冊です。
メディア
- TBS「ひるおび」
- テレビ朝日「ワイドスクランブル」「報道ステーション」「羽鳥モーニングショウ」
- フジテレビ「グットディ」「BSプライムニュース」
- NHK「視点論点」
- TOKYO MX「TOKYO MX NEWS」2009年4月〜、金曜コメンテーター
書籍
- 『現代都市行政の構図』(ぎょうせい、1985年)
- 『現代地方自治の座標』(勁草書房、1987年)
- 『政策学への発想』(ぎょうせい、1988年)
- 『都市行政学研究』(勁草書房、1990年)
- 『都庁-もう一つの政府』(岩波新書、1991年)
- 『自治体プロの条件』(ぎょうせい、1992年)
- 『新しい地方政府』(芦書房、1994年)
- 『自治体政策学入門』(ぎょうせい、1996年)
- 『視点/論点 分権時代を問う』(ぎょうせい、1999年)
- 『地方分権と地方自治』(勁草書房、1999年)
- 『現代行政学』(学陽書房、2000年)
- 『自治体の公共政策入門』(ぎょうせい、2000年)
- 『自治体の「改革設計」』(ぎょうせい、2002年)
- 『市町村合併』(ちくま新書、2002年)
- 『東京都政』(岩波新書、2003年)
- 『地方は変われるか』(ちくま新書、2004年)
- 『政策の潮流、改革のうねり』(ぎょうせい、2005年)
- 『自治体をどう変えるか』(ちくま新書、2006年)
- 『自治体政策』(日本経済評論社、2008年)
- 『現代地方自治』(学陽書房、2009年)
- 『地方議員』(PHP新書、2009年)
- 『道州制』(ちくま新書、2010年)
- 『都知事~権力と都政』(中公新書、2011年)
- 『新たな「日本のかたち」』( 角川SSC新書、2013年)
- 『日本行政学』(学陽書房、2013年)
- 『大都市行政とガバナンス』(中央大学出版部、2013年)
- 『人口減少時代の地方創生論』(PHP研究所、2015年)
- 『地方議員の逆襲』(講談社現代新書、2016年)
- 『東京の大問題!』(マイナビ新書、2016年)
- 『老いる東京』(角川新書、2017年)
- 『この国のたたみ方』(新潮新書、2019年)
- 『元気な日本を創る構造改革』(PHP、2019年)
- 『いまこそ脱東京!』(平凡社新書、2021年)
- など多数
講演実績
- 地方自治体
- 経済団体
- 地方議会
- 市町村アカデミー
- 自治大学校(総務省)
- 各都道府県幹部研修(研修所)
- 監査委員研修会(岩手県)
- 地方議員のあり方研修会(地方議会総合研究所)など
この講師のおすすめポイント
佐々木信夫さんは、中央大学名誉教授(法学博士)であり、日本の行政・地方自治に精通した第一人者です。東京都庁で16年間の実務経験を積んだ後、大学教授として長年にわたり地方自治・都市行政の研究に従事。地方制度調査会委員や大阪市特別顧問なども歴任し、政府や地方自治体の政策策定にも深く関わってきました。
また、NHK「視点・論点」への出演や、『この国のたたみ方』(新潮社)、『いまこそ脱東京!』(平凡社新書)などの著書を通じて、日本の行政・地方創生のあり方を発信。自治体関係者やビジネスパーソンに向けた講演も多く行い、分かりやすい解説が好評を得ています。
◆ 行政の実務経験と学術的視点を融合したリアルな講演
佐々木さんは、東京都庁での行政経験と研究者としての知見を活かし、現場に即した行政改革や地方自治の課題をリアルに解説。自治体職員や地方議員にとって、実践的に活かせる内容が満載です。
◆ 「日本州構想」など未来志向のビジョンを提言
著書『この国のたたみ方』では、「日本州構想」や「地方創生」の具体策を提案。これまでの「都道府県制」に代わる新しい国の形を提示し、地方の活性化について実践的な議論を深めます。
◆ 東京一極集中の是正と地方再生をわかりやすく解説
長年、都市行政を研究し、東京一極集中の問題点を指摘してきた佐々木さん。「地方創生はどう進めるべきか?」「自治体はどう生き残るべきか?」といった問いに対し、具体的な施策を提示し、聴講者の理解を深めます。
◆ 地方議会の活性化と政治の未来を考える
自治体の課題を解決するためには、議会の活性化が不可欠。地方議会のあり方や議員の役割について、「どうすれば住民に信頼される議会になるのか?」を具体的にアドバイスします。
◆ 行政・経済・ビジネスにも活かせる視点を提供
地方行政だけでなく、国の経済や企業の地方進出戦略にも応用できる視点を提供。自治体関係者だけでなく、ビジネスリーダーや政策立案者にとっても価値のある講演内容となっています。
佐々木信夫さんの講演は、地方自治体職員、議員、企業経営者、政策担当者にとって「これからの日本のかたち」を考える上で大変参考になります。未来志向の地方創生・行政改革を学びたい方におすすめです!
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。
お客様の声
地方議会の改革
実態に即したわかりやすい講演で参考になる。
地方創生~全国フリーパス構想
新幹線、高速道、ジェット機など高度高速網の運賃をタダにする。これが大評判。
東京をどうする、都政をどうする
都知事選や都議選をテーマに、東京都政の体験をもとにリアルに講演。好評!






