汐見和恵 しおみかずえ
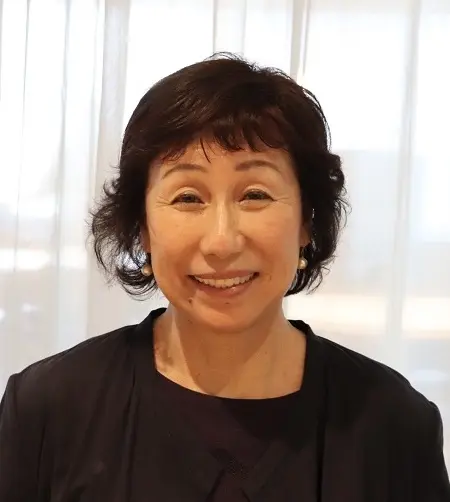
一般社団法人 家族・保育デザイン研究所 所長・保育ソーシャルワーカー/立教大学社会福祉研究所 特任研究員/フレーベル西が丘みらい園 前園長(現在は保育アドバイザー)/渋谷区 CO 渋谷アドバイザー
プロフィール
1951年、東京都生まれ。保育士、学習塾経営などいくつかの仕事の後、42歳で大学、大学院へ。専門は家族社会学と社会福祉学。家族関係や子育て支援・保護者支援、保育園・幼稚園の子どもの育ちと保育者の関わりなど、幅広く子育てと家族に関する研究をしている。
臨床育児・保育研究会では20年以上にわたり、保育者と共に保育実践や保育理論について学び、東京都 第三者評価委員を13年間務めた。新渡戸文化短期大学退職後はフレーベル西が丘みらい園園長を務め、子ども主体の保育を職員と一体となって進めてきた。現在は家族・保育デザイン研究所における活動の他、各所で保育者を対象とする講演・研修を行っている。近年は韓国の保育園・幼稚園との関わりも多くなり、韓国各地の保育園・幼稚園の視察を実施し、2023年には韓国において「日本における子どもの主体を大事にした保育」などの講演を2回行っている。
テーマ
出身・ゆかりの地
経歴
・一般社団法人家族・保育デザイン研究所代表理事(2016年12月〜2018年5月)
・新渡戸文化短期大学 教授(2005年4月〜2017年3月)
・聖心女子大学 非常勤講師(2015年4月〜2018年3月)
・NHK放送大学 テレビ『少子社会の子ども家庭福祉』ゲスト講師
第7回「就学前の保育・教育と子ども家庭福祉」、第8回「地域子育て支援と子ども家庭福祉」(2015年度〜2018年度)
・武蔵大学人文学部 非常勤講師(2005年4月〜2006年3月)
・東京福祉専門学校 非常勤講師(2004年4月〜2006年3月)
・都立北多摩看護専門学校 非常勤講師(2003年4月〜2005年3月)
・学習塾経営(1979年7月〜1994年2月)
・社会福祉法人なかよし保育園 保育士(1976年4月〜1979年3月)
【資格】
・社会福祉士
・社会学修士(立教大学大学院社会学研究科 後期課程満期退学)
・保育士
・東京都福祉サービス評価推進機構 第三者評価・評価委員(2005年〜2018年3月末)
【委員会・その他】
・和光市子ども
・子育て支援会議 副会長
・NPO 法人すくすく泉保育園理事
・まちの保育園六本木運営委員
【これまでの委員会・その他】
2012年2月〜現在 和光市子ども・子育て支援会議 副議長
2017年4月〜2021年度 NPO 法人さくらんぼ理事
2014年9月〜2016年度 国分寺市地域福祉計画策定委員会 子育て支援部会長
2012年4月〜2016年度 国分寺市子ども・子育ていきいき計画事業評価委員会 会長
2011年4月〜2016年度 国分寺市子ども・子育ていきいき計画推進協議会 会長
2012年度〜2014年度 武蔵野市幼児教育振興教育委員会 委員
2011年度〜2014年度 中野区次世代育成推進審議会 会長
2009年度〜2010年度 中野区次世代育成推進審議会 副議長
2008年度 内閣府「少子化社会対策に関する先進的取組事例調査」委員会委員
主な講演テーマ
こども主体の保育とは
ー幼児期のこどもとわたしたちー
こども主体の保育について考えます。なぜ「こども主体」が大切なのか。その保育とは。放任や自由との境界をどう考えるかなど、具体的な事例を元に検証していきます。 ×
こどもが主体となる保育と保育者のあり方
なぜ「こども主体」が大切なのか。そしてその保育とは。
こどもが主体となる保育について知り、自分なりの「こども主体の保育」と保育者の関わりを型取っていくことがゴールです。
一斉保育からの脱却、放任・見守り・自由との境界線、行事の考え方など、今の保育の基本的な考え方を実践を通して手にします。
【こんな人におすすめ】
・新任~リーダー層
・各クラス担任
・こども理解、保育を深めたい方
・こどもが主体となる保育の意味を見つめ直したい方
・こども主体の実践を知りたい方
【身につくちから】
・こども主体の保育を正しく理解し自園で活かす
・具体的な事例からも自分の保育と照らし合わせ振り返り実践する
・こども主体の保育を手にする
・さらなる保育の質向上 ×
書籍・メディア出演
書籍紹介
クリックすると、詳細が表示されます。
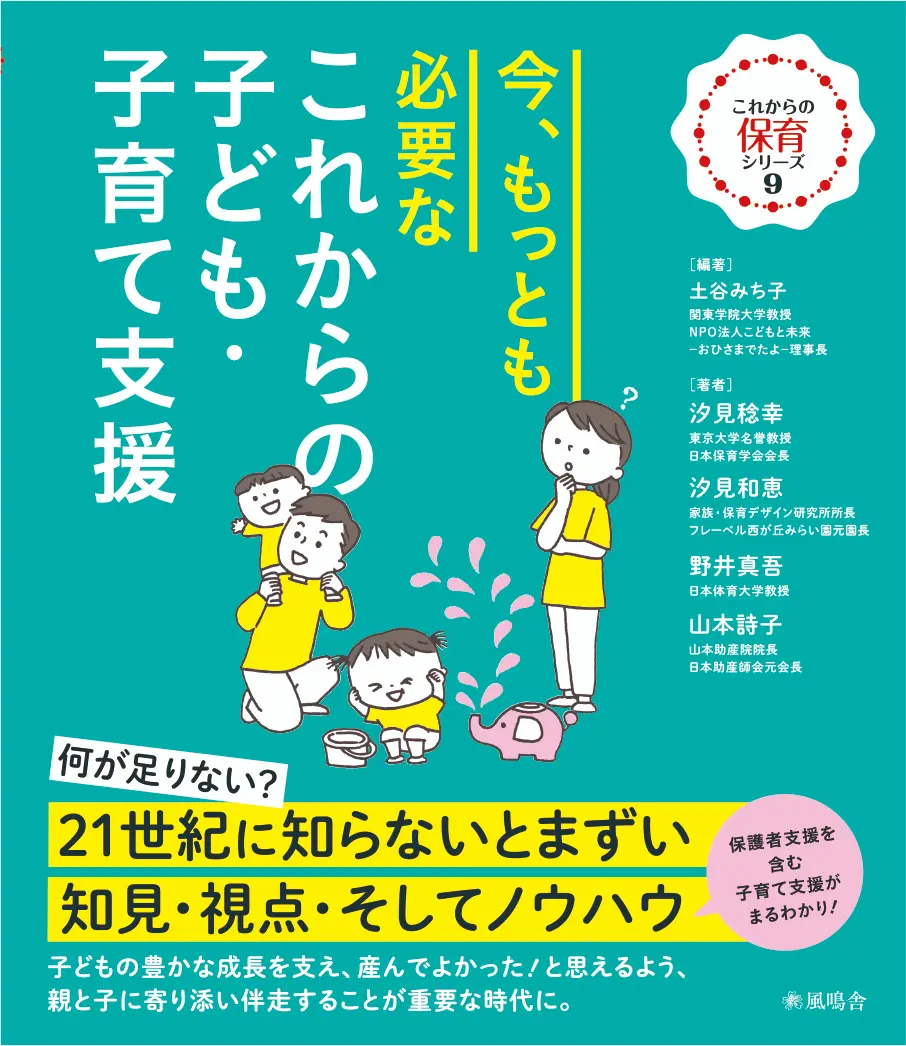
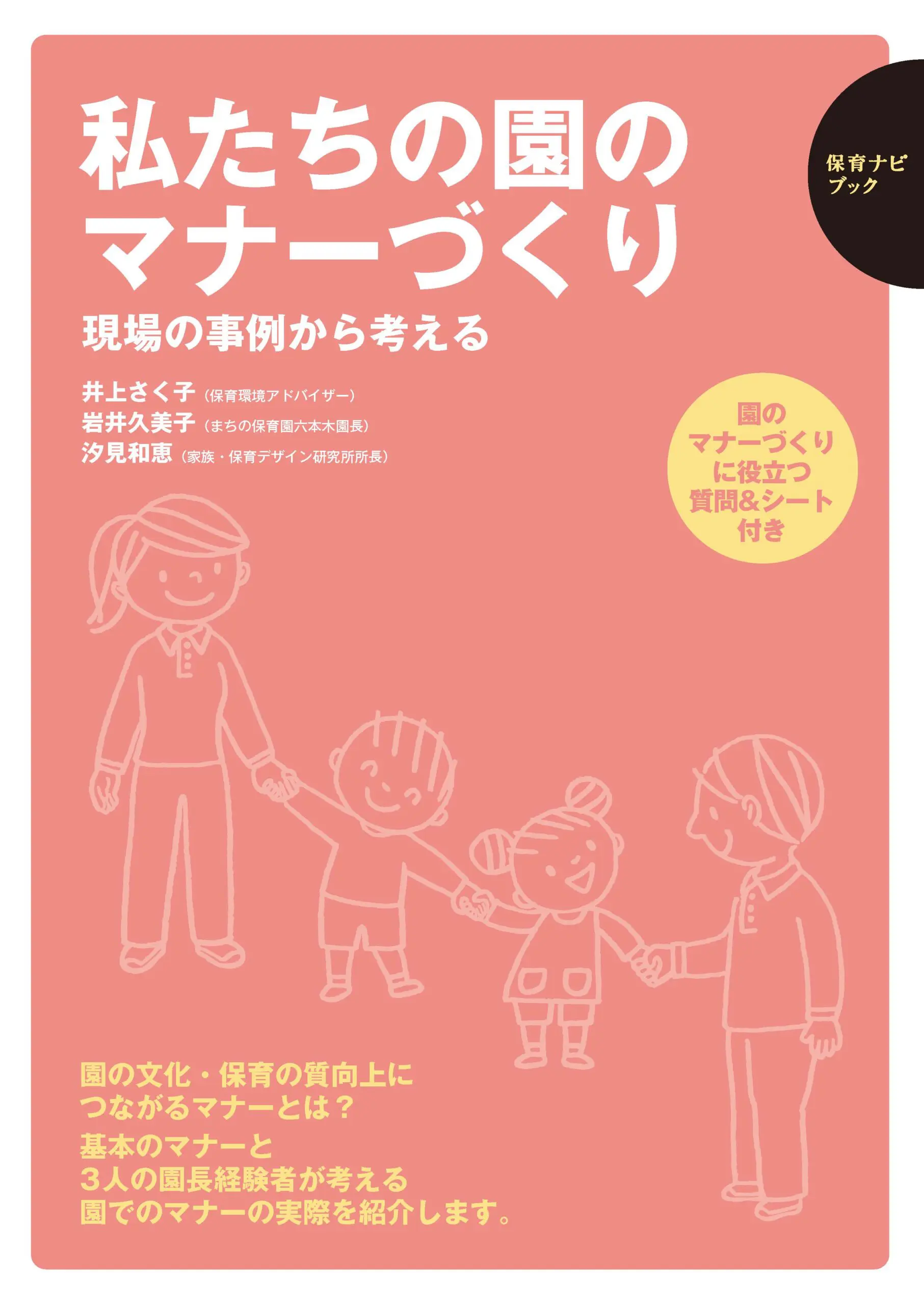
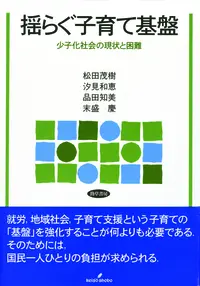
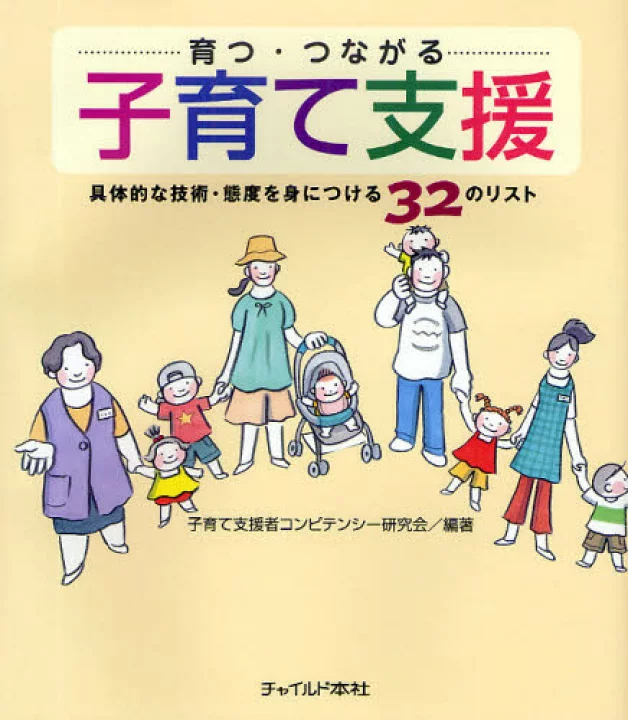
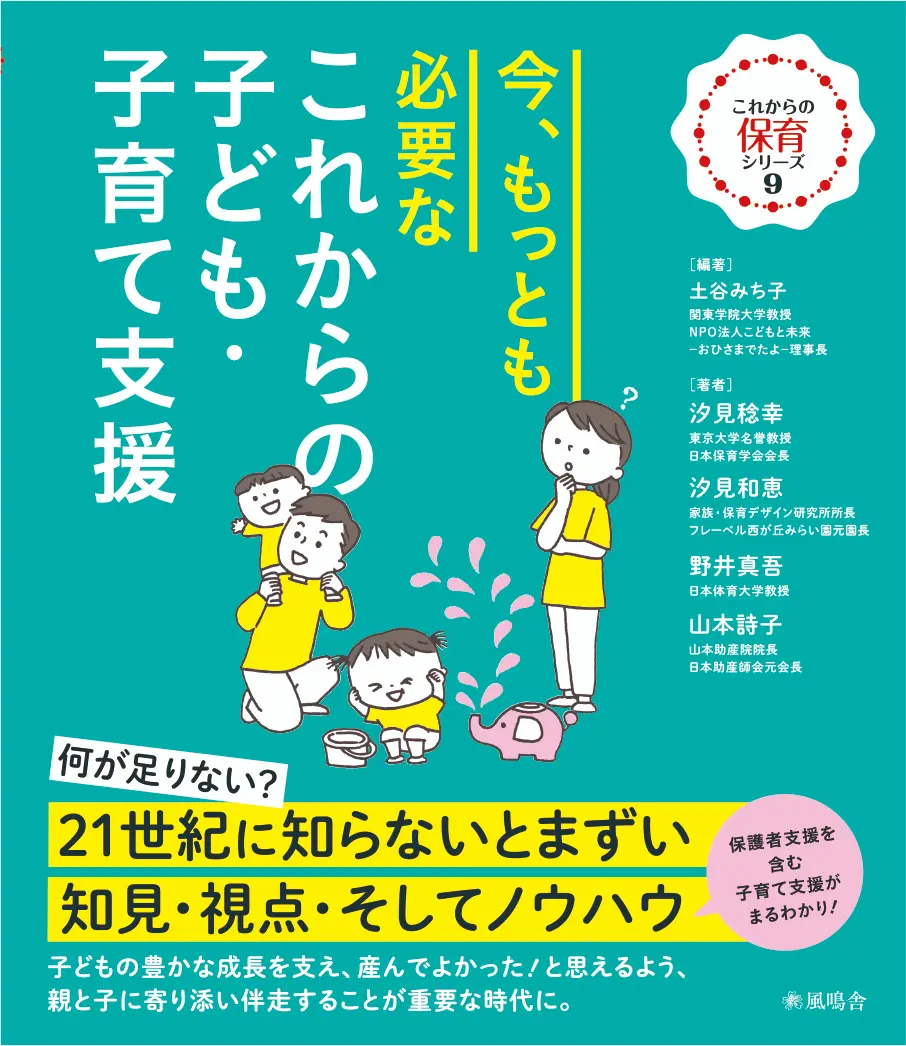
今、もっとも必要な これからの子ども・子育て支援
何が足りない? 21世紀に求められる知見・視点・そしてノウハウ。
子どもの豊かな成長を支え、産んでよかった! と思えるよう寄り添い伴走することが一層重要な時代に。
保護者支援を含む子育て支援がまるわかり。
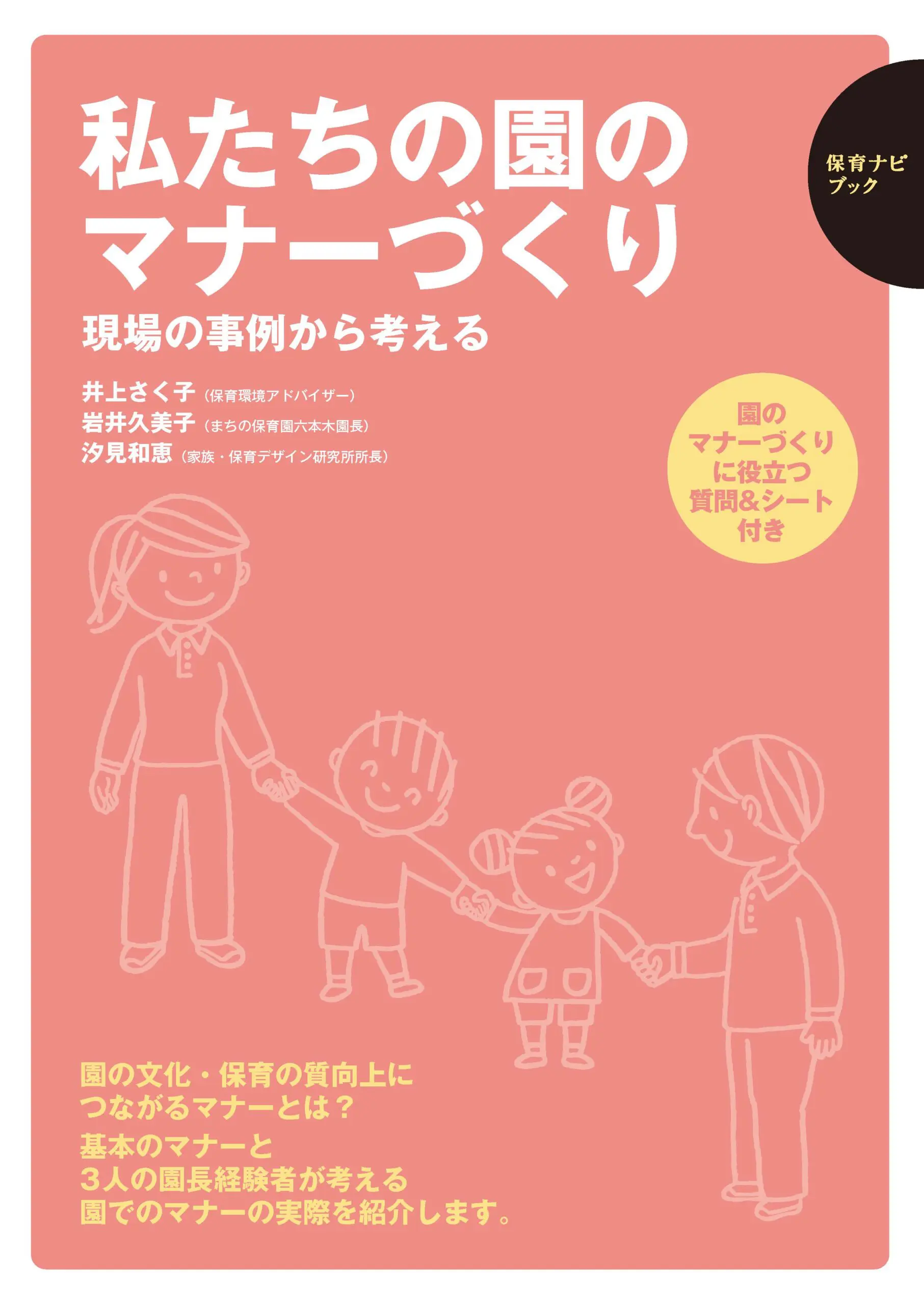
私たちの園のマナーづくり 現場の事例から考える
園の文化・保育の質向上につながるマナーとは? 基本のマナーと3人の園長経験者が考える園でのマナーの実際を紹介します。
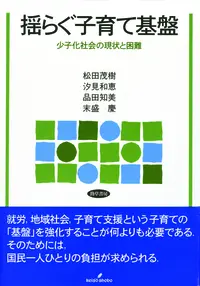
揺らぐ子育て基盤 少子化社会の現状と困難
就労、地域社会、子育て支援という子育ての「基盤」を強化することが必要である。そのためには、国民一人ひとりの負担が求められる。
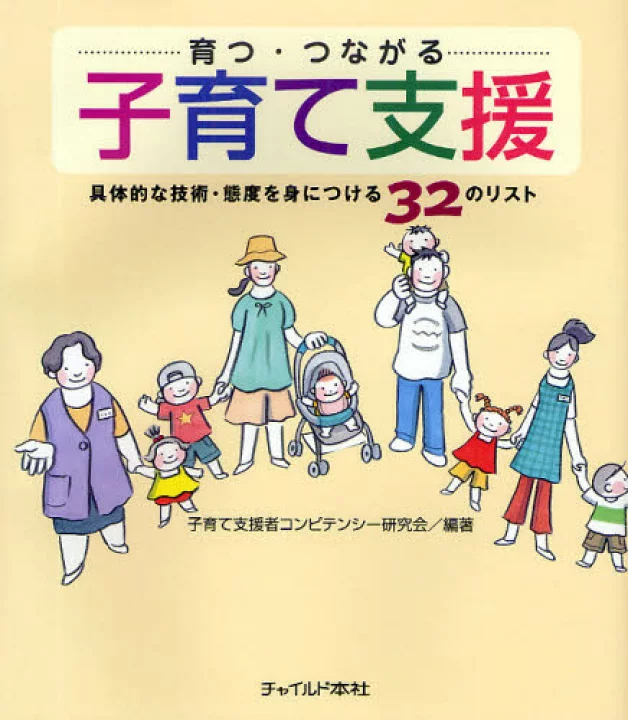
育つ・つながる 子育て支援具体的な技術・態度を身につける32のリスト
コンピテンシー(適正能力)の概念を生かして、子育て支援に求められているもの、あるべき姿を提示し、各地域、各施設の実情に合った子育て支援のやり方を見つけることができる「子育て支援」の入門・実践書です。
書籍
- 『今、もっとも必要なこれからの子ども・子育て支援』(共著)風鳴舎・2021年
- 『私たちの園のマナーづくり 現場の事例から考える』(共著)フレーベル館・2021年
- 『揺らぐ子育て基盤 少子化社会の現状と困難』(共著)勁草書房・2010年
- 『育つ・つながる子育て支援ー具体的な技術・態度を身につける 32のリスト』チャイルド本社 2009年・子育支援者コンピテンシー研究会
- 『社会福祉援助技術III 児童・家庭編』(共著)学分社・2007年
- その他、雑誌原稿は多数。
この講師のおすすめポイント
汐見和恵さんは、教育と社会福祉学の専門家であり、家族社会学や子育て支援に深い知見を持つ保育のスペシャリストです。東京都生まれで、長年にわたり保育士として実務に携わるとともに、学術的な研究と教育活動も行っています。大学院で家族社会学を学んだ後、保育と子育て支援の研究を本格的に行い、現在は一般社団法人家族・保育デザイン研究所の所長を務めています。また、フレーベル西が丘みらい園の前園長としても知られ、地域や国際的な活動にも積極的に関わっています。特に、韓国の保育園や幼稚園との交流活動が増えており、保育の現場で実践的な経験を共有するなど、国際的な視点から保育を見つめています。
◆ 家族・子育て支援の多角的なアプローチ
汐見和恵さんは、家族社会学と保育学を融合させたアプローチで、家族全体の育児支援に取り組んでいます。講演では、家族の役割や保護者支援、また保育者と保護者との協働の重要性について深く掘り下げています。この視点は、子育てに関わる全ての方々にとって貴重な情報源となります。
◆ 子ども主体の保育の実践的指導
汐見さんが提唱する「子ども主体の保育」では、子どもの自主性を大切にした保育のあり方に焦点を当てています。実際に保育現場での実践を交えながら、保育者としてどのように子どもと向き合うべきか、どうすれば子どもの成長を促進できるかを学べる貴重な機会です。
◆ 保育者の育成と実践的アドバイス
汐見さんは、長年にわたって保育者の育成に携わり、その経験から得たノウハウを伝えています。保育者の心構えや実践的なスキル、教育理論に基づくアドバイスを通じて、保育の質を向上させる方法を教えてくれます。これにより、保育現場での実務に役立つ具体的な指針を得ることができます。
◆ 地域と国際的な視野を持った保育の実践
汐見さんは、地域密着型の保育活動と共に、国際的な保育との交流も積極的に行っています。特に韓国の保育園との交流を通じて、異なる文化の保育方法を学び、実践的な知見を講演で紹介しています。国際的な視野を持った保育のあり方について学べる機会を提供しており、グローバルな観点からの保育の発展を促進します。
◆ 子どもと保育者のより良い関係を築く方法
汐見さんの講演は、子どもと保育者の関係性の改善にも重点を置いています。子どもの心理や成長過程を理解し、保育者がどのように接するべきか、また保育者自身の心のケアの重要性についても触れています。このような視点は、保育者としての役割を再確認し、より充実した職務遂行を支援します。
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。




