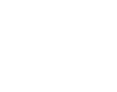Special 「人が辞めない会社」には理由がある——“サムライ社労士”が語る、人と組織を強くする職場づくりの極意【016 石井隆介さん】深堀りインタビュー!講師紹介リレー
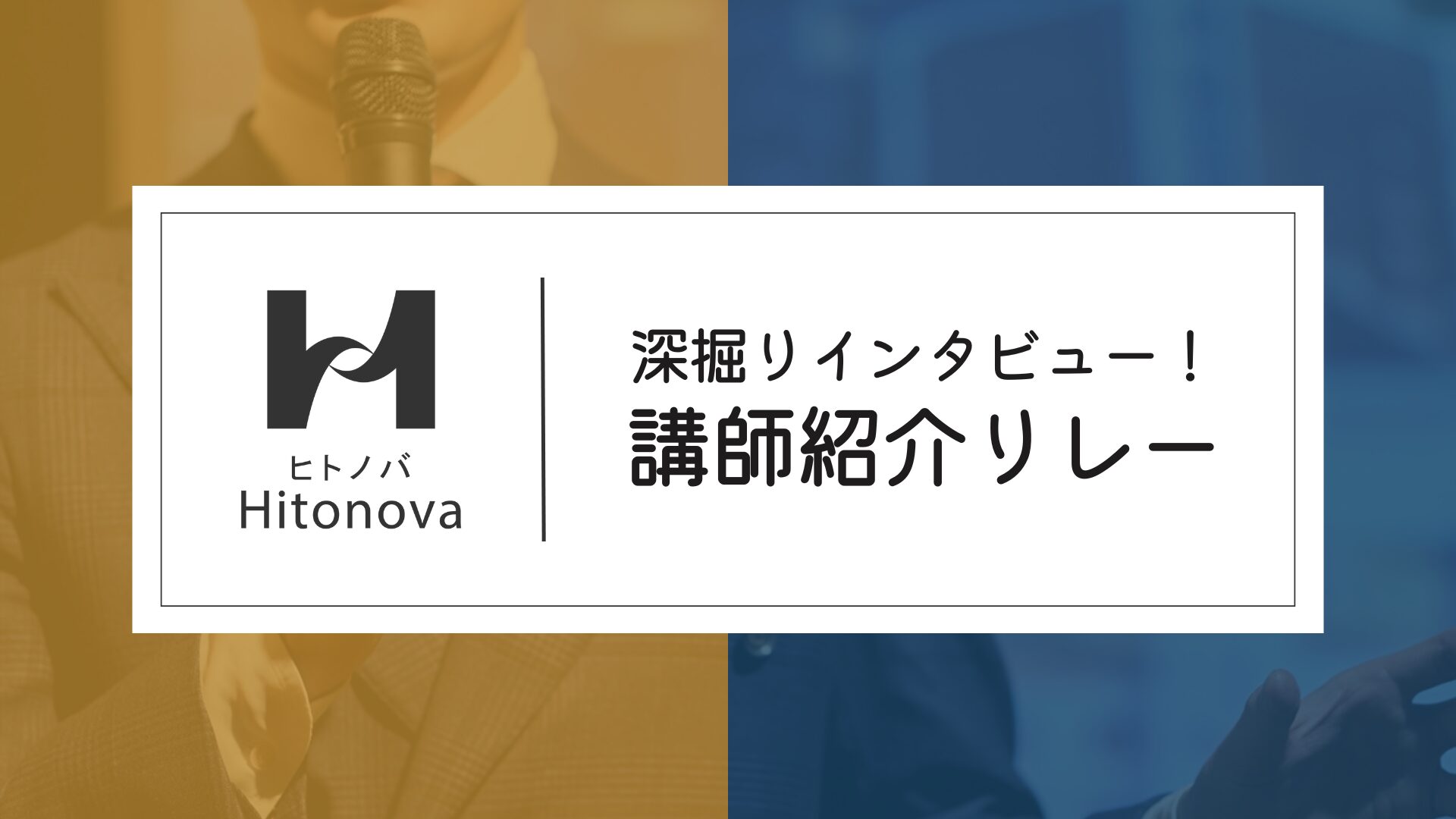
「人が辞めない会社」には理由がある——“サムライ社労士”石井隆介さんが語る、人と組織を強くする職場づくりの極意
中小企業を護衛する“サムライ社労士”として、全国の商工会議所や企業研修で注目を集めているのが、社会保険労務士の石井隆介さん。
金融機関での15年にわたる勤務を経て、延べ2,000人以上の経営者と接してきた経験から、「人と組織の関係こそが経営の土台である」と痛感したといいます。
独立後は「人材が辞めない会社づくり」を掲げ、労務管理の見直しや助成金活用を通じて、350社以上の現場改善をサポート。法律論にとどまらない“現場目線の提案力”が、多くの経営者から信頼を集めています。
現在は「人材が辞めない会社づくり」を掲げ、労務管理の見直しや助成金活用を通じて350社以上を支援。現場目線の提案力に定評のある石井さんに、今回は“人が定着する職場づくり”の秘訣を伺いました。
石井隆介 さん
中小企業を護衛するサムライ社労士/人材定着コンサルタント
ジャンル:業務改善・コストダウン・働き方改革・意思決定・マネジメント・経営論・人材育成・人事・リーダーシップなど
人気の講演テーマ
「年収の壁」対策セミナー~非正規労働者のさらなる戦力化のコツ~
管理職のための「パーソナルブランド」セミナー
賃上げが怖くなくなる!定時短縮メソッド
ここがおすすめ!
社会保険労務士・石井隆介さんの講演は、「人が辞めない職場づくり」を実現する実践的な内容で高い支持を集めています。「年収の壁」対策セミナーでは、最新の社会保険・税制改正を踏まえ、パート戦力化と正社員化のポイントを具体的に解説。「パーソナルブランド」セミナーでは、管理職が自分の強みを言語化し、信頼されるリーダーになる方法を学べます。さらに「定時短縮メソッド」では、労働時間を短縮しながら生産性を高める独自手法を紹介。人手不足・賃上げ・定着率改善など、中小企業の課題解決に直結する内容で、経営者・管理職必聴のプログラムです。
Q1. 社労士を志したきっかけについて
金融機関勤務を経て、「お金ではなく人が会社を支える」と気づいた原点
金融機関で15年間勤務された中で、どのような出来事が「人と組織の関係を良くしたい」という想いにつながったのでしょうか?
石井さん:
「金融機関で15年間、中小企業の経営者の方々に資金面での支援を行ってきました。
融資や経営相談を通じて、事業を支えるやりがいも感じていましたが、次第に『お金の問題』だけでは解決できない問題で悩む経営者を多く見るようになりました。
特に多かったのが、人に関する悩みでした。
『採用してもすぐ辞めてしまう』『現場がうまくまとまらない』『後継者が育たない』。
数字では測れない、組織の内側にある課題こそが、経営を左右していると実感するようになりました。 人口減少が進むこれからの時代、企業を本当に支えるのは『資金』ではなく『人』だ。
そう確信したことが、社会保険労務士を志すきっかけになりました。
経営者の悩みにもっと深く寄り添い、人と組織の関係を整えることで企業を強くするというミッションを掲げて、勤務社労士を経て独立をしました。」

Q2. 独立後に感じた中小企業の現場課題
“任せる文化”が人を育てる。成長実感がある会社は強い
これまで350社以上を支援されてきた中で、特に印象的だった「人が辞めてしまう会社」と「人が定着する会社」の違いは何だと感じますか?
石井さん:
「決定的な違いは、『人を信じて任せられるかどうか』です。
人が定着する会社には、社員を信じて仕事を任せ、必要なときに後ろからそっと支える管理職が育っています。任された社員は『自分を信じてもらえた』と感じ、自ら考え行動するようになります。結果として、責任感と主体性が芽生え、仕事の中に自分の成長を感じるようになるのです。
良い会社は、社員が『この会社で成長できる』と実感できる職場です。
日々の仕事の中で、自分の力が少しずつ広がっていく感覚。この成長実感こそが、最も強い定着要因です。
給与や待遇だけでは人は動きません。自分の存在が認められ、任された仕事の先に『成長の手ごたえ』があると感じられるとき、人は長く働く意欲を持ち続けます。
一方で、人が辞める会社には任せる文化がありません。
トップがワンマンで、管理職や中堅層が育っていない。結果として、重要な判断をすべて経営者が抱え込み、『自分がやらないと回らない』組織になっています。
そうなると社員は責任を持つ機会を与えられず、成長を感じられないまま会社にいる意味を見失ってしまいます。
今後の日本社会は、人手不足と高齢化がますます進みます。
『人を信じて任せる』ことで社員の成長を引き出し、その過程で会社も一緒に成長していく。
これから生き残る会社は、そうした人の成長に投資できる組織です。
成長実感を与えられる会社が、最終的に『人が辞めない会社』になるのだと、私は確信しています。」
Q3. 「定時短縮メソッド」誕生の背景
“時間を変える”と“働き方”も変わる——短時間労働の効果とは
「長時間労働をやめ、短時間でも成果を出せる会社へ」というテーマを掲げるようになった背景や、実際に成果が出た事例を教えてください。
石井さん:
「“定時短縮メソッド”を考案するきっかけは、私自身の転職経験でした。
以前、8時間労働が当たり前の会社から、7時間20分定時の会社に転職したときに、たった40分の違いで仕事の集中力や職場の雰囲気が大きく変わることを体感したんです。
短くなった分だけ、みんなが『どう時間を使うか』を真剣に考えるようになり、無駄な会議や残業が自然と減っていきました。
社労士として独立した後、この経験を労務改善の仕組みとして再現できないかと考えたのが始まりです。
特に、今の中小企業が抱える課題は『生産性が上がらないのに最低賃金だけが上がる』という構造的な問題です。
だからこそ、時間の使い方を見直すことが、最も効果的な経営戦略になると確信しました。
実際に導入した企業では、残業時間が月60時間から15時間に減少し、設立60年で過去最高の売上を記録しました。
さらに、売り上げが設立10年で初めて1億円を超え、決算賞与を支給できた会社もあります。人材定着に悩みを抱えていた葬儀社の離職率が3割減少するなど、目に見える成果が続出しています。
単に労働時間を減らすだけでなく、「人の悩みを解決しながら業績も上げる」。
これこそが、私の提唱する定時短縮メソッドの最大のメリットです。
もはや8時間定時の時代は終わりました。」

Q4. 経営者へのアドバイスとして大切にしていること
業界への誇りを持つ経営者は、必ず伸びる
経営者と向き合う中で、「この考え方を持っている会社は伸びる」と感じる共通点はありますか?
石井さん:
「それは『業界で働く人の社会的地位を上げたい』と本気で思っている経営者です。
単に自社の業績や利益だけを追うのではなく、『この仕事に誇りを持てる人を増やしたい』『うちの業界をもっと良くしたい』という思いを持っている経営者の会社は、確実に伸びています。
たとえば、従業員が努力して成果を上げたとき、昇給や賞与を支給しながら、その理由を丁寧に説明してくれる経営者がいます。
『あなたのこういう頑張りが、会社を支えてくれたからだよ』と伝える。
その瞬間の経営者の顔は本当にうれしそうで、満面の笑みを浮かべています。
そこには、人を育てることに喜びを感じる経営者としての誇りがあります。
こうした経営者は、社員をコストではなく『仲間』として見ています。
だからこそ、給与や評価の背景をきちんと説明できる。
『なぜ昇給できたのか』『なぜこの賞与が支払えるのか』を言葉で伝えることで、社員の納得感と信頼感が生まれます。
その積み重ねが、会社全体のエンゲージメント(組織への愛着)を高めているのです。
一方で、数字だけを追いかける会社は、短期的な成果は出ても長続きしません。
人を大切にする会社は、一見時間がかかるようでいて、結果的に人が辞めずに育つ強い組織になります。
『社員の人生の質を上げたい』『この業界をもっと誇れる場所にしたい』
そんな志を持つ経営者の言葉や行動には、いつも一貫性があります。
そして私は、そういう経営者の背中を支えることが、社労士としての最もやりがいのある仕事だと感じています。」
Q5. 「年収の壁」や人手不足など、今の労務課題への提言
“制度の誤解”が人手不足を招く。まずは正しい理解から
現場を見ていて、企業が「年収の壁」や人手不足の問題を乗り越えるために、まず取り組むべきことは何だと思いますか?
石井さん:
「『年収の壁』の問題は、制度そのものよりも知識不足や思い込みによって起きているケースが圧倒的に多いと感じています。
『103万円を超えたら損をする』『扶養から外れると働けなくなる』といった誤解が、現場の働き方の選択肢を狭めているのです。
実際には、制度を正しく理解すれば、短時間パートのフルタイム化や正社員化は十分に実現できます。
大切なのは、国の施策を待つのではなく、会社主導で説明と対話を重ねることです。
経営者や総務担当者が、従業員一人ひとりに『この制度はこう変わる』『こうすれば働き方を広げられる』と丁寧に説明していくことで、働く側の不安は確実に減っていきます。
実際、私が支援している企業でも、説明会を繰り返し行うことで『壁を超えても大丈夫』と理解が広がり、結果として戦力化・正社員化の流れが進みました。
労務管理の出発点は制度を正しく伝えることです。」

Q6. 管理職の「パーソナルブランド」について
“完璧な上司”より“信頼できる上司”を——自分を知る力が信頼を生む
部下から信頼される管理職には、どのような共通点がありますか?
また、管理職自身が“自分ブランド”を築くために意識すべきことは?
石井さん:
「信頼される管理職の条件は、『自分の強みを理解し、それを自分の言葉で語れる人』であることだと思います。
上司として完璧である必要はありません。
むしろ、自分の得意・不得意を正直に認め、それをチームにわかりやすく伝えられる人ほど、部下からの信頼は厚くなります。
なぜなら、自分を知っている人は、他人も大切にできるからです。
多くの管理職が『どうすれば部下を動かせるか』を考えますが、最初に取り組むべきは『自分をどう表現するか』です。
私は研修の中で、『自分の強みを言語化し、それを周囲に一貫したメッセージとして伝える』ことをワークにしています。
これができると、リーダーとしての軸がブレなくなり、どんな局面でも落ち着いて判断できるようになります。 部下は、完璧な上司よりも『信頼できる上司』を求めています。
その信頼を生むのは、肩書きではなく、自分の言葉で語れる力。
それこそが、管理職が築くべき『パーソナルブランド』なのです。」
Q7. 今後の展望・伝えたいメッセージ
「雇う・雇われる」から「共に成長する」関係へ
これからの日本の中小企業にとって、“人と組織の関係”はどう変わっていくべきだと考えていますか?
また、講演を通じて伝えたいメッセージをお願いします。
石井さん:
「これからの時代、企業と人の関係は『雇う・雇われる』から『共に成長する』へと進化していくべきだと考えています。
かつては会社が与え、社員が従う時代でしたが、いまは違います。
働く人が自らの成長を実感しながら仕事に取り組めるかどうか。そのことが、会社の成長と直結する時代になりました。
中小企業にとって人材は最大の資産です。
だからこそ、『この会社で働くことで自分が成長できる』と社員が思える仕組みを整えることが大切です。
それは特別な制度ではなく、日々のコミュニケーションや評価の中で成長実感を感じさせること。
人は成長を感じられる場所にこそ、長くいたいと思うものです。
また、会社側も『人に依存しすぎない仕組みづくり』を同時に進める必要があります。
仕事を個人任せにせず、業務を見える化し、共有化する。
それが進むと、個人の成長と組織の安定が両立します。
私はこれを時短労務と呼び、単なる労働時間短縮ではなく、『無駄を減らし、生産性を高め、余裕を生み出す仕組み』と定義しています。
講演で大切にしているのは、『わかった』ではなく『できる』と感じてもらうことです。
単に正解を教えるのではなく、『答えを導くためのヒント』をお伝えするようにしています。
その会社なりの最適解を、自分たちで見つけてもらうことを目的にしているからです。
だからこそ、私は常に行動につながる語り掛けを意識しています。
人と組織の関係を変えることができれば、会社の未来は確実に変わります。
社員を信じ、成長を支え、仕組みで守る。その3つのバランスが取れた会社こそが、これからの時代を生き残る。
私は講演を通じて、その一歩を踏み出す勇気を多くの経営者に届けたいと思っています。」
石井隆介さん、ありがとうございました!
Contact お問い合わせ
講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。
気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。
5営業日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。