Special 経営者が休むと、会社は強くなる〜「両想いビジネス」で“頑張りすぎない成功”をつくる〜【017 松山智弘さん】深堀りインタビュー!講師紹介リレー
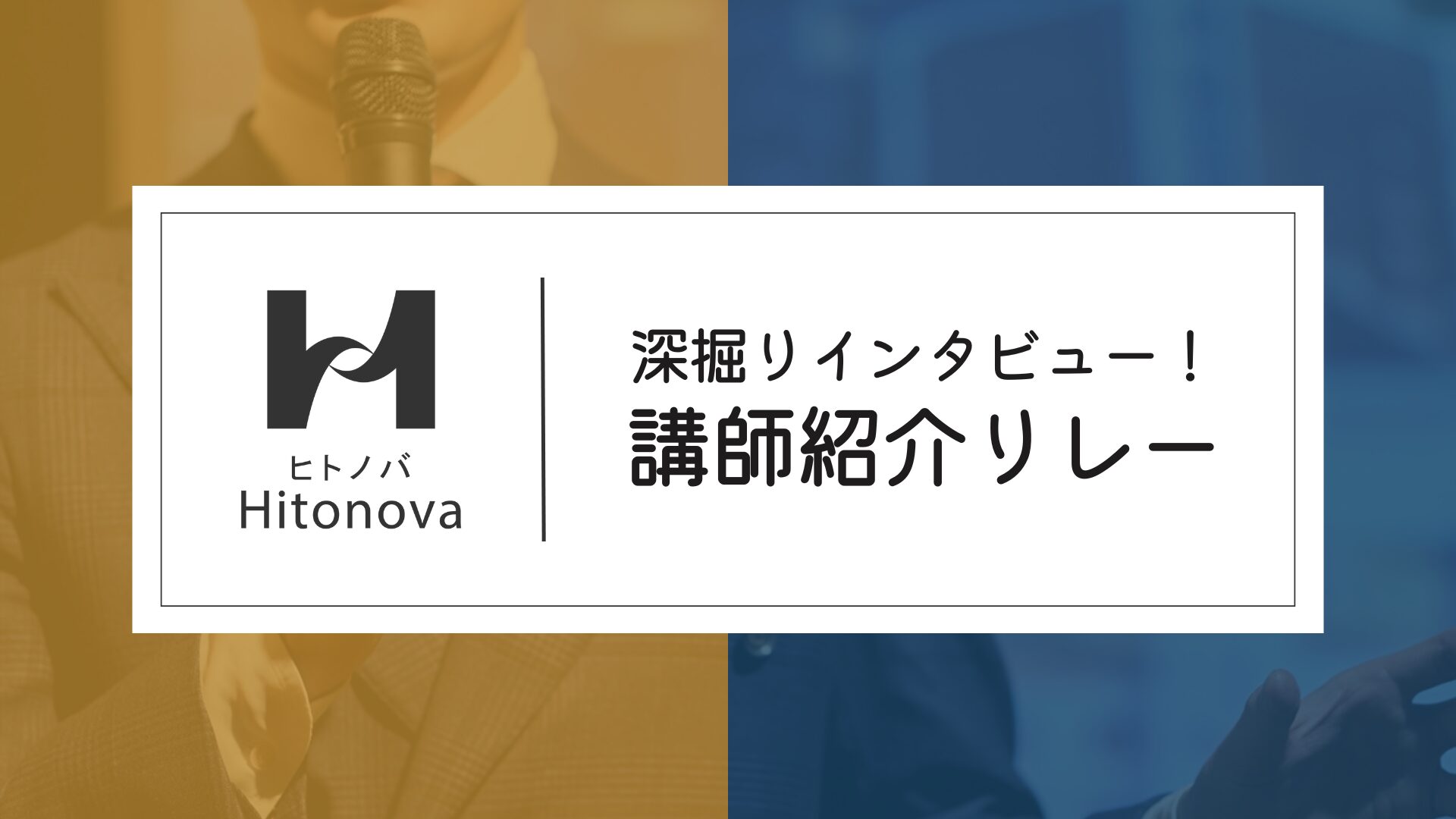
働きすぎ経営者に広がる「休む経営」という新発想
経営者自身が“働きすぎ”に苦しむ時代。
「長時間働かないと成果は出せない」という思い込みを手放し、業績と幸福の両立を実現する経営者が増えています。
その背景には、“休むことで会社を強くする”という新しい発想を広めるコンサルタント・松山智弘さんの存在があります。
ご自身も過労と挫折を経験し、「両想いビジネス」という独自の哲学を築いた松山さんに、働き方・経営・そして幸せなビジネスの本質について伺いました。
松山智弘 さん
両想いビジネス研究所 所長/「経営者の長時間労働をやめても業績を上げられる仕組みづくり」を支援するマーケティング戦略コンサルタント
ジャンル:従業員満足度(ES)・ブランディング・顧客満足(CS)・キャリアデザイン・働き方改革・ワークライフバランス・副業・マーケティング・経営・起業・自己実現・自己啓発・コミュニケーション
人気の講演テーマ
「働きすぎ経営者」が失うもの~信頼・利益・家族を守る働き方改革~
社長が“休んだら”売上5倍!?「休む経営」の思考術と実践術
ここがおすすめ!
1987年大阪府生まれ。関西大学工学部を首席で卒業後、Webマーケティング会社に入社し、100社以上を支援。試用期間中に年間MVPを受賞。
その後、美容クリニック企業で月商1.3億円の事業を3.5億円超へと成長させ、独立。SNS炎上や過労による挫折を経て、「自分と両想いになる働き方」の重要性を実感。
現在は、経営者が長時間労働をやめても業績を上げられる仕組みづくりを支援し、「休む経営」を広める講演やコンサルティングを行っている。
「両想いビジネス」とはどんな考え方か
誰も犠牲にしない経営を目指して
まずは松山さんが提唱されている「両想いビジネス」について教えてください。どのような考え方に基づいているのでしょうか?
松山さん:
『「両想いビジネス」とは、経営者自身・お客様・スタッフ・家族など、ビジネスに関わるすべての人が幸せになることを目指す経営のあり方です。
言い換えると、“誰かを犠牲にしないビジネス”とも言えるかもしれません。
多くの経営者さんが「頑張らないと成果は出ない」「お客様のために自分を後回しにするのが当然」と思い込んでしまいがちです。
でも実際は、それでうまくいく人ってほとんどいないんですよね。
私自身もそうで、若い頃は“寝る間も惜しんで働く”タイプでした。
しかし、気づいたときには心も体もボロボロになり、大切な人間関係まで壊れてしまっていたんです。』
経営者自身が“自分と両想い”になることから始まる幸せの連鎖
なるほど。では、経営者が“両想い”になるために、何から始めるべきでしょうか?
松山さん:
『まずは経営者自身が“自分の本心”としっかり向き合い、やりたいこと・やりたくないことを明確にすることが大切です。
それをベースに事業を設計していくと、自然とお客様やスタッフ、家族など、周囲の人たちとも良い関係が築ける。
これが、私が提唱している“両想いビジネス”の土台です。
たとえば、自分が無理して提供していたサービスを手放したら、本当に価値を感じてくれるお客様だけが残ったり、経営者自身が楽しそうに働いている姿を見て、スタッフが前向きに動き始めたり──。
“経営者が自分自身と両想いであること”が、結果的に長時間労働に頼らない経営や、業績アップ・チームの成長につながっていくんです。』

過労・炎上の経験から見えた“頑張りすぎ”の代償
「休みたいけど休めない」──強制終了が教えてくれたこと
松山さんご自身も過労やSNS炎上を経験されたとか。どのように乗り越え、現在の「休む経営」へとつながったのでしょうか?
松山さん:
『そうですね……今でこそ「休む経営」や「両想いビジネス」をお伝えしていますが、昔の私は真逆でした。
「成果主義で生きることが善」と信じて疑わなかったんです。
成果を出すために、朝から深夜まで働き、睡眠時間は3時間。そんな生活をしたこともあります。
でも本音では、「こんな無理して頑張る生き方はもう嫌だ」と感じていました。
それでも、頑張って成果を出す生き方しか知らないから、本心を無視して頑張り続けてしまう……。
そんな“休みたいけど休めない”状態を続けていると、やがて「休みたい」を歪んだ形で叶えてしまうんですよね。
交通事故や病気で入院、離婚、信頼していた人の裏切りなど──。頑張りすぎ経営者なら、誰もが一度は経験している「強制終了」です。
私自身も3ヶ月以上の高熱に悩まされて入院し、売上がゼロになった時期がありました。
そして、自分が頑張りすぎているときほど、人への思いやりも薄れていくものです。
口では「お客様のため」「社員のため」と言っていても、心の奥では「自分の成果のため」に動いてしまう。
その結果、私はお客様との小さなトラブルをきっかけにSNSで炎上し、精神的にもどん底に落ちました。』
自分の本心とビジネスを一致させたとき、成長が始まった
松山さん:
『そんな中で気づいたのが、「頑張り方を間違えると、人もビジネスも壊れてしまう」ということ。
そこから少しずつ、「どうすれば“自分を犠牲にしなくても成果が出るのか”」を研究し始めたんです。
心理学やマーケティングを徹底的に学び、実際の経営現場で検証を重ねました。
そして見えてきたのが、“自分の本心とビジネスを一致させること”が、最大の成長戦略になるという答えでした。
最初は半信半疑でしたが、思い切って“やりたくない仕事”を手放してみたら、不思議なことにお客様の質が変わり、売上も安定し始めたんです。
そのとき初めて、「休むことは悪ではなく、経営の一部なんだ」と実感しました。
つまり、「休む経営」こそが、経営者自身とビジネスに関わるすべての人を救う方法だったんです。
あの過労と炎上の経験があったからこそ、今の活動があります。
つらい時期ではありましたが、今振り返ると、あれが“自分と両想いになるためのターニングポイント”だったと思っています。』
なぜ「社長が休むこと」が経営戦略になるのか
休むことは逃げではなく“思考のリセット”
松山さんは「社長が休むことこそが経営戦略」とおっしゃっています。少し逆説的にも聞こえますが、その理由を教えてください。
松山さん:
『経営者が働きすぎると、どうしても“視野”が狭くなります。
疲れているときほど、目の前の数字やトラブルにばかり反応してしまって、長期的な判断ができなくなるんです。
でも、しっかり休む時間を取ると、「なぜ自分がこの仕事をしているのか」「何を本当に大切にしたいのか」が見えてきます。
つまり、休むことは“逃げ”ではなく、思考と感情をリセットして経営判断の精度を上げる行為なんです。』
経営者の状態が会社の状態をつくる
松山さん:
『もうひとつ大事なのは、経営者の状態は会社にそのまま反映されるということ。
社長が焦っていたら、社員も落ち着かなくなる。
社長が疲れていたら、組織全体の雰囲気もどんよりしてくる。
逆に、経営者が余白を持って笑顔で働いていると、チームのエネルギーが上がり、結果的にお客様満足度や生産性も上がっていきます。
休むというのは、単なるリフレッシュではなく、経営者という“最高の経営資源”のコンディションを整えることなんです。』
「整える」「任せる」「信じる」時代の新リーダーシップ
松山さん:
『実際に、私が支援してきた企業でも、「社長が週に1日は完全オフを取る」と決めただけで、売上が安定したり、スタッフが自主的に動くようになったりという変化が起きています。
社長がいない日をつくることで、スタッフが成長し、組織に“自走力”が生まれるんですね。
これは、まさに「休むことが経営戦略になる」典型的なパターンです。
また、「働く時間を減らしながら利益アップする」と経営者が決断することで、初めてそれを実現するためのマーケティング戦略にアンテナを張れるようになります。
ですから私は、「休む経営」は“甘え”ではなく、“仕組みづくりの一部”だと考えています。
頑張り続ける経営から、「整える」「任せる」「信じる」経営へ──。
それこそが、これからの時代に求められる新しいリーダーシップの形だと思っています。』

休むことで業績が上がった企業事例
家族との時間を取り戻して売上5倍に──トレーニングジム経営者の変化
実際に「休む経営」で成果を上げた企業事例はありますか?
松山さん:
『まず一つ目は、関西でパーソナルトレーニングジムを経営されている方のお話です。
この方は「妻や娘と幸せな時間を過ごすためにもっと稼ぎたい」という思いで独立されたのですが、実際には、思うように経営が安定せず、焦るあまり休みも取らず、毎日朝から晩まで働きづめの生活を続けていました。
ところが、頑張れば頑張るほど結果が出ないばかりか、奥さんや幼い娘さんとの関係が急激に悪化してしまったんです。
このとき私がアドバイスしたのは、「長時間労働をやめて、最低でも週に1日は完全休業日をつくり、家族のためだけに使う日を設けましょう」ということでした。
最初は不安そうでしたが、素直に実践してくださって──そこから驚くほどの変化が起きたんです。
まず、家族関係が劇的に改善し、娘さんとも毎日お風呂に入るほど仲良くなりました。
奥さんとも数年ぶりに結婚記念日を祝うことができたそうです。
そして何より驚くべきは、その後の業績。なんと売上が5倍以上に伸びたんです。
なぜこんなことが起きたかというと、「心の余白」ができたことで、判断や行動の質が一気に上がったからです。
焦りの中で手を打つのではなく、「お客様が本当に求めている価値」を見つめ直せるようになった結果、ファンが増え、紹介やリピートが自然に起こるようになりました。
つまり、“休むこと”が経営再建のスイッチになったんです。』
「院長が整う」と医院が変わる──歯科医院で起きた奇跡
松山さん:
『もうひとつ印象的だったのが、関東で歯科医院を経営されている先生のケースです。
この院長先生はとても真面目で努力家な方で、「スタッフのため」「患者さんのため」と自分を後回しにして働き続けていました。
朝は誰よりも早く出勤し、夜は最後に帰る。休診日もセミナーや勉強会で埋まっていて、ほとんど“休みゼロ”の生活だったそうです。
ですが、いつしか医院の雰囲気が重くなり、スタッフの離職が続くようになりました。
原因を探ると、スタッフたちは「院長がいつもピリピリしている」「話しかけづらい」と感じていたんです。院長先生ご自身も、「感情をコントロールできなくなっていた」と後におっしゃっていました。
そこで私は、「思い切って休みを“戦略的に”取りましょう」と提案しました。
まずは週に半日でもいいから“完全に医院のことを考えない時間”をつくる。
最初は「そんなことをしたら患者さんに迷惑をかける」と不安を口にされていましたが、実際にやってみると、むしろ真逆の結果が出ました。
数週間後には、スタッフの表情が明るくなり、医院の雰囲気が柔らかく変化。
それに合わせて患者さんからの口コミが増え、新規患者数も右肩上がりになりました。
スタッフからも「先生が笑顔だと私たちも安心して働けます」と声が上がり、結果的に離職率が大きく改善したんです。
この先生が印象的な言葉をくださっていて、「休むことで、自分の機嫌を取ることが経営の一部だとわかりました」とおっしゃっていました。
社長や院長が“整っている状態”でいることが、最高の経営資源なんですよね。』
長時間労働から抜け出す最初の一歩
「休むことは悪いことではない」と気づくことから
「休めない」と悩む経営者が最初に踏み出すべき一歩は何でしょうか?
松山さん:
『多くの経営者がおっしゃる「休めない」は、突き詰めると「休むことに罪悪感がある」なんです。
「自分が休んだら売上が落ちるんじゃないか」「スタッフに示しがつかないんじゃないか」──そう感じて、結局また働いてしまう。
だから、最初の一歩は“休むことを悪いことだと思わない”という意識を持つことだと思います。
休む時間が課題とチャンスを見つける
そのうえで、経営者に取り組んでほしい具体的な行動としては、「週1日以上の“完全休業日”を設定する」「1日7時間以上は働かない」「“50分集中+10分休憩”のサイクルで働く」を推奨しています。
長時間労働というのは、実は「仕事量の問題」ではなく、「心の焦りの問題」であることが多いんです。
焦っているときほど、「もっとやらなきゃ」「止まったら終わる」と思い込んでしまう。
でも実際は、止まった瞬間にしか見えない“課題”や“チャンス”があるんです。
それを見つけるための時間を作ることが、経営を変える起点になります。
阪神タイガースにも通じる“休ませる=成果を最大化する”法則
少し余談ですが、2025年シーズンで阪神タイガースの藤川球児監督が、就任1年目にして圧倒的なリーグ優勝を果たしましたよね。
その秘訣は、選手のコンディション調整を最優先にして、主力を含む全ての選手に無理をさせなかったことだと感じています。
結果として、ケガ人をほとんど出さず、多くの選手がキャリアハイの成績を残しました。
これはまさに「休ませる=成果を最大化する」という“休む経営”の原理と同じです。
経営者もチームも、常に全力では続きません。
大切なのは、休みながら最高のパフォーマンスを発揮できる“リズムのある働き方”をつくることです。』
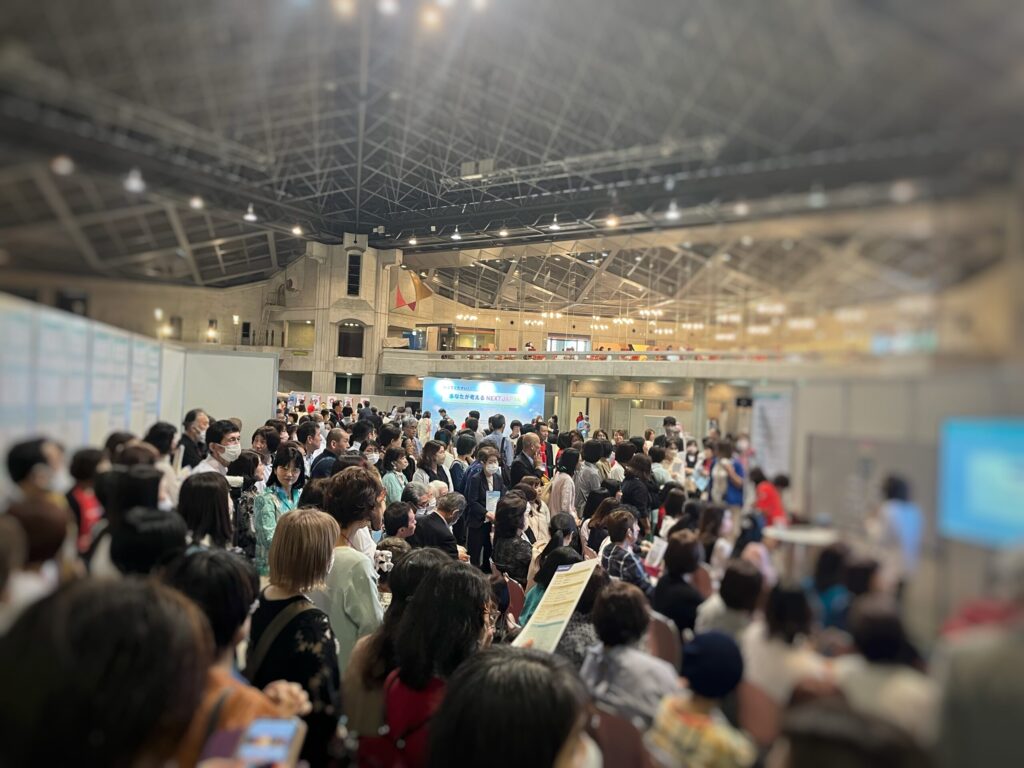
講演・研修で伝えたいメッセージ
経営者が幸せに働くことこそ最高の経営戦略
講演や研修では、どのようなメッセージを伝えているのですか?
松山さん:
講演や研修で一番お伝えしたいのは、「経営者が幸せに働くことこそが、最高の経営戦略である」というメッセージですね。
多くの経営者が「会社を良くするためには、まず社員を幸せにしないと」と考えますが、実は順番が逆なんです。
経営者自身が整っていない状態では、どんなに理念を語っても組織には伝わらない。
だから私はいつも、「自分を犠牲にする経営から、自分を大切にする経営へ」転換してほしいとお話ししています。
「休むことは逃げではなく信じる力」
講演ではよく、「社長が機嫌よく働いている会社は、社員の定着率も売上も高い」とお話しします。
結局のところ、会社の雰囲気は社長の心の状態そのものなんです。
社長が焦っていると、会社は慌ただしくなる。
逆に、社長がゆとりを持って笑っていると、社員も自然と動き、結果的に成果が上がる。
この“内面からの連鎖”を理解してもらうことを何より大切にしています。
また、講演では必ずこうお伝えしています。
「休むことは、逃げることではなく“信じる力”です」と。
自分やチームを信じて任せる勇気があるからこそ、安心して休める。
その信頼関係がある組織ほど、強くて長く続くんです。
ですから私は、「休む経営」や「両想いビジネス」を単なる働き方改革ではなく、“人を信じる経営の形”として伝えています。
頑張りすぎるのをやめ、自分自身を信じ、仲間を信じる。
その循環が起きたとき、会社も人生もうまく回り出します。
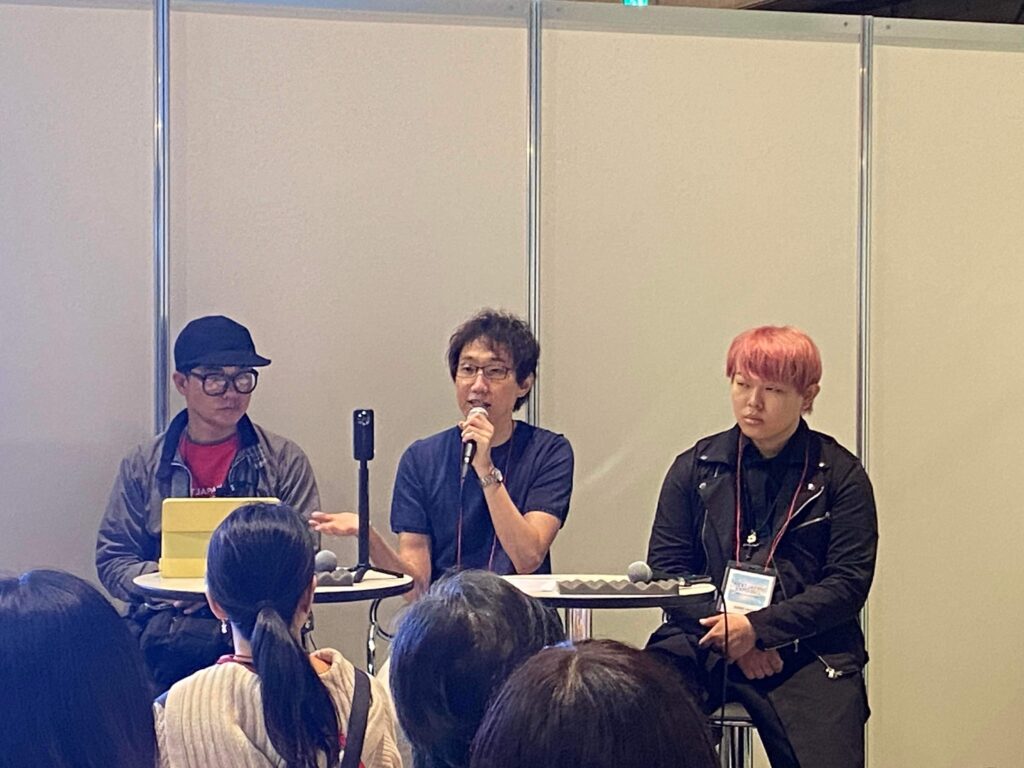
目指すのは「両想いの経営」が当たり前の社会
経営者が自分と仲直りすることが、すべての始まり
最後に、今後目指している社会の姿を教えてください。
松山さん:
私が目指しているのは、“ビジネスを通じて経営者が自分自身と両想いになるのが当たり前の社会”です。
経営者が自分の本心を大切にし、無理をしなくても成果が出て、家族やスタッフ、お客様、取引先、社会と“両想いの関係”を築ける──そんな世界をつくりたいと思っています。
思考術やマーケティング戦略を駆使して、こうした理想が「新しい経営のスタンダード」になれば嬉しいですね。
“頑張りすぎない経営者”が日本経済を豊かにする
これまで多くの経営者を支援してきて感じるのは、「働きすぎている人ほど、本当は優しい」ということです。
誰かのために頑張りすぎて、自分を後回しにしてしまう。
でも、実は“自分との関係が整っていないと、他との関係も整わない”んです。
だからこそ、まずは経営者自身が自分の心と仲直りすることが、すべての始まりだと思っています。
本当に人を幸せにできるのは、自分が満たされている人だけ。
だから私は、“頑張りすぎない経営者”が増えることが、結果的に経済を豊かにすると信じています。
幸せが循環する社会を仲間とともに創る
今後は、「両想いビジネス」や「休む経営」の考え方をより多くの経営者に届け、“働くことと幸せが両立する時代”を実現していきたいと思っています。
講演・セミナー・書籍・連載・コンサルティングなどを通じて、経営者だけでなく、スタッフや家族までもが笑顔でいられる企業を一社でも多く増やしたい。
そして、最終的には“幸せが循環する社会”を仲間たちと一緒につくっていく──それが、私のこれからの使命です。

松山さん、ありがとうございました!
Contact お問い合わせ
講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。
気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。
5営業日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。



