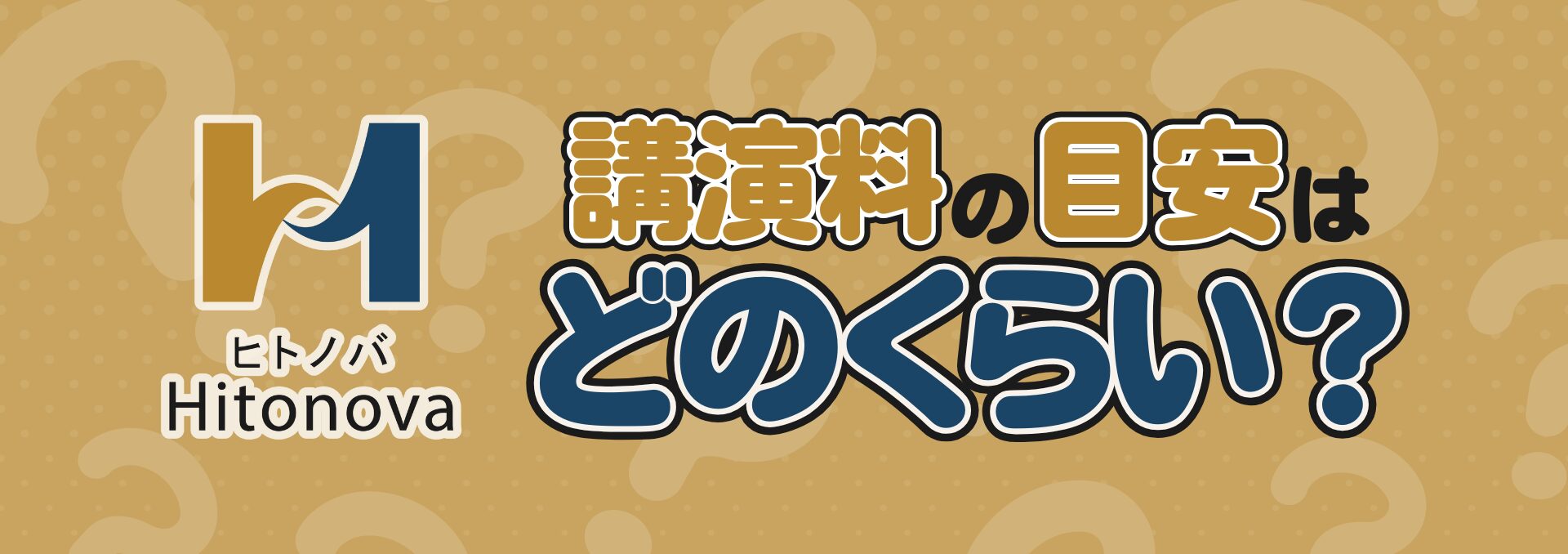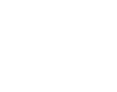岡田晃 おかだあきら
大阪経済大学 特命教授/経済評論家
プロフィール
慶應義塾大学経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。編集委員を経てテレビ東京へ出向し、「ワールドビジネスサテライト」などでキャスター・プロデューサーを務める。ニューヨーク駐在時にはアメリカ経済・政治動向を現地から発信し、同支局長・米国法人社長としても活躍。2006年に独立し、現在は大学での教育・執筆活動を通じて、経済を多角的に解説している。
講演では、日本と世界経済の動きをマクロからミクロまでわかりやすく読み解き、歴史的視点と最新データをもとに今後の展望を提示する。長年の取材経験で得た現場感と独自の分析をもとに、企業経営や個人のビジネス戦略に生かせる視点を提供し、聴講者に前向きな活力を与える内容となっている。
テーマ
出身・ゆかりの地
経歴
1947年 大阪市に生まれる
1971年 慶應義塾大学経済学部卒業
同年 日本経済新聞入社
松山支局、地方部、産業部などを担当
1987年 日本経済新聞 編集委員
1991年 テレビ東京出向
「ワールドビジネスサテライト(WBS)」マーケットキャスター
1994年 テレビ東京 経済部長
「WBS」プロデューサー
各種経済番組のプロデューサー、キャスター、コメンテーター
1998年 同 NY駐在(~2003年)
NY支局長、テレビ東京アメリカ(米国現地法人)社長
2003年 同 理事・解説委員長
2006年 テレビ東京退職
同年 経済評論家として独立(~現在)
大阪経済大学客員教授
2022年 大阪経済大学特別招聘教授
2025年4月 大阪経済大学特命教授(~現在)
主な講演テーマ
<2026年度の重点テーマ>
高市政権は日本経済を救えるか
~2026年の景気展望と政治動向
大方の予想を覆して高市早苗氏が自民党総裁選で勝利し、女性として初めて首相に就任した。これを受け、株価は大幅に上昇し、高市新政権の経済政策への期待が高まっている。高市氏の経済政策は「成長重視」を掲げ、改革にも積極的な姿勢を示しており、日本経済が本格的な復活に向かう可能性がある。
この数年、政治の停滞とともに経済政策の停滞も続いていたが、その中でも景気が大きく崩れることはなく、株価の回復が進んでいたことは、日本経済が着実に底力をつけてきた証といえる。こうしたタイミングで高市首相が登場したことは、日本経済にとって大きなチャンスである。
講演では、歴代内閣の経済政策を検証しつつ、高市新政権の経済政策を展望し、その可能性と課題を明らかにする。 ×
<2026年度の重点テーマ>
・「昭和100年」に学ぶ日本経済復活への教訓とヒント
・「昭和100年」にみる日本の底力~令和の時代に日本経済は復活する!
昭和から令和へ――日本経済の100年から未来を読む。
2026年、昭和改元から満100年を迎えます。激動の昭和時代には、戦争・復興・高度成長など、現代の日本経済を形づくる多くの転機と教訓がありました。度重なる危機の中でも、先人たちは知恵と行動で「ピンチをチャンスに」変えてきたのです。
経済ジャーナリストの岡田氏は、昭和46年(1971年)から日本経済を取材し続け、50年以上にわたり数々の経済の現場を見つめてきました。現在はその経験をもとに「昭和経済100年の歩み」を研究し、令和日本の再生に向けた視点を発信しています。
本講演では、昭和から令和へと続く日本経済の軌跡をひもときながら、過去の成功と失敗の歴史から学ぶ“復活のヒント”を提示。激動の時代を生き抜く企業やビジネスパーソンに、前向きなエネルギーと希望を届けます。 ×
<2026年度の重点テーマ>
「新ジャポニスム」が日本経済を救う
世界の注目を集めるニッポン
世界が再び日本に熱視線――「新ジャポニスム」が令和経済を動かす。
近年、日本は世界中からかつてない注目を集めています。
訪日外国人(インバウンド)は過去最高を更新し、日本食・アニメ・伝統文化など「日本らしさ」への関心が世界的に高まっています。さらに、高品質なモノづくり技術への再評価も進み、日本ブランドの存在感が再び強まっています。
こうした潮流は、19世紀後半に欧米で巻き起こった「ジャポニスム」を彷彿とさせるものであり、まさに“新ジャポニスム(Neo Japonisme)”と呼ぶべき現象です。
本講演では、文化と経済の関係をひもときながら、「新ジャポニスム」が令和日本の経済復活の牽引力となる可能性を探ります。観光、文化産業、輸出ビジネスなど多方面に示唆を与える注目の内容です。 ×
・2026年の国際情勢と日本経済の行方
・2026年の景気見通しと今後の企業戦略
・トランプ旋風で揺れる国際情勢――それでも日本経済は復活する!
トランプ関税の影響と日本経済の行方――“トランプ旋風”をどう乗り越えるか。
トランプ関税問題は一応の決着を見せたものの、その影響は今後もじわじわと日本経済に波及していくと見られます。トランプ氏の外交姿勢や日米関係の行方など、国際情勢は依然として不透明です。
本講演では、トランプ前大統領の真の狙いと政策の背景を冷静に分析し、日本経済への実際の影響度を多角的に読み解きます。
一方で、最近の日本経済は企業業績や株価、雇用など多くの分野で「過去最高」「バブル期以来」といった好記録が続出。中長期的に見れば、日本経済の底力と回復基調は確実に強まっています。
講師はデータと現場取材に基づき、トランプ関税後の日本経済の展望と、完全復活への道筋を具体的に提示します。国際経済の動きを踏まえながら、“逆風をチャンスに変える”ための視点を共有します。 ×
地方を元気に!
――日本経済再生と地方創生の展望
“新ジャポニスム”が地方を変える――インバウンドと地域経済再生の新たな潮流。
世界中で高まる日本ブームが、いま「新ジャポニスム」として新たな経済現象を生み出しています。
訪日観光客(インバウンド)の増加は、宿泊・飲食・小売といった消費拡大だけでなく、地方での雇用創出、設備投資、インフラ整備など、幅広い地域経済への波及効果をもたらしています。
さらに、日本食・農産物・日本酒などの輸出が拡大し、農業や地方産業の活性化にもつながる動きが顕著です。
本講演では、「新ジャポニスム」がもたらす経済効果と、その流れをどう地方創生・地域ビジネスの成長へと結びつけていくかを、データと事例を交えて解説します。
“日本人気”を持続的な発展につなげるためのヒントが詰まった内容です。 ×
少子高齢化時代の日本経済と企業戦略
少子高齢化をチャンスに――DXと人材活用が拓く“日本経済の次の成長”
日本が直面する「少子高齢化」は、長らく経済成長を阻む要因とされてきました。
しかし実は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、女性の活躍拡大、柔軟な働き方改革など、社会構造を変える取り組みこそが、この課題を乗り越える力となり得ます。
経済ジャーナリスト・岡田氏は、日本経済新聞在籍時の1979年に、いち早く「高齢化社会」を総合的に取材・分析。年金・福祉・企業経営など幅広い分野にわたる影響を探り、その成果を連載・書籍として発表しました。以来40年以上にわたり、このテーマを継続的に追い続けています。
本講演では、長年の取材経験をもとに、少子高齢化社会を成長のチャンスに変える視点を提示。
DXや人材多様化を軸に、日本経済が持続的に発展するための具体的な方向性を示します。 ×
・「課題こそニーズだ」――ピンチをチャンスに変える経営
・危機の時代を乗り越える企業戦略――生き残りの条件とは?
・少子高齢化時代の企業戦略――キーワードは「DX」「働き方改革」「市場ニーズ」
・ここが違う!好調企業の‟秘密”――危機を乗り越える中小企業経営とは?
・事業承継成功の秘訣――企業を永続的に発展させる「10のポイント」
現場の経営者たちに学ぶ――中小企業の成長と事業承継のヒント
長年にわたり日本経済新聞やテレビ東京の記者として、数多くの企業と経営者を取材してきた岡田氏。現在は大阪経済大学で社会人向け公開講座「北浜・実践経営塾」を主宰し、産業界を代表する経営者をゲストに迎えて、自社の戦略や経営哲学、事業承継のリアルな体験談を紹介している。
本講演では、これまでの豊富な取材経験と実践の場から得た知見をもとに、経営者が直面する課題や中小企業が成長するための実践的アプローチをわかりやすく解説。リーダーの意思決定、組織づくり、後継者育成など、経営の本質に迫る内容です。
企業経営や事業承継に携わるすべての方に、新たな気づきと行動のヒントを提供します。 ×
江戸最大のヒットメーカー・蔦屋重三郎に学ぶ
企業家精神と経営戦略
蔦屋重三郎に学ぶ――時代を動かした“江戸の起業家精神”と経営戦略
2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』の主人公として注目される蔦屋重三郎。
彼は、歌麿・写楽・北斎といった才能を世に送り出し、江戸の出版・浮世絵文化を牽引した伝説のプロデューサーです。蔦屋が築いたビジネスモデルは、まさに“江戸のコンテンツ産業”の先駆けでした。
その成功の背景には、時代の変化と市場ニーズを的確に読み取り、独自の発想で差別化を図った戦略力があります。弾圧という逆境の中でも挑戦をやめず、創造と革新で危機を乗り越えた蔦屋の姿勢は、現代の企業経営にも通じるものです。
本講演では、ジャポニスムの源流にもなった浮世絵文化と蔦屋重三郎の経営哲学を通じて、
“時代を変える発想と挑戦”のヒントをお伝えします。 ×
織田信長のイノベーション戦略
「常識」を変えた経営革命に学ぶ
織田信長に学ぶ――常識を打ち破るイノベーションと経営戦略
戦国時代において、天下統一へと突き進んだ織田信長の原動力は「イノベーション」でした。
桶狭間の戦いでの大胆な戦術、宗教勢力の武装解除を目的とした比叡山焼き討ち、規制緩和や兵農分離、鉄砲・火薬の大量導入など――そのどれもが常識を覆す改革的な行動でした。
そして「天下布武」というビジョン自体が、時代を変えるイノベーションだったのです。
本講演では、信長の戦略思考やリーダーシップを現代経営に重ね、中小企業が変化の時代を生き抜くための発想転換と実践のヒントを提示します。
歴史に学ぶイノベーションの本質を通じて、「勝ち残る企業経営」と「挑戦する組織づくり」を考える内容です。 ×
<歴史から経済・経営を学ぶ>
・徳川家康に学ぶ経済戦略
――日本経済復活のヒントがここにある
・「江戸」の名君から学ぶ危機突破力と経済復活策
――保科正之、徳川綱吉、徳川吉宗、田沼意次、上杉鷹山…
・「江戸」の商人から学ぶ危機突破力と経営戦略
――鴻池、三井、近江商人、蔦屋重三郎……
・「江戸時代」に学ぶ日本経済復活のヒント
・徳川家康に学ぶ事業承継の最強モデル
・戦国武将に学ぶ事業承継成功の秘訣
――徳川家康、武田信玄、上杉謙信など
・真田幸村に学ぶ中小企業の生き残り戦略
・戦国武将に学ぶ中小企業の生き残り戦略
・「東の渋沢栄一・西の五代友厚」に学ぶ危機突破力と日本経済復活の展望
歴史に学ぶリーダーシップと経営戦略――戦国武将・江戸の名君・商人たちが教える“経済復活”の知恵
混迷する現代社会にこそ、歴史に学ぶヒントがあります。
戦国武将の決断力、江戸の名君の改革精神、そして商人たちの知恵と実行力――。それらはすべて、令和の日本経済や中小企業経営にも通じる“普遍の原理”です。
本シリーズでは、徳川家康・上杉謙信・武田信玄・真田幸村など戦国武将のリーダーシップから、徳川綱吉・吉宗・田沼意次・上杉鷹山・保科正之といった名君の政策、さらに鴻池・三井・近江商人・蔦屋重三郎など江戸の実業家の経営哲学までを取り上げ、
「事業承継」「経営戦略」「危機突破力」「日本経済復活」などの視点で現代に活かせる教訓を読み解きます。
歴史を“過去の物語”ではなく、“未来を拓く経営の教科書”として捉え直す――。
経営者、ビジネスリーダー、自治体・団体の皆様におすすめのシリーズです。 ×
書籍・メディア出演
書籍紹介
クリックすると、詳細が表示されます。
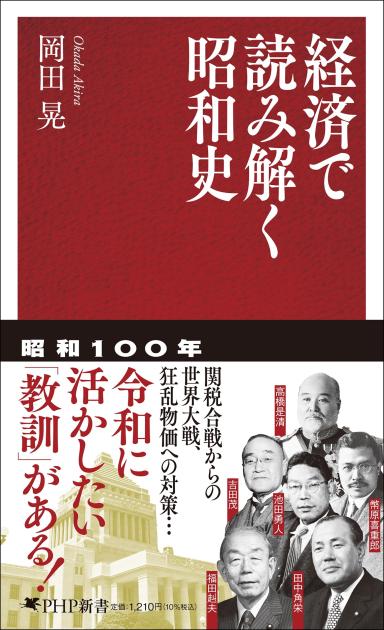


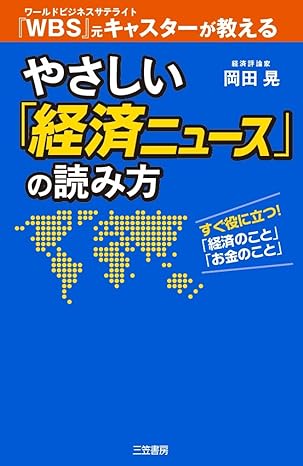
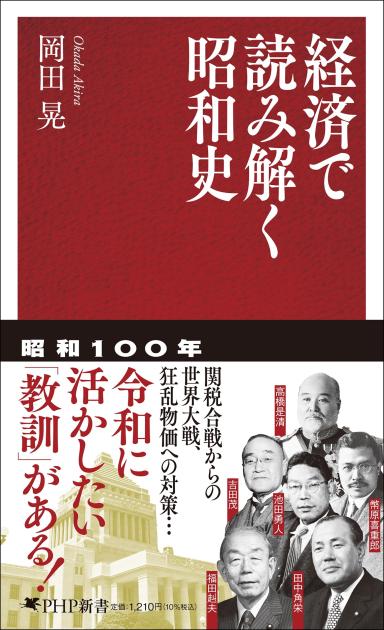
経済で読み解く昭和史
『昭和100年』――激動の時代に、日本はどう立ち上がったのか。
関税合戦に端を発した世界恐慌、戦争と敗戦、狂乱物価、そして奇跡の復興と高度経済成長、バブル経済へ――。
「昭和」は、危機と挑戦の連続だった。しかし日本は、そのたびに立ち止まり、考え、前へ進んできた。
本書は、昭和という100年に迫る激動の時代を「経済」の視点から通史で読み解く一冊である。恐慌で始まった昭和、戦争の時代、敗戦からの復興、高度経済成長とその終焉、そしてバブルへの道。その一つひとつを丹念に辿ることで、単なる歴史の出来事ではなく、現代にも通じる「判断」と「選択」の積み重ねが浮かび上がる。
なぜ昭和の日本は、あれほど元気だったのか。
困難な時代に、何を信じ、何を変え、何を守ったのか。
昭和百年という節目に、過去を懐かしむためではなく、令和の日本経済を立て直すための「教訓」を探る。
通史で読むからこそ見えてくる、未来へのヒントがここにある。

徳川幕府の経済政策――その光と影
通史で読み解くからこそ、見えてくるものがある
家康から綱吉の時代は戦後の高度経済成長、新井白石の「正徳の治」は平成のバブル崩壊といったように、江戸時代の経済変動は現代と似ている点が多い。デフレからの脱却に繋がった、吉宗による「享保の改革」の功罪とは。田沼意次の構造改革が成功しなかったのはなぜか……。徳川幕府の経済政策の成功(光)と失敗(影)に学ぶ。

明治日本の産業革命遺産 ラストサムライの挑戦!技術立国ニッポンはここから始まった
「日本の奇跡」と言われる明治の産業革命の礎は、幕末のサムライたちによって準備されていた。製鉄、造船、石炭産業の現場では、藩の垣根を超えて技術を共有し、奮闘する人々の熱いドラマがあった!
例えば、製鉄のもととなった伊豆の反射炉の技術は、佐賀藩と伊豆の代官・江川英龍が協力して研究が始まり、佐賀から薩摩へ、さらに水戸藩を経由し、最終的には釜石の洋式高炉に結実した。それが明治時代に官営釜石製鉄所や官営八幡製鉄所へとさらなる発展を遂げ、現在の新日鉄住金に至る。
造船に関しては、島津斉彬の命を受けて幕府の長崎海軍伝習所で学んだ薩摩藩士・五大友厚は、トーマス・グラバーらと共に長崎の小菅修船場を建設した。これが現在の三菱重工長崎造船所につながっていく。岩崎弥太郎、弥之助、久弥の3代に渡る三菱重工業の社長たちの事業拡大の歴史とも重なる。
“軍艦島“で知られる石炭産業の発展においては、福岡藩士だった團琢磨の働きがめざましく、彼の見識と技術導入へのアイデア、決断力が、石炭産業の多大な発展を促した。
幕末から明治の激動の時代に、政治の争いとは無関係に、日本の未来を考えて奔走した若きサムライたちや現場の無名の職人たちの、ひたむきさやチャレンジ精神を感じる熱い一冊です。
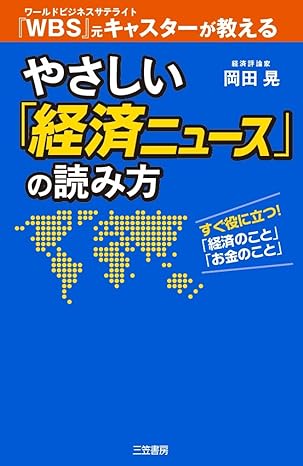
やさしい「経済ニュース」の読み方
アベノミクス、TPP、円安、株、消費増税……いま、経済ニュースが面白い!!
『日本経済新聞』『テレビ東京』など“報道の最前線"で
活躍してきた著者ならではのするどい視点で
経済を“表と裏から"読み解くコツを教えます!
メディア
- テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト(WBS)
- テレビ東京系列「モーニングサテライト」
- テレビ東京系列「クロージングベル」
- テレビ東京系列「あすの日経朝刊」
- テレビ東京系列「ニュースワイド 11」
- テレビ東京系列「ニュースウェーブ 615」
- 東京MX テレビ「東京マーケットワイド」
- BSジャパン 「こちら経済編集長」
- ラジオNIKKEI「マーケット・トレンド」
- NHK 総合 「関西熱視線」(関西ローカル)
- NHK Eテレ 「知恵泉」
- インターネットTV「ストックボイス」
- その他、多数
その他の活動、所属団体など
- 景気循環学会
- 日本記者クラブ
- 一般財団法人「産業遺産国民会議」発起人
- 埼玉大学経済学部非常勤講師(2007~2010 年)
書籍
- 『経済で読み解く昭和史』(PHP新書)
- 『徳川幕府の経済政策――その光と影』(PHP 新書)
- 『明治日本の産業革命遺産 ラストサムライの挑戦!技術立国ニッポンはここから始まった』(集英社)
- 『やさしい「経済ニュース」の読み方』(三笠書房)
- 『これが高齢化社会だ』(共同執筆、日本経済新聞社)
- 『新・産業革命』(共同執筆、日本経済新聞社)
- 『21 世紀への企業戦略』(共同執筆、日本経済新聞社) など
連載
- 会社四季報オンライン「賢者は歴史に学ぶ」
- 公益財団法人産業雇用安定センター広報誌『かけはし』 「歴史に学ぶ ウィズコロナ時代の中小企業経営」
これまでの主な執筆
- 『マイナビニュース』連載「コロナ禍に打ち克つためにできること」
- 『マイナビニュース』連載「令和の時代に日本経済が復活するワケ」
- 『マイナビニュース』連載「経済ニュースの“ここがツボ”」
- 『会社四季報オンライン』連載「マクロデータはこう読むと面白い」
- 『KOTOBA』(集英社)連載 「明治の産業革命遺産――“日本の底力”のルーツを訪ねて」
- 『プレジデントオンライン』
- 『ダイヤモンドオンライン』
- 『歴史街道』
- 『月刊・経済広報』(一般財団法人経済広報センター)
- その他、多数
講演実績
一般向け
- 大阪経済大学の一般市民向け公開講座
- 他大学の一般市民向け生涯学習講座
- 地方自治体の一般市民向け生涯学習講座
- 金融機関(メガバンク、地銀、信金など)の一般市民・投資家向けセミナー
- 証券会社の一般市民・投資家向けセミナー
- 不動産関連会社の一般市民・投資家向けセミナー
特定顧客層向け
- 経済団体(各地の商工会議所、経営者団体、中小企業団体、法人会、業界団体など)の年次総会・定例会合・勉強会
- 企業の取引先・協力会社などとの会合・勉強会
- 企業の社内研修(役員研修、幹部研修など)
- 労働組合の組合内研修・勉強会
- 地方自治体首長・議員研修
- 地方自治体の職員研修
この講師のおすすめポイント
経済評論家であり、大阪経済大学特命教授の岡田晃(おかだあきら)氏は、
日本経済新聞とテレビ東京で長年にわたり経済報道の最前線を歩んできた、経済ジャーナリズムの第一人者です。
国内外の経済・金融・政治の動向を長期的な視野で分析し、最新のデータと実例をもとに“わかりやすく・前向きに”語る講演には、経営者やビジネスリーダーから高い支持を集めています。
テレビ東京時代にはニューヨーク支局長として5年間駐在し、米国経済や国際情勢を現場で取材。
その豊富な経験を活かし、講演では「昭和100年の経済史」「高市政権と日本経済」「新ジャポニスムと日本復活」「トランプ関税の影響」「DXと少子高齢化対策」など、
日本経済の過去・現在・未来をつなぐ多角的な視点で分析します。
さらに、歴史を経営の教科書として読み解く独自のシリーズ「歴史から経済・経営を学ぶ」では、
徳川家康や織田信長、上杉鷹山、近江商人などの戦略やリーダーシップを現代経営に重ね、
ピンチをチャンスに変える思考法、事業承継の成功モデル、中小企業の生き残り戦略など、実践的なヒントを提示します。
岡田氏の講演は、単なる経済解説にとどまらず、
経営者やビジネスパーソンが「今をどう読み、次にどう動くか」を考えるための実践的な示唆に満ちています。
明快で説得力のある語り口と前向きなエネルギーが聴講者の意欲を高め、
「元気になれる経済講演」「希望を感じる内容」として全国で高く評価されています。
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。



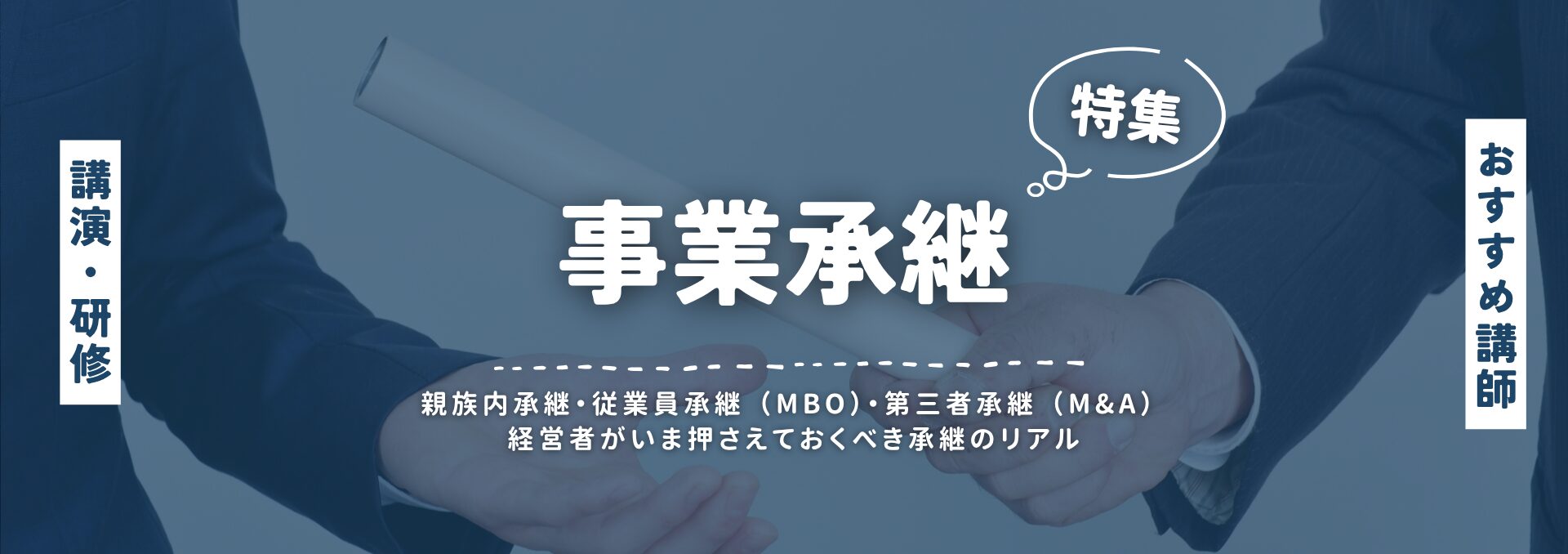
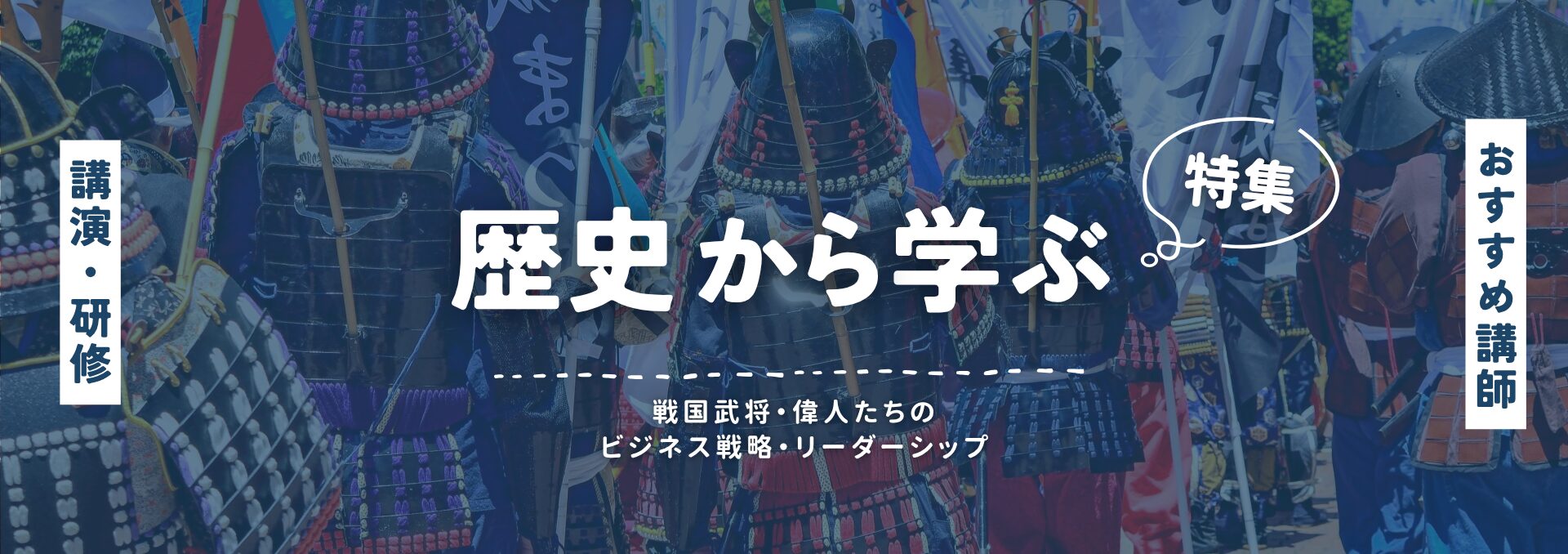

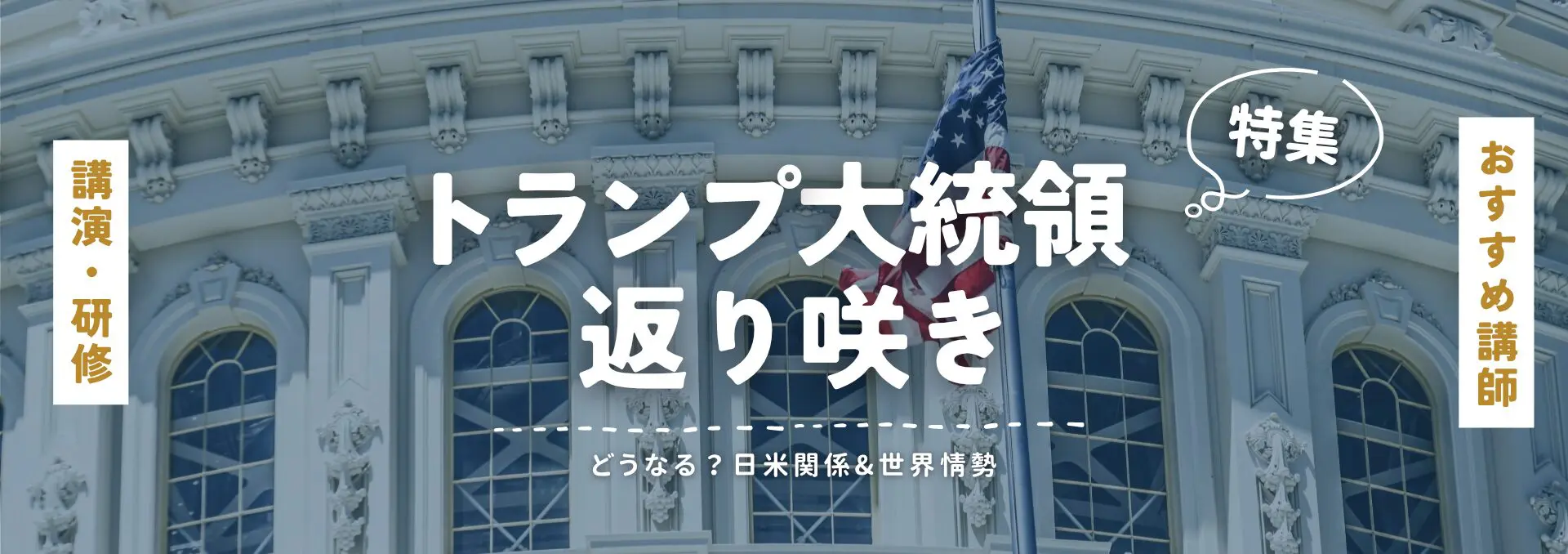
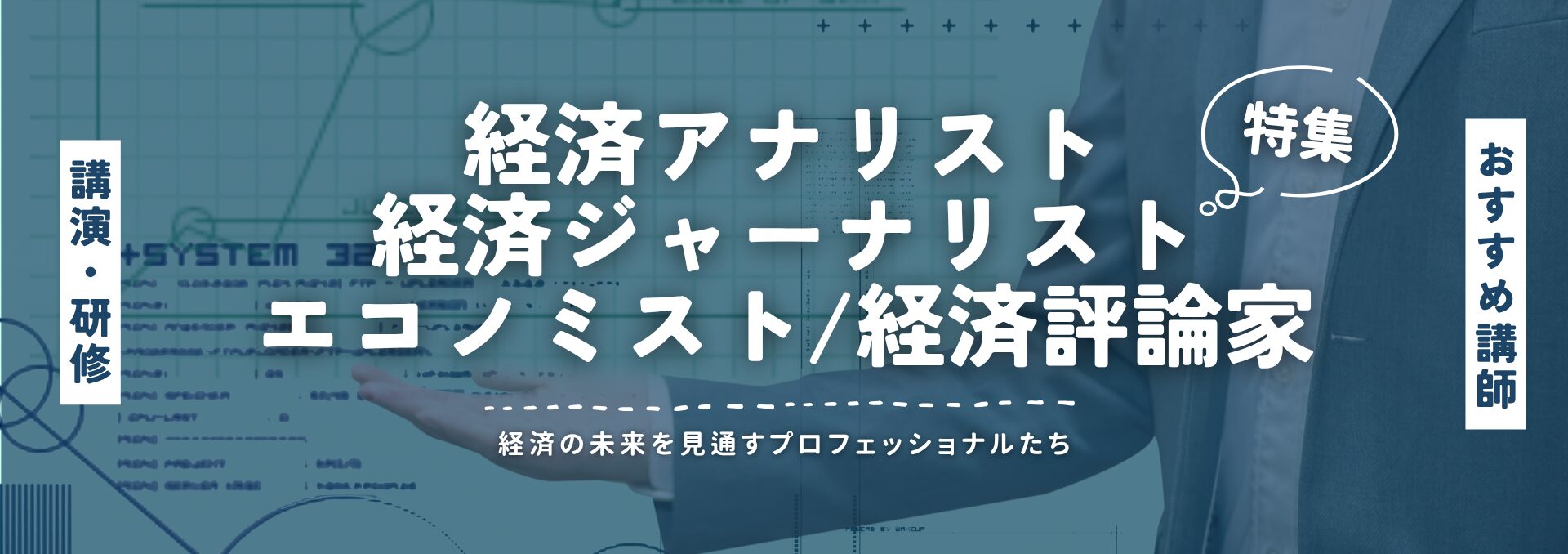
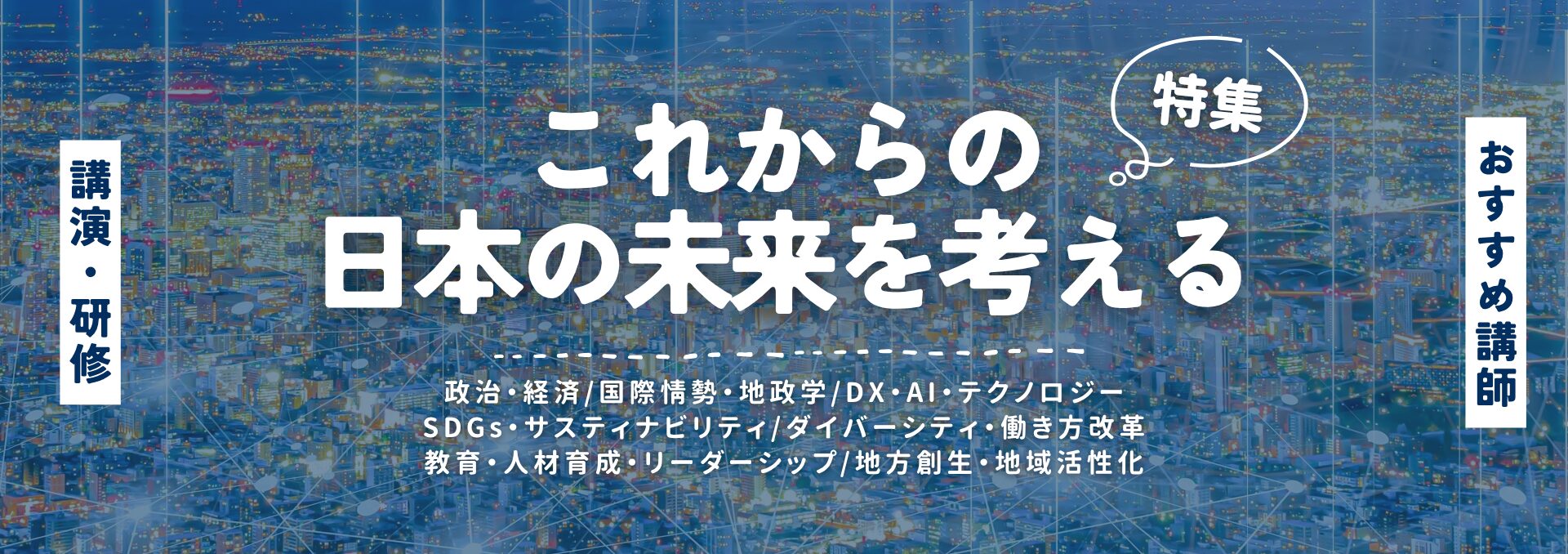
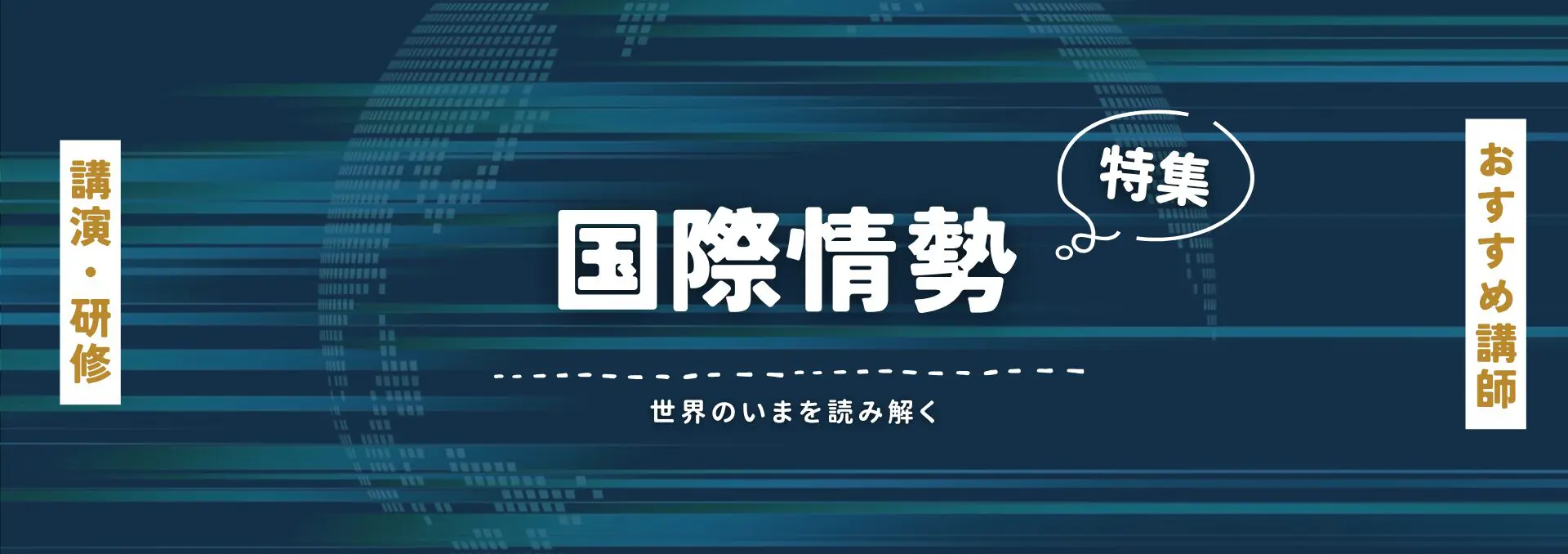
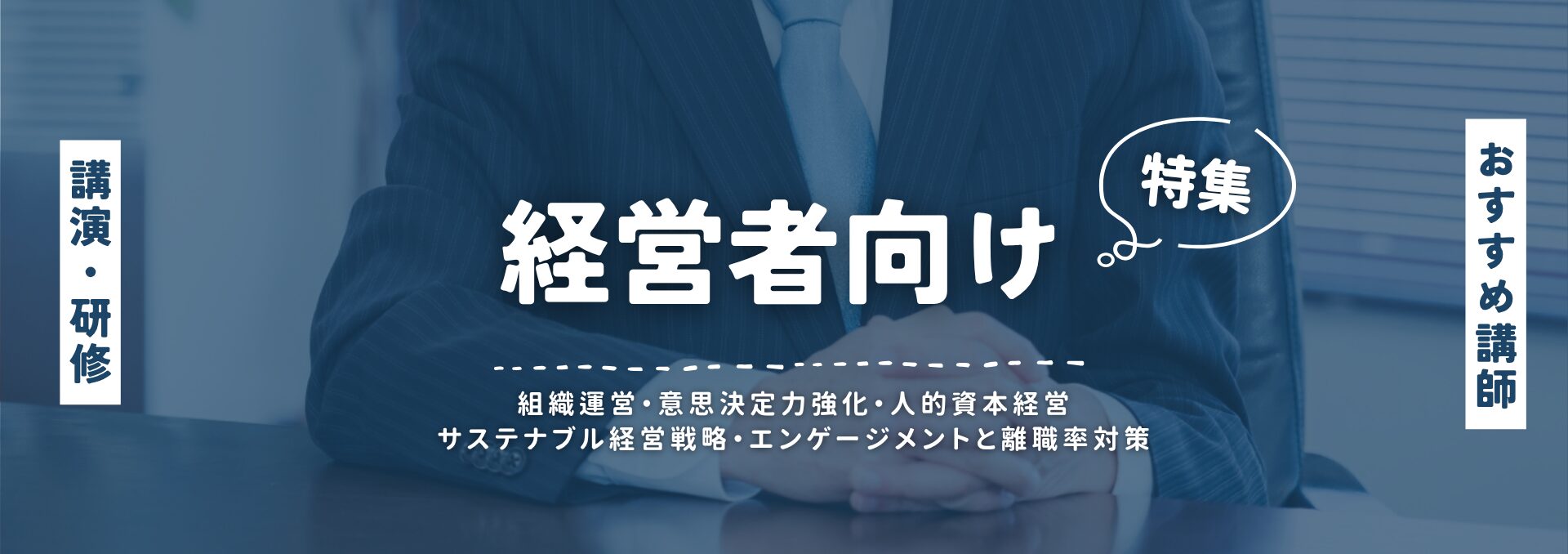
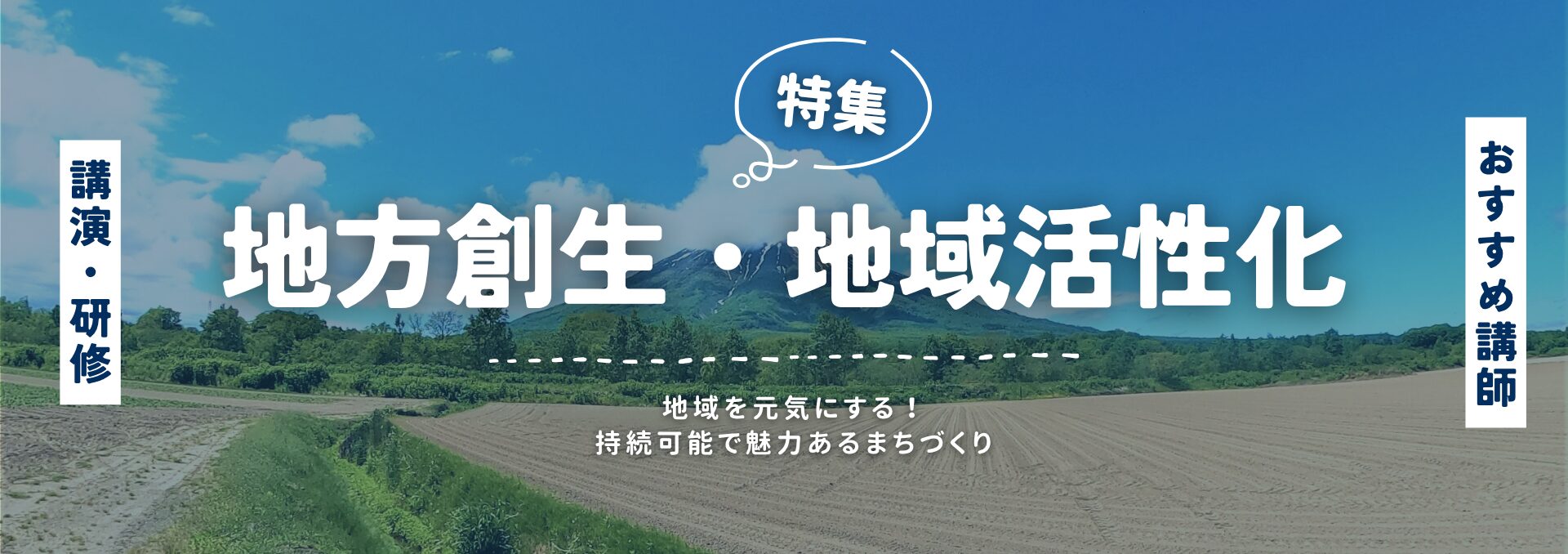
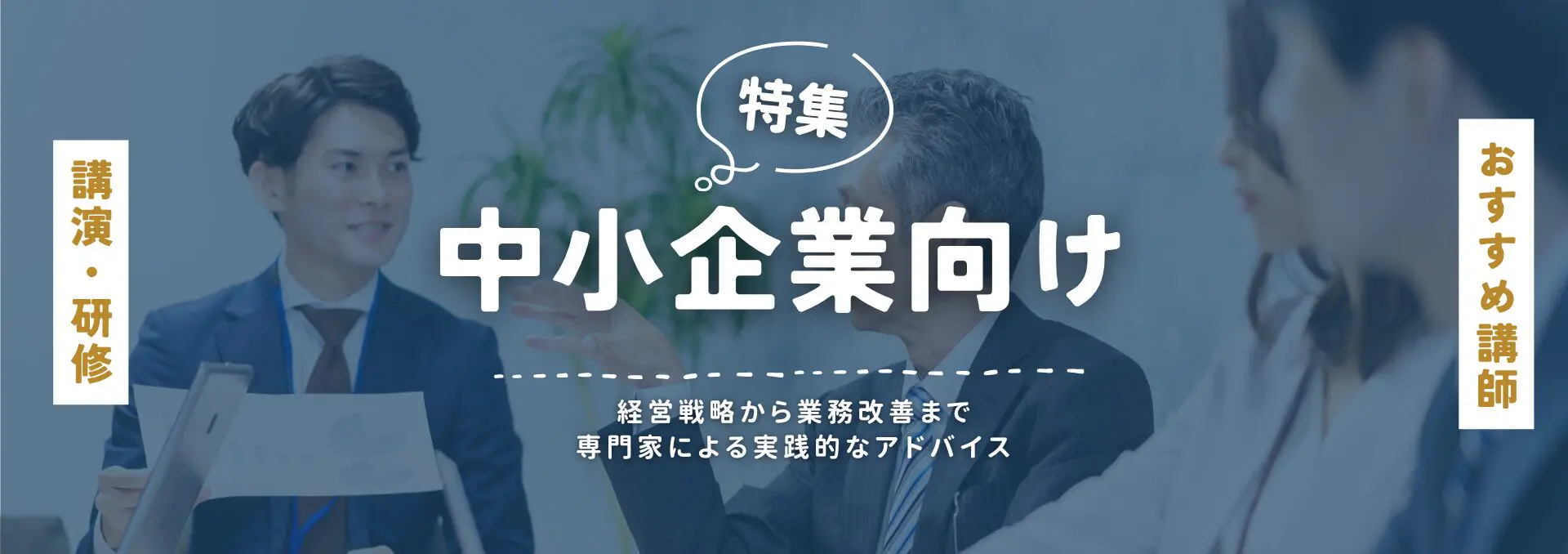
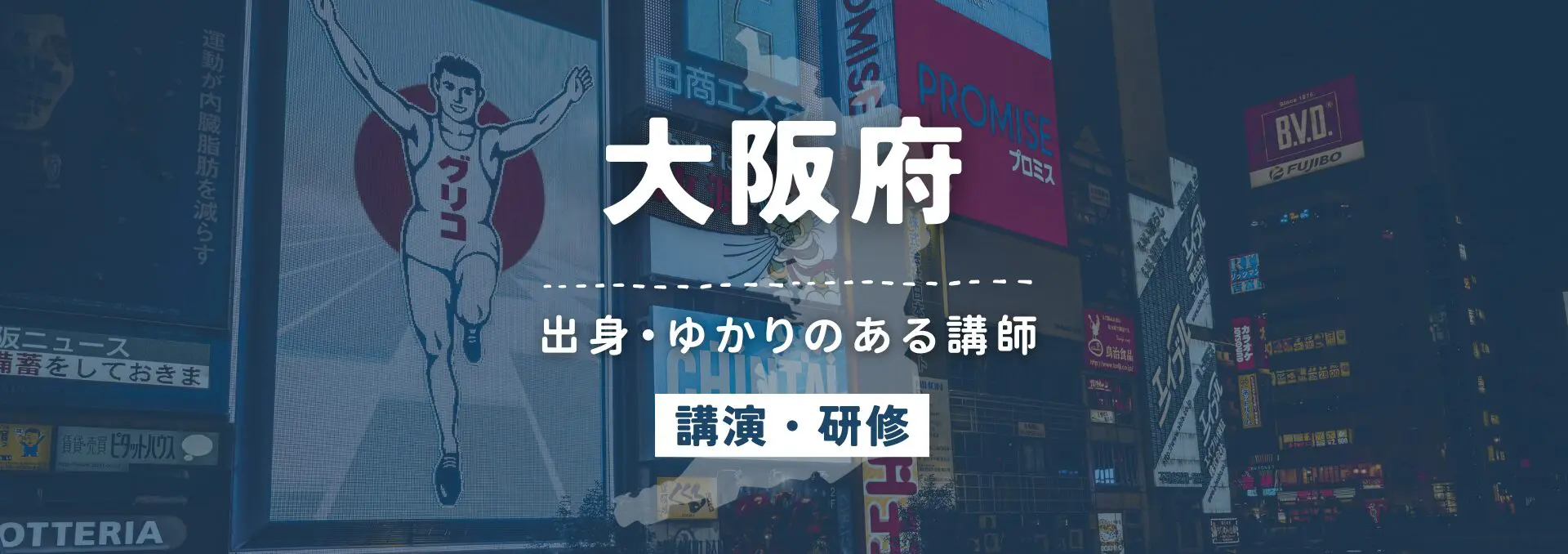
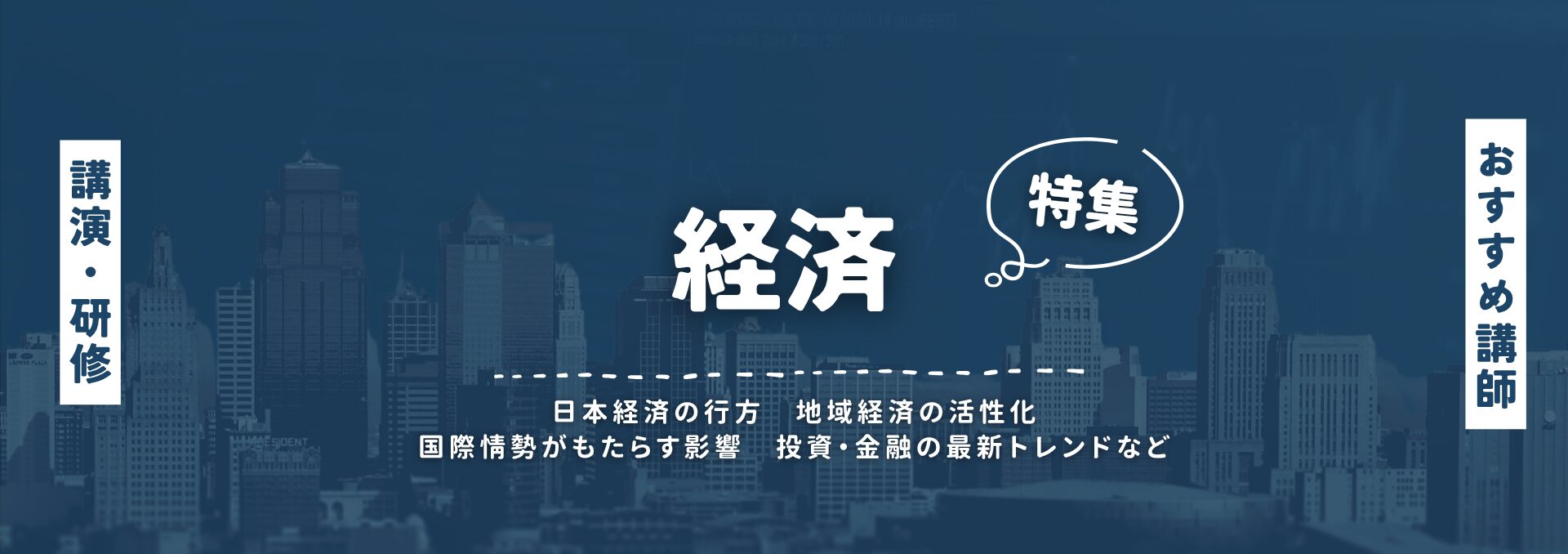

-scaled.jpeg)